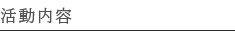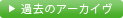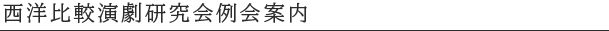
*オンライン(Zoom会議)方式
*前日の23日(金)にZoomリンクをメーリングリストで配信します。当日会議室に入室後、参加者名をフルネームにしてください。
*非会員の方は7月22日(木)までに氏名(必須)・連絡先メールアドレス(必須)・肩書きまたは所属(自由)を添えて事務局までご連絡ください。
パネルディスカッション
「演劇のナラトロジーをめぐって ―信用できない語り、パフォーマティヴィティ、焦点化―」
パネリスト 關智子(早稲田大学他非常勤講師)・山下純照(成城大学文芸学部・司会も)
ディスカッサント 岡本淳子(大阪大学大学院言語文化研究科)
このパネルのきっかけは昨年6月の本研究会における、今回のパネリストの一人山下の個人発表に対する、会場からの關による質問(およびその後の電子メールによる指摘)だった。山下は発表で、岩井秀人『ある女』を例として、最近の現代日本の戯曲の一部に、登場人物同士の対話ないし会話(および身体表現)によって進行する部分(これを演示と名づける)と、語り手による語りの部分の、特異な組み合わせが見られ―言うまでもなく両者の混合自体は演劇史とともに古い―この組み合わせによって生み出される効果ないし機能に注目すべきものがあるという指摘をした。語りの内容とは食い違う形で、そのあとの演示が進行するのである。このような語りはナラトロジーで言う「信頼できない語り(unreliable narration)」に当たる。これに対し關は、信頼できる/できないの基準を問題化した。山下は当初、演示されたものが信頼性の基準となると答えたものの、その後の關の(メールによる)指摘により、再考の必要性に気づいた。
今回のパネルでは改めて、まず演劇における語りの信頼性の問題を掘り下げる。ただし今回は、narrationとしての語りのみならず、演示も含めたnarrativeとしての<語り>まで広げて考察し、演示の部分にも信頼できない<語り>があるという仮説を検証する(關の個別報告)。これが今回の第1の柱である。
今回の第2の柱は<語り>の行為遂行性performativityである(關の個別報告)。J・L・オースティンの『言語と行為』において演劇は考察の対象から外されているが、いくつかの作品は、演劇における言表行為が行為遂行的に機能する不/可能性について自己言及的に提示している。演劇においてオースティンの行為遂行的言表行為がいかなる形で成立可能/不可能であるかを検証する。
今回の第3の柱は焦点化(focalization)の問題である。ジュネットによりそれまでの視点(point of view)の概念に代わって導入されたこの分析道具は、演劇のナラトロジーにとって意義深い。わかりやすい例は回想劇である。通常、回想形式についての暗黙の約束事として不問に付されている焦点化の2層構造の存在(ある人物による想起/当人も登場する形での内容の演示)を指摘したい(同様の指摘をおこなっている映画のナラトロジー研究にも触れる)。そしてこのことは信頼できない<語り>の問題にも適用可能であることを述べる。その上で、実は焦点化の多層構造は演劇的ナラティヴの本質に属しているのではないかということを吟味する。そして、本来多層的な演劇的ナラティヴの焦点化を、さらに意識的に多様化・多重化した劇形式があることを具体例に即して論じる。これは信頼できない<語り>の問題圏を越え、演劇ナラトロジーの論点を拡大する試みである(山下の個別報告)。 発表①
關智子
「嘘のドラマトゥルギー ― マーティン・マクドナー『ピローマン』における信頼できない語り手 」
要旨
従来の演劇作品では、演示(representation)と語り(narration)は物語を構築する上で、基本的に相互補完的に機能してきた。しかし語りの比重が増してきた現代演劇において、この2つの形式が提示する物語内容が矛盾するケースが散見される。それらはいずれかあるいは両方が、劇的世界の事実と異なっており、したがって「信頼できないunreliable」ものとなる。では、この形式の差は信頼性に影響するだろうか。山下はこの問いに対し、「原則として演示の方が信頼できる」と解答し、それに対し關は、演示での提示部分が信頼できない場合もあるのではないかと反論・仮説した。本発表ではマーティン・マクドナー(Martin McDonagh, 1970-)の『ピローマン』(The Pillowman, 1995年執筆、1999年出版、2003年初演)を取り上げ、この仮説の検証を行う。
本作品では、自白や誓いという行為遂行的言表行為が重要な要素として描かれ、また主人公カトゥリアンの職業が作家であることに鑑みても、一貫して「物語るstory-telling」行為を重視した作品であることは明白である。加えて、登場人物たちは次々に嘘を吐くために言表内容は二転三転し、観客/読者はその言表行為への信頼性を失う。そのような状況で、カトゥリアンが書いた作品のいくつかは「語る」と同時に俳優によって「演示」までされるが、これも同様に内容が事実と異なっていることが示される。本発表では、『ピローマン』における以上のような言表行為およびその主体の「信頼できなさ」を物語論の視点から分析し、演劇を対象とした物語論的研究の可能性、および演劇的言表行為を対象とした物語論研究の必要性を指摘する。
発表②
山下純照
「岩井秀人『て』における多様な焦点化による<叙事詩化> ― 変動する時間軸からのコメント、別目線での反復、<ロング・ショット>」
要旨
岩井秀人は代表作のいくつかで(『夫婦』『おとこたち』)父親による暴力の問題を書き込んでいる。本作もその1つである。おそらく暴力ゆえにそれぞれのひずみをもって成長せざるを得なかった山田家の4人のきょうだい(男2人、女2人)とその両親、それに1人の友人、さらに長女の配偶者もいて、「全員が集まる」試みがなされるものの、すべてが噛み合わず、何かがただ激しく空回りする中で、祖母の菊枝が臨終を迎える。
劇の現在は、祖母の葬儀が終わった時点だ。振り返って、葬儀の時間、菊枝の臨終直前におこなわれた家族集合の時間、出棺と火葬場の時間という、おおまかにいって3つの時間が再現される。しかし、『て』は回想劇ではない(特定の人物の回想として提示されるのではない)。作品世界を指し配する主体を、ここでは(作品に内在するという形容を省略して単に)作者と言っておくと、作者によって時間軸を自在に往来させる広義の叙事詩的演劇になっている。ただこれには容易に反論が予想される。なぜなら、観客への語り(narration)は出てこないし、字幕などの説明もないからだ。
本発表では、『て』においては多様な焦点化の手法によって、ある種の<叙事詩化>が目指されているという仮説を立てこれを検証したい。同じ人々が同じ時間帯に同じ場所で経験した出来事を、その多様な側面を浮き彫りにするために、異なる人物の<目線>から2度反復して演示するという方法が明示されている(場割自体にそう書いてある)が、それだけではない。多様な焦点化による<叙事詩化>は、おそらく痛みを潜伏させた家族史を演示する方法論だった。結末では家族一同みな手を貸して、祖母の棺桶を焼き場のスペースに収めようとするが、何度やっても壁にぶつかりうまくいかない。それでも手を離そうとはしない彼ら全員が<ロングショット>で捉えられていて、泣き笑いを誘うのだ。
關智子(せき・ともこ)
早稲田大学他非常勤講師、演劇博物館招聘研究員、批評、翻訳。専門は現代英国演劇、戯曲理論。主な論文として「「逆転と両義性のドラマトゥルギー-『白いウサギ、赤いウサギ』における登場人物と作者の地位をめぐって-」、「残酷な自嘲性と観客への攻撃-サラ・ケインの未出版モノローグ作品に対する一考察」他。『西洋演劇アンソロジー』では「マーティン・エスリン」の項目を担当。
山下純照(やました・よしてる)
成城大学文芸学部・大学院文学研究科教授。演劇学、ドイツ近現代演劇、および日本現代演劇の美学。本会事務局長および例会担当運営委員。日本演劇学会理事。フィッシャー=リヒテ『演劇学へのいざない』共訳、2013年。『西洋演劇論アンソロジー』編集代表、2019年。最近の論文:「壊れていくクラインの壺――岩井秀人『おとこたち』にみる「舞台の語り」――」(『美学美術史論集』22, 2020)
岡本淳子(おかもと・じゅんこ)
大阪大学大学院言語文化研究科言語社会専攻 准教授。博士(言語文化学)。専門は現代スペイン演劇。著書に『現代スペインの劇作家アントニオ・ブエロ・バリェホ―独裁政権下の劇作と抵抗』など。
翻訳作品に、パロマ・ペドレロ「キス、キス、キス」 (『現代スペイン演劇選集II』所収)、
ライラ・リポイ「聖女ペルペトゥア」(『現代スペイン演劇選集III』所収)、ブランカ・ドメネク「さすらう人々」(『21世紀のスペイン演劇1』所収)、ミゲル・デ・セルバンテス「幸福なならず者」(『セルバンテス全集第5巻 戯曲集』所収)など。

*オンライン開催(Zoom会議)
*5月21日(金)に、電子メールの会員一括送信でZoom会議リンクを送付いたします。
*会員以外で参加を希望する方は5月20日(木)までに氏名とリンク送り先を添えて電子メールで事務局までお申し込みください。初めての方は簡単な自己紹介をお願いします(申込先アドレス:y3yamash[アト]seijo.ac.jp)
1.研究発表 14:00~15:20
堀真理子(青山学院大学) 「ベケットとエコロジー ― 『ゴドーを待ちながら』を中心に」
<発表要旨>今世紀に入ってから「人新世」という概念のもと、人間至上主義を見直し、技術発展が生活を豊かにするという発想から別の思考への転換が求められてきています。しかし、ベケットをはじめ「不条理」の作家たちはすでに今日的なエコロジカルな思考のもとに作品を書いています。そう考えると、抽象性や無意味さばかりが強調されてきたベケットの作品がよりリアルに迫ってきます。本発表では、『ゴドーを待ちながら』の出版稿のみならず、草稿や演出ノートにも触れながら、ベケットのエコロジカルな思考に基づく演劇的表現方法を探っていきたいと思います。
(休憩 15:20~15:30)
2.論文合評 15:30~16:10松浦愛子(釧路公立大学)
“Textualization of the English Theatre and Its Consequences in the 19th Century: Theatre Publisher Samuel French in the Mid-Victorian Period”(CTR:『西洋比較演劇研究』2021年, 20巻1号, pp. 1-27)
ディスカッサント:安田比呂志(開智国際大学) <論文掲載リンク(松浦氏)> https://www.jstage.jst.go.jp/article/ctr/20/1/20_1/_article/-char/ja
■発表者プロフィール
堀真理子(ほり まりこ)
青山学院大学経済学部教授。単著に『ベケット巡礼』『改訂を重ねる『ゴドーを待ちながら』』『反逆者たちのアメリカ文化史』、共編著にSamuel Beckett and Pain、Samuel Beckett and trauma、Influencing Beckett / Beckett Influencing、共著に『文学都市ダブリン』『戦争・詩的想像力・倫理』『サミュエル・ベケットと批評の遠近法』、Beckett at 100、The Edinburgh Companion to Samuel Beckett and Arts、Samuel Beckett as World Literature等がある。
松浦愛子(まつうら あいこ)Aiko MATSUURA
釧路公立大学准教授。博士(英国マンチェスター大学演劇学科)。専門は、19世紀イギリス演劇史。現在の研究テーマは、著作権法と作者の社会的地位の変容と劇場建築、および、市民社会の形成過程。「ヴィクトリア朝劇場空間統制のポリティクス——「群衆」から「市民」へ」(『ヴィクトリア朝文化研究』第11号、日本ヴィクトリア朝文化研究学会:3-25.2013年)は、第1回日本ヴィクトリア朝文化研究学会優秀論文賞佳作賞を受賞。
第219回例会:2021年7月後半の土曜日午後。内容については4月上旬をめどに第一報を発信。オンライン開催

*オンライン開催(Zoom会議) リンク発送は4月9日を予定
■総会 15:00~15:30
*2020年度活動および会計報告、運営委員改選、2021年度計画および予算などが議題になります。 ■第217回例会 15:30~17:00(研究発表・質疑応答)
横山義志 なぜ歌と踊りは「自然」ではなくなったのか? ~ 一八世紀フランス演技論とキケロ『弁論家について』 ~
西洋近代演技論において「自然」という概念は歌や踊りといった音楽性の排除を促す機能を持っていた。「自然な」演技とは、歌唱的・舞踊的要素を排除した演技のことだった。だが歌や踊りもヒトという生き物にとって「自然な」営みには違いないだろう。ではなぜこの概念がそのような機能を持つに至ったのか。 それはこの概念がキケロの「弁論の自然本性(natura orationis)」という概念に由来するためである、というのが本発表で提示したい一つの回答である。この言葉はキケロ『弁論家について』の演技に関連する記述のなかで見られ、一八世紀フランス演技論はこの記述に大きな影響を受けている。非音楽的・散文的演技論の枠組みを提示したフランス語のテクスト(ディドロ『『私生児』についての対話』(一七五七)、シャルル・デュクロ「古代人のデクラマシヨン」(『百科全書』第四巻、一七五四)、ピエール・レモン・ド・サン=タルビーヌ『俳優』(一七四七)、ルイジ・リッコボーニ『デクラマシヨンについての考察』(一七三八)等)とキケロのテクストを比較しながら、「役者(acteur)」が「自然(nature)」から「霊感(inspiration)」を受けて演技するとなぜ音楽性が排除されていくのかを考察したい。
■発表者プロフィール
横山義志(よこやま・よしじ)
SPAC-静岡県舞台芸術センター文芸部、東京芸術祭国際事業ディレクター、学習院大学非常勤講師。専門は西洋演技論史。発表の関連論文として、博士論文 La grâce et l’art du comédien. Conditions théoriques de l’exclusion de la danse et du chant dans le théâtre des Modernes (Université Paris X-Nanterre),「朗誦の記譜可能性について ドラマにおける音楽の排除」、「キケロはいかにして疑うのをやめ、俳優の真情を信じるようになったか 感情主義演技論の理論的起源」、「アリストテレスの演技論 非音楽劇の理論的起源」等。『西洋演劇論アンソロジー』では「クインティリアヌス」、「エミール・ゾラ」、「アンドレ・アントワーヌ」の項目を担当。 * 終了後、そのままオンライン懇親会を予定
** 今後の例会予定
第218回例会:2021年5月22日(土)午後。内容は会員の著書合評会(堀真理子氏)・CTR掲載論文合評会(松浦愛子氏)。オンライン開催
第219回例会:2021年7月後半の土曜日午後。内容については4月上旬をめどに第一報を発信。オンライン開催

■日時:2020年12月12日(土) 14:00- 16:00 (20分程度の延長の可能性あり)
*ミーティングルームのリンクおよび配付資料については、当日一週間前をめどにご案内します。
■進行
14:00 冒頭あいさつ・趣旨説明・以降の流れの説明
14:10~15:20 発表1-3(各20~30分)
(ブレイク10分)
15:30~15:45 パネリスト間での意見交換
15:45~最長で16:20 フロアを交えた意見交換
■シンポジウム趣旨
2020年の春以来、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって、世界各国の劇場・劇団が活動の制限・休止を余儀なくされている。これを背景に発展してきたのが、いわゆるオンライン演劇だ。その形態は、過去の公演録画を工夫して配信するものだったり、あるいはまったく新規に、オンラインでの発表を前提に制作されたものだったりする。
そのような事例の数々について、これまでにさまざまな場で議論が行われてきた(表象文化論学会、国際演劇評論家協会(AICT)日本センターほか)。だが「日本国外の劇場・劇団による実践」に対する目配りという点では、なお大いに議論の余地がある。
本シンポジウムでは、英独仏の各言語圏の舞台芸術を専門とする3名の会員が、それぞれに追ってきたオンライン演劇の実践例を紹介し、意見交換を行う。各国での実践に関する考察を手がかりに、オンライン演劇の現状と今後について、議論を深めたい。
■発表1:辻佐保子 「プラットフォームとしてのオンライン、媒体としてのオンライン:イギリスとアメリカの事例から」
本発表は、イギリスとアメリカにおけるオンライン演劇の実践例を扱う。イギリスでは3月から現在に至るまで、ロックダウンから段階的再開、再ロックダウンと演劇の制作・上演をめぐる状況は目まぐるしく変化している。他方のアメリカ、特に中心地ニューヨークでは、感染爆発を受けて2020年11月現在では2021年5月末まで(METは9月まで)劇場閉鎖が決定している。どちらの国でも、劇場や劇団、アーティストは厳しい状況への対応が迫られ続けている。こういった非常事態においてこそ、各国・各地域の制作・上演環境やシステム、「ライブ」に対する認識の相違が鮮やかに浮かびるのではないだろうか。本発表では、イギリスでの事例としてリトル・エンジェル・シアターの『どこいったん I Want My Hat Back』と、劇団ワイズ・チルドレンやチチェスター・フェスティヴァル・シアターが試みた配信システムについて、アメリカの事例としてリチャード・ネルソン作の『アップル・ファミリー The Apple Family』Zoom三部作(What Do We Need to Talk About?, And So We Come Forth, Incidental Moments of the Day)について紹介する。
■発表2:田中里奈 「オンライン上での劇場的空間の創造:ドイツ語圏における試み」
ドイツ・スイス・オーストリアでは、3月半ばにレパートリー形式での無料配信が劇場等で始まり、同月末のシャウシュピールハウス・チューリヒによる新作『コロナ受難劇 Coronapassionspiel』の制作発表宣言を皮切りに、オンライン初演の作品が次々と発表された。同時に、ブルク劇場によるTwitter演劇『演目変更 Vorstellungsänderung』や、劇評誌「ナハトクリティーク Nachtkritik」上でのチャットを用いた配信並走型トークイベントのように、観客を交えた劇場的空間の形成が試みられた。徐々に有料配信のシステムが整備されると、劇場公演が再開されたのちも、劇場内外にいる俳優を画面を通じて接続させたゴブ・スクワッドの『ショウ・ミー・ア・グッド・タイム Show Me A Good Time』(モウソントゥルム・フランクフルト)のように、上演空間を劇場に留めない作品が第二次ロックダウンまでたびたび催されてきた。
本発表では、発表者が観客(または参加者)として観察した作品を中心に取り上げ、また直近でハインリヒ・ベル財団が刊行した『ネットシアター Netztheater』の議論を紹介しつつ、オンラインをプラットフォームに据えた上演とその体験について、例会参加者とともに考察を深めたい。
■発表3:藤井慎太郎 「公共の広場としての劇場が閉ざされたとき フランス語圏演劇に見る応答のかたち」
本発表ではフランス語圏における実践例を扱う。フランスでは、Zoomなどを活用した作品の事例が、当初はダヴィッド・ボベ演出『妖精たちFées』くらいで数が少なかったのだが、秋になってからアルチュール・ノジシエル演出『スプランディッズSplendid's』、マリオン・シエフェール演出『ジャンヌ・ダークJeanne Dark』、ヴァレリー・ムレジェン『3人の緑の男Trois hommes vertes (sic)』など、ようやく数が増えてきた。この予稿を執筆している段階では未実施のものが多く、具体的にどの作品を取り上げるかは未定である。オンラインの手法を活用したものではないが、コリーヌ国立劇場やパリ市立劇場による電話を活用した演劇の実践についても検討を加えたい。こうした事例を紹介しながら、「公共の広場/場所」としての劇場が閉鎖された状況下で、演劇に何が可能なのかという背景にもふれたいと考えている。
■発表者プロフィール
辻佐保子(つじ・さほこ)
早稲田大学文学学術院文化構想学部講師(任期付)。専門はアメリカのステージ・ミュージカルやミュージカル映画、ラジオ・ミュージカルの作劇法。
「ミュージカル『特急二十世紀号に乗って』における楽曲の機能」(『早稲田大学大学院文学研究科紀要』59、第三輯、早稲田大学文学研究科、2014年)、「ミュージカル『ビリオン・ダラー・ベイビー』における号外の機能とその劇的意義について」(『表象・メディア研究』7、早稲田表象・メディア論学会、2017年)、“`Salute to Radio': The Self-reflexive Artistry of Betty Comden and Adolph Green in Fun with the Revuers" In. Studies in Musical Theatre, 2020年。
田中里奈(たなか・りな)
明治大学国際日本学部助教。博士(国際日本学)。専門は20世紀以降のドイツ語圏と日本のミュージカル、両文化圏間の興行文化論。2017年度オーストリア国立音楽大学音楽社会学研究所招聘研究員。2019年、International Federation for Theatre Research, Helsinki Prize受賞。代表的な著作に、「文化政策遂行機関としてのヴィーン劇場協会──オーストリア・ヴィーンにおける文化営為の政治性」(『明治大学大学院国際日本学研究論集』8、2018年)、「変容し続けるジュークボックス・ミュージカル ―ヴィーンにおけるミュージカルとポップ・ミュージックの関係を例に」(『演劇と音楽性』森話社、2020年)がある。
藤井慎太郎(ふじい・しんたろう)
早稲田大学文学学術院教授(演劇学、文化政策学)。フランス、ベルギー、カナダなどのフランス語圏諸国・地域、および日本を中心として舞台芸術の美学と制度を研究している。共編著書にThe Dumb Type Reader (Museum Tusculanum Press, 2017)、『演劇学のキーワーズ』(ぺりかん社・05)、監修書に『ポストドラマ時代の創造力 新しい演劇のための12のレッスン』(白水社・13)、共同責任編集にAlternatives théâtrales, “numéro hors-série : Scène contemporaine japonaise” (18), Théâtre/Public, “no.198:Scènes françaises, scènes japonaises / allers-retours”(09)、共訳書にクリスティアン・ビエ、クリストフ・トリオー著『演劇学の教科書』(国書刊行会・09)、翻訳戯曲にワジディ・ムワワド作『炎 アンサンディ』『岸 リトラル』、ミシェル・ヴィナヴェール作『職さがし』など。
〔コーディネーター〕
萩原健(はぎわら・けん)
明治大学国際日本学部教授。博士(文学)。専門は現代ドイツ語圏の舞台芸術、および関連する日本の舞台芸術。
『演出家ピスカートアの仕事──ドキュメンタリー演劇の源流』(森話社、2017年)、「佐野碩とピスカートア」(菅孝行編『佐野碩──人と仕事』藤原書店、2015年)、「宝塚を二度迎えたベルリーンの劇場──そのレヴューの歩み」(中野正昭編『ステージ・ショウの時代』森話社、2015年)。

Zoomを利用したオンライン研究会(詳細は会員メールリストでご案内します)
■内容:
『演劇と音楽』合評会
2020年6月に森話社から刊行された『演劇と音楽』(森佳子・奥香織・新沼智之・萩原健(編))の各論文の内容の不明瞭な部分を明瞭にし、また新しい視点や不足した部分をあぶり出し今後の一層深い研究へと発展させることを目的として合評会を行いたいと思います。
以下の順番で一人30分程度の持ち時間で進めていきます。
①村島彩加論文「文士俳優・土肥春曙の仕事──台詞術に着目して」
②辻佐保子論文 「コムデン&グリーンはいかにして「統合」と向き合ったか──『ベルがなっている』と『フェイド・アウト-フェイド・イン』の劇作術に見る美学」
③田中里奈論文「変容し続けるジュークボックス・ミュージカル──ヴィーンにおけるミュージカルとポップ・ミュージックの関係を例に」
■事前質問提出のお願い今回は質疑応答において多少の交通整理をしたいので、「論文全体に関わる内容の質問」を事前に集めさせていただきたく考えております。例会のリンクとともに会員メールリストで質問フォームを送付いたします。
※この他、当日質問も受け付けます。
■登壇者プロフィール
・村島彩加(むらしま あやか)
明治大学兼任講師、青山学院大学非常勤講師。専門は日本近代演劇。
「表情をめぐる冒険──明治時代末期、新旧俳優の挑戦と挫折」(神山彰編『交差する歌舞伎と新劇』森話社、2016年)、「緞帳の調製と百貨店──進上幕の近代」(神山彰編『興行とパトロン』森話社、2018年)。
・辻佐保子(つじ さほこ)
早稲田大学文学学術院文化構想学部講師(任期付)。専門はアメリカのステージ・ミュージカルやミュージカル映画、ラジオ・ミュージカルの作劇法。
「ミュージカル『特急二十世紀号に乗って』における楽曲の機能」(『早稲田大学大学院文学研究科紀要』59、第三輯、早稲田大学文学研究科、2014年)、「ミュージカル『ビリオン・ダラー・ベイビー』における号外の機能とその劇的意義について」(『表象・メディア研究』7、早稲田表象・メディア論学会、2017年)、“`Salute to Radio': The Self-reflexive Artistry of Betty Comden and Adolph Green in Fun with the Revuers" In. Studies in Musical Theatre. (2020年度中に掲載予定)。
・田中里奈(たなか りな)
明治大学国際日本学部助教、神奈川大学ほか兼任講師。博士(国際日本学)。専門は20世紀以降のドイツ語圏と日本のミュージカル、両文化圏間の興行文化論。
「文化政策遂行機関としてのヴィーン劇場協会──オーストリア・ヴィーンにおける文化営為の政治性」(『明治大学大学院国際日本学研究論集』8、2018年)、“Local Bodies in Japanese Popular Musical Theater Today: Re-localization in the Transformation of the Musical Marie Antoinette," (Awarded for Helsinki Prize 2019 of the International Federation of Theatre Research, 2019)、“A Jukebox Musical, or an ≫Austro-Musical≪? ―Cultural Memory in Localized Pop Music(al) I am from Austria (2017)―"(『西洋比較演劇研究』18、2019年)。
〔コーディネーター〕
新沼智之(にいぬま ともゆき)
玉川大学芸術学部パフォーミング・アーツ学科准教授。専門はドイツを中心とする西洋の近代演劇史、演技論。
フィッシャー=リヒテ『演劇学へのいざない──研究の基礎』(共訳、国書刊行会、2013年)、シラー『オルレアンの乙女』(翻訳・解説『ベスト・プレイズII』所収、論創社、2019年)、「演技の近代化プロセスにおけるゲーテの演劇観」(『西洋比較演劇研究』18、2019年)。

以下の要領でおこないます。中止となった6月の全国大会で予定していたシンポジウム案をもとに行います。ぜひともご予定をお開けいただけますよう。
■日時: 2020年8月29日(土) 14:00- 16:00(15分程度延長の可能性あり)
*オンライン研究会 会議リンクおよび配付資料の詳細については当日一週間前をめどにご案内します。
■内容: 『演劇と音楽』シンポジウム:研究手法の視点から
■進行
14:00 冒頭あいさつ・主旨説明・以降の流れの説明
14:10~15:25 報告1-5(各15分)
(ブレイク5分)
15:30~15:45 パネリスト間での意見交換
15:45~最長で15:15 フロアを交えた意見交換
■シンポジウム趣旨
かつて演劇学において、「聴覚的なもの」を扱う研究は、単に「言語を媒介するもの」という見解に基づくものが主流であった。しかし現在では、近年発展してきたパフォーマンス研究の影響から、音楽・音への関心が高まり、研究者の興味の対象は広がっている。例えば、発話される言葉に限らない声、音楽、ノイズなどの要素に注目する研究、または発話される言語そのものに音楽的な特徴や機能を見出す研究、あるいはオペラやミュージカルなど音楽が主導的な役割を果たすジャンルを、演劇学のなかに積極的に位置付ようとする研究も増えてきている。このような研究においては、伝統的な演劇学や音楽学だけでなく、より発展的な方法、すなわち学際的な方法論も必要となるだろう。本シンポジウムでは、西洋比較演劇研究会30周年を記念して刊行された『演劇と音楽』の執筆者の中から5名が、それぞれの視点でこの問題を検討し、議論を深めることで、今後の研究における可能性を探っていく。 各パネリストの発表内容は、次の通りである。
■報告1: 大崎さやの 「マルッテリアーノ詩形と演劇の音楽性」
18世紀、マルテッロが復活させた14音節詩行のマルテッリアーノは、脚韻を踏む詩形で、ヴェネツィアの人々の愛する音楽性に満ちていた。これはゴルドーニが劇作家として成功を収めるために不可欠な詩形であった。以上のように本発表では、演劇の「音楽性」に関する研究例を示す。
■報告2: 藤原麻優子 「ミュージカルにおける音楽性について 「ウエスト・サイド・ストーリー」を例に」
本発表では、近年広がりを見せつつあるミュージカル研究における、作品分析の一例を提示する。具体的には、1957年に初演されたミュージカル『ウエスト・サイド・ストーリー』を手掛かりに、ミュージカルでの言葉・音楽・ダンスの関係について考察する。
■報告3: 森佳子 「オペラ《蝶々夫人》パリ版再考 演出台本から見えるもの」
プッチーニの《蝶々夫人》パリ初演版は、当時の自然主義の流行に則って改稿された。このことを証明するには、一次資料の演出台本が大きな鍵になる。台本・楽譜に加え、上演用の演出台本の考察は、オペラ研究を深めていく上で重要なアプローチの方法である。
■報告4: 萩原健 「ハイナー・ゲッペルスの〈ミュージック・シアター〉 聴衆/観客を解放する〈教材〉」
ハイナー・ゲッベルスの〈music theater〉は、音楽・テクスト・身体表現・舞台美術・照明等の構成要素をすべて等価に扱う。演劇学・音楽学・文学・美学ほかの研究者による学際的な共同研究の可能性を拓く研究対象である。
■報告5: 奥香織 「定期市の舞台から「ナショナル」な歌劇へ 国家・公権力との関係に見るオペラ=コミックの特質」
歴史を経る中で絶え間なく変容したオペラ=コミックは独自性を特定し難く、また演劇史・音楽史においても軽視されがちである。しかし、国家・公権力との関わり、国民性の表れという観点からその歴史的変容に目を向けると、18・19世紀フランス社会におけるその役割と位置づけが問い直され、社会的・政治的見地からその特質もまた浮かび上がってくる。
■発表者プロフィール
大崎さやの(おおさき・さやの)
東京大学文学部非常勤講師。博士(文学)。専門はイタリア演劇、イタリア文学。共訳書『ベスト・プレイズⅡ』(2020)。論文に「ゴルドーニとオペラ・セーリア ーメタスタージオ作品との関係を中心にー」(2019)など。
藤原麻優子(ふじわら・まゆこ)
早稲田大学演劇博物館招聘研究員。博士(文学)。専門はブロードウェイ・ミュージカル。 論文に「「これはどんなミュージカルなの?」--メタミュージカル試論」(2016)など。
森佳子(もり・よしこ)
早稲田大学ほか非常勤講師。博士(文学)。専門は音楽学(フランスのオペラ)。主な著書に『オッフェンバックと大衆芸術−パリジャンが愛した夢幻オペレッタ』 (2014)、『オペレッタの幕開け−オッフェンバックと日本近代』(2017)など。
萩原健(はぎわら・けん)
明治大学国際日本学部教授。現代ドイツ演劇および関連する日本の演劇。著書に『演出家ピスカートアの仕事』(2017)、訳書にフィッシャー=リヒテ『パフォーマンスの美学』(共訳、2009)など。
奥香織(おく・かおり) 明治大学文学部専任講師。博士(フランス文学・文明)。専門は近代フランス演劇。 共訳書『ベスト・プレイズⅡ』(2020)、「感覚の知を表象する場としてのマリヴォー劇ー「恋の不意打ち」の構造と機能をめぐって」(2016)など。

日時 2020年6月27日(土) 14:00~17:00
総会 14:00~14:25
例会 14:30~16:30
場所 オンライン
* 6月26日(金)午後早めの時間に、電子メールの会員一括送信で会議リンクを送付いたします。開始時刻にクリックしてください。総会・例会の資料および質疑応答についてもリンクとともに説明をお送りします。
* 会員以外で参加を希望する方は6月25日までに氏名とリンク送り先を添えて電子メールで事務局までお申し込みください。(申込先アドレス:y3yamash[アト]seijo.ac.jp)。
研究発表(1) 藤崎 景(明治大学大学院文学研究科演劇学専攻博士後期課程)「メロドラマ研究における「思い出」の重要性」14:30~15:30
研究発表(2) 山下 純照(成城大学)
「岩井秀人のいくつかの作品にみる「語り」の演劇性」15:30~16:30
<発表要旨>
藤﨑 景「メロドラマ研究における「思い出」の重要性」
元来メロドラマは西洋演劇における一ジャンルを指し示す言葉であった。その研究上の位置付けが大きく変わったきっかけはピーター・ブルックスの主著『メロドラマ的想像力』に求めることが出来る。同書においてブルックスは、メロドラマの表現に対して受容者の心性に及ぼす作用の面から肯定を行う。その上でバルザックやヘンリー・ジェイムズといった小説家の作品のうちにメロドラマの劇作法が通底していることを主張したのである。ブルックスがメロドラマを表現に関する問題として俎上に載せたことは重要である。以来、人文科学の諸領域において「メロドラマ」をキーワードとした研究が多面的に行われている。
メロドラマを表現の問題として捉える場合、映像メディアは極めて重要な資料である。演劇学においても、記録映像の登場によって舞台上の表現に対してこれまで以上に詳細な検討が可能になったことは事実である。だが映像メディアに記録され難いものとして観客の「思い出」がある。観劇記に代表される「思い出」には時として誤謬が含まれており、正確な記録であるとは必ずしも言い切れない。だが上述したように、メロドラマの表現を検討する上では観客の心性との関係が重要なのである。ゆえに本発表では、演劇におけるメロドラマについて「思い出」との関係から検討を行う。フランスの演劇学者であるジャン=マリ・トマソーが指摘したごとく、メロドラマは文学的な「価値」の面から貶められてきた。そのメロドラマについて研究を行う意義について考察を深めたい。
山下純照「岩井秀人のいくつかの作品に見る「語り」の演劇性」
今回の発表の背景は、2000年代それもとりわけ2010年以降、俄然顕著になってきている日本現代戯曲の一つの傾向である。それは対話形式と並んで何らかの語りを多用するというものである。語りとは、ここでは語り手が登場して(相手役に向かってではなく)語るという通常の形態を指すことにする(ただし語り手がいなくとも、何らかの舞台の約束事によって広義の<語り>がおこなわれ、それを戯曲に読みとることができる場合もまた少なくない。発表者の最近の論文ではむしろその点を取り上げたが、ここでは論点を絞る意味であえて除外する)。
世界演劇史の初期から、対話と並んで語りは演劇形式の構成部分であった。ただ17世紀から19世紀までの近代戯曲における対話中心(それもかなり独占排除的なそれ)の時代を経て、再び語りの形式が戯曲にしばしば用いられるようになったのは20世紀からである(ブレヒト流の叙事詩的演劇はその重要な例である)。ところが西洋近代戯曲の影響を受けた日本の創作近現代劇では(能や歌舞伎そして人形浄瑠璃といった古典ないし伝統演劇の分野はさしあたりおいておく)、木下順二の群読劇のような、また唐十郎『秘密の花園』冒頭の男のモノローグや、野田秀樹『赤鬼』で観客との橋渡しをするとんびという人物のような印象深い例が点在したとはいえ、戯曲の形式は対話のそれがやはりほぼすべてであった。
それが21世紀になると、岡田利規『三月の5日間』(2004年)、古川健『治天ノ君』(2013年)、岩井秀人『ある女』(2012年)、同『おとこたち』(2014年)、同『夫婦』(2016年)、上田誠『来てけつかるべき新世界』(2016年)、神里雄大『バルパライソの長い坂をくだる話』(2018年)、谷賢一『メービウスの輪』(2019年)、市原沙都子『バッコスの信女―ホルスタイの雌』(2019年)といった、演劇界で一定の評価を獲得した作品群において語りの形式が目立つ形で用いられてきている。同じ時期に書かれた戯曲の総体から見ればその数は限定的だとはいえ、注目すべき現象ではないだろうか。これらの戯曲における語りの意義を考察することは私たちが直面している課題だと思われる。
すなわちそこでの語りはいかなる劇中機能をもち、その機能は理論的にどう把握され、さらには歴史的にどう位置づけられるのか。アプローチとしては、語りの理論、すなわちナラトロジーにおける最近約30年間の、演劇についての言及を参照することが出発点となる。その意味でシーモア・チャトマン、ブライアン・リチャードソン、モニカ・フルーダニクらの仕事を踏まえ、演劇における語りについての理論的な布置を確認したうえで、本発表では岩井秀人の諸作品を対象として上記の問いに取り組みたい。さらに、リチャードソンらが指摘する、英語圏・ドイツ語圏の演劇における20世紀の語りの要素との比較を試み、岩井におけるそれを歴史的に位置づける。
<発表者プロフィール>
藤﨑景(ふじさき・けい)
明治大学大学院文学研究科演劇学専攻博士後期課程。現在は新派とメロドラマとの間に見られる劇作術の相似性に関心を持ち、研究を進めている。口頭発表「『滝の白糸』におけるメロドラマ性への一視点」(日本演劇学会2019年度全国大会)
山下純照(やました・よしてる)
成城大学文芸学部・大学院文学研究科教授。演劇学、ドイツ近現代演劇、および日本現代演劇の美学。本会事務局長および例会担当運営委員。日本演劇学会理事。『西洋演劇論アンソロジー』編集代表。最近の論文:「「もどき」の概念の現代演劇への適用可能性 : タールハイマー演出『エミーリア・ガロッティ』を中心に」(『成城美学美術史』23, 2017)、「壊れていくクラインの壺――岩井秀人『おとこたち』にみる「舞台の語り」――」(『美学美術史論集』22, 2020)

以下の要領で、今年度の総会、および5月例会に代わる研究会を持つことにいたしましたので、ご予定いただきたくお知らせいたします。
<6月オンライン例会>
【日時】 2002年6月27日(土)午後2時ー6時の範囲で適切な時間帯
【場所】 オンライン
【方法】 あらかじめ資料をクラウドで掲示の上、ZOOM会議方式で開催する方向で考えていますが、詳細については後日あらためてご案内いたします。
【内容】 2020年度総会 研究発表会

日時 2020年1月11日(土) 14:00~18:00
場所 明治大学駿河台キャンパス12号館6階 2062号室
御茶ノ水駅御茶ノ水橋口から明大に向かう通り沿いの建物です。
https://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/campus.html
前回と会場が異なります。ご注意ください.
パネルディスカッション
「再び〈自然的身体と象徴的身体〉の連接・融合・分離をめぐって」
コーディネーター・司会:小菅 隼人(慶應義塾大学)
発表①:熊谷 知子(明治大学)「演劇における「万歳三唱」――戦時下の東京を中心に」
発表②:萩原 健(明治大学)「寿がれる「ヒトラー」―― 戦後のドイツと日本における〈ナチス式敬礼〉をめぐって」
発表③:稲山 玲(明治大学)「「天皇の代替」を考察する――井上ひさし『夢の痂』から野田秀樹『南へ』」
ディスカッサント:田中 里奈(明治大学)
発表要旨・登壇者プロフィール
発表①:熊谷 知子「演劇における「万歳三唱」――戦時下の東京を中心に」
令和元(2019)年10月22日,即位礼正殿の儀において安倍首相の発声に続き,参列者たちが「万歳三唱」した姿が記憶に新しい.そもそも,石井研堂『明治事物起源』(橋南堂,1908)によれば,「万歳(ばんざい)」という言葉が現在と同じように高唱されるようになったのは明治22(1889)年2月11日,大日本帝国憲法発布の日が始めとある.
その後,日清日露の戦争を経て「万歳三唱」は国民のあいだに定着していくことになるが,昭和初期の偉人劇や軍事劇では,舞台上の群衆が「万歳」と歓呼する場面がしばしば取り入れられた.それだけでなく,昭和12(1937)年12月には南京陥落の報を受け,多くの劇場で役者と観客は共に「万歳三唱」したという.本発表では,「万歳三唱」を「自然的身体」と「象徴的身体」の緊張関係において,天皇と国民を媒介するパフォーマンスと捉え,小山内薫『森有礼』(1926)や真山青果『凱旋乃木将軍』(1937)を例にその劇的効果について考える.
熊谷知子(くまがい・ともこ)
明治大学文学部兼任講師.専門は近代日本演劇.これまで小山内薫作・演出,二代目市川左団次主演による上演とその時代背景の分析を中心に研究を進めてきた.「小山内薫と晩年の偉人劇―『森有礼』『戦艦三笠』『ムッソリニ』」(『交差する歌舞伎と新劇』神山彰編,森話社,2016年),「小山内薫『西山物語』序論―雑誌『演劇新潮』創刊から『西山物語』発表まで」(『文芸研究 明治大学文学部紀要』139号,2019年9月)ほか.
発表②:萩原 健「寿がれる「ヒトラー」―― 戦後のドイツと日本における〈ナチス式敬礼〉をめぐって」
第三帝国とも呼ばれたナチス・ドイツでは,ヒトラーが皇帝のように,〈ナチス式敬礼〉によって「ハイル・ヒトラー」と寿がれた.この「ヒトラー」は,自然的身体と,異形の権力者の象徴的身体,その双方を指すように見えないだろうか.戦後のドイツと日本の舞台での,この寿ぎの身ぶりを追究する.
〈ナチス式敬礼〉は,古代ローマでの身振りをムッソリーニが,さらにヒトラーが自国での実践に取り入れて始まり,戦後のドイツでは法によって禁じられた.以来,舞台での表現は,劇中劇やパロディ等,何らかの枠がかけられ,「ヒトラー」が持つ〈神通力〉は抑制されている.一方,戦後日本の舞台の場合,この身振りはときに無批判・無邪気に行われたり受け止められたりし,ひいてはそれに魅力を感じているとおぼしき受け手の例もある.すなわちこの身振りは現在も,場所を問わず,異形の権力者の象徴的身体を召喚し,一部の人々を服従させる力を持つ.
萩原健(はぎわら・けん)
明治大学国際日本学部教授.専門は現代ドイツ語圏の演劇・パフォーマンスおよび関連する日本の演劇・パフォーマンス.近年は日本の作り手による日本国外での上演に関心を寄せる.フィッシャー・リヒテ『パフォーマンスの美学』(共訳,論創社,2009年),『演出家ピスカートアの仕事』(森話社,2017年),The Routledge Companion to Theatre and Politics (共著,Routledge, 2019) ほか.
発表③:稲山 玲「「天皇の代替」を考察する――井上ひさし『夢の痂』から野田秀樹『南へ』」
ロラン・バルトが皇居を指して「空虚な中心」と呼んだように,天皇はその性質として「空虚」と評される存在である.戦後日本の劇作家たちも,多くの場合天皇そのものは舞台に登場させない形で(すなわち「空白」として)天皇制を表象してきた.しかし,時に舞台上にはその「空白」を埋める代替の身体が登場する.野田秀樹『南へ』(2011)はその一例である.同作では,天皇の「ヨリシロ」を名乗る人物が登場し行幸のリハーサルを行うのである.野田自身は同作を井上ひさしとつかこうへいへのオマージュを込めた作品として位置づけているが(朝日新聞2011年2月4日),実際に「天皇の代替」を務める人物が行幸のリハーサルを行うという筋は,発表者が2019年1月の西洋比較演劇研究会シンポジウムでも取り上げた井上ひさし『夢の痂』(2006)を踏襲している.本発表においては,井上,野田の両作品間における継承と断絶を検証し,それを糸口として天皇という「空白」を代替の身体が埋めることの意味を考えたい.
発表者③:稲山玲(いなやま・れい)
明治大学文学部助手.研究テーマは野田秀樹を中心とした現代日本演劇.最近の論文としては,「野田秀樹『透明人間の蒸気』における「終わらない終わり」と天皇制」(『西洋比較演劇研究』2019年3月号,日本演劇学分科会西洋比較演劇学研究会),「『野田版・国性爺合戦』に見る野田秀樹の国家イメージ」(『演劇学論集』2018年春号,日本演劇学会)他.
ディスカッサント:田中里奈(たなか・りな)
明治大学大学院国際日本学研究科博士後期課程.専門はドイツ語圏と東アジアのミュージカル,両文化圏間の演劇文化交流史.直近の論文として,“A Jukebox Musical, or an »Austro-Musical« ? – Cultural Memory in Localized Pop Music(al) I am from Austria (2017),”(『西洋比較演劇研究』第18巻第1号,2019).2019年度国際演劇学会Helsinki Prize受賞.
コーディネーター/司会:小菅隼人(こすげ・はやと)
慶應義塾大学理工学部教授.専門は舞踏,および,英国チューダ朝演劇.楠原偕子先生の指導によって舞踏研究に導かれた.また,学部・大学院より,中世英文学を専門とする指導教授のもとでチューダ朝演劇の文脈においてシェイクスピア研究を進めている.『腐敗と再生:身体医文化論』(編著,慶應義塾大学出版会,2004),The Routledge Companion to Butoh Performance (共著,Routledge, 2018),The Routledge Companion to Theatre and Politics (共著,Routledge, 2019) ほか.

研究発表をめぐる活発な討議で一年を締めくくりたいものです。ご参加ください。
日時 2019年12月7日(土) 14:00~18:00
場所 専修大学神田キャンパス 1号館地下1階 13番教室
https://www.senshu-u.ac.jp/about/campus/
内容
(1)研究発表 14:00~15:50
阪東知子「世紀転換期における劇の抒情的要素と上演可能性―ホーフマンスタールの『小世界劇場』を中心に」
(2)研究発表 16:00~18:00
新田孝行 「回想のオペラ――現代オペラ演出における時制の問題」
発表要旨・発表者プロフィール
(1)阪東知子「世紀転換期における劇の抒情的要素と上演可能性―ホーフマンスタールの『小世界劇場』を中心に」
本発表は、ウィーンの詩人ホーフマンスタール(1874-1929)が劇作家として活躍するようになった根拠を上演芸術のパラダイム転換のみならず、彼の韻文の独自性が修正されたことに見出すことを目的とする。
劇作家としてのホーフマンスタールの活躍は、1903年以降の演出家ラインハルトとの協力関係に負うところが大きいと言われている。それゆえホーフマンスタールの1890年代の抒情詩劇のいくつかが自然主義演劇の上演を主導したことで有名なブラームによって上演され、それが不成功に終わったことについては、等閑視されがちである。その不成功の原因は、概してブラームの上演手法とホーフマンスタールの抒情的要素の不調和にあったと指摘されているが、上演に影響したとされる抒情的要素にホーフマンスタールはどのように対処したのか。のちのラインハルトとの協働においては問題にならなかったのか。
その問いに答えるために、本発表では1897年に書かれた抒情詩劇『小世界劇場』の考察を中心とし、ホーフマンスタールの韻文の技巧性および独自性とドラマの危機における劇の形式、上演可能性の関係について検討する。1890年代の抒情詩劇が韻律の多様性に富んでいること(Wesche 2018)を、上演における効果的な韻文を探求する実験の跡と見るならば、そこに劇作における詩人の変化を見出すことができるだろう。
阪東知子:明治大学大学院文学研究科独文学専攻博士後期課程単位取得退学。明治大学非常勤講師。研究テーマは、ホーフマンスタールの改作劇。論文:「Die philologische inszenatorische Belebung für die Moderne – Hofmannsthals Bearbeitungstechnik in Elektra」(『明治大学大学院文学研究論集』46, 2017),「ラインハルトとホーフマンスタール―共同作業に至るまで」(『明治大学大学院文学研究論集』43, 2015)など。
(2)新田孝行 「回想のオペラ――現代オペラ演出における時制の問題」
最近のオペラでは、序曲やバレエの場面のように歌手が歌わずオーケストラが演奏する箇所で、話の伏線になる過去の出来事を黙劇として演じさせることがよくある。こうした過去の再現は、台本のト書きや前後の歌詞で言及される内容の説明を目的とする場合もあれば、人物像や粗筋自体を変更する演出上の解釈として行われる場合もある。
部分的に過去を挿入するのではなく、オペラ全体を過去として提示する演出も珍しくない。冒頭で原作には存在しない現在の状況なるものが演じられ、そこから回想としてオペラが本格的に始まるのがその代表的なパターンである。さらに、ステファン・ヘアハイム(1970~)による幾つかのオペラ演出などで見られるように、役柄の異なる二人の人物を同じ一人の人物の現在と過去と設定し、話が現在と過去の間で行ったり来たりしたり、舞台上で現在と過去が同時に存在したりするかのような効果を狙った例もある。
このように現代のオペラ演出では何らかの形で過去を表現することが重大な関心事となっている。その様々な試みを本発表は「回想のオペラ」と名づける。それは時制に関する演劇的探究という側面をもつ。そもそも舞台芸術には物語を語る手段として小説の過去形に相当するものがない。すべては「永遠の現在」において起こる。この限界に対する現代オペラ演出の側からの挑戦とも言うべき「回想のオペラ」について、具体例を紹介しつつ理論的に検討する。
新田孝行:早稲田大学オペラ/音楽劇研究所招聘研究員。主な著作に『キーワードで読む オペラ/音楽劇研究ハンドブック』(項目執筆、2017年)、「現代オペラ演出、あるいはニュー・ミュジコロジーの劇場――ローレンス・クレイマーの音楽解釈学再考」(『音楽学』、2017年)、「ポストモダンのオルフェウス――ステファン・ヘアハイムのオペラ演出について」(『美学』、2016年)。

皆様お元気ですか。お知らせが遅くなってしまいましたが、下記の要領で例会を開催いたします。
奮ってご参加ください。
日時 2019年10月26日(土) 14:00~18:00
場所 明治大学駿河台キャンパス 12号館 2061教室(6F)
御茶ノ水駅御茶ノ水橋口から明大に向かう通り沿いの建物です。
https://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/campus.html
内容
(1)研究発表 14:00~15:50
奥 景子「福田恆存の『現代の英雄』に見られる喜劇観」
(2)30周年記念事業成果報告および検討① 16:00-18:00
山下純照「『西洋演劇論アンソロジー』の使い方など」
発表要旨・発表者プロフィール
奥 景子「福田恆存の『現代の英雄』に見られる喜劇観」
今回の発表では、福田恆存の『現代の英雄』を取り上げる。この作品は、作者本人も認めている通り、シェイクスピアの『マクベス』の翻案である。福田は、1958年に自身の翻訳で『マクベス』を上演する前、1957年にその翻案である『明智光秀』という戯曲を執筆・上演しており、1952年の『現代の英雄』はそれらに先駆けるものである。
『現代の英雄』は、悲劇『マクベス』をもとに、ある実在の人物を加え、福田の想像力で編み直した喜劇である。批評家からキャリアをスタートさせ、劇作家としても『キティ颱風』や『龍を撫でた男』で既に一定の評価を得ていた福田は、独自の喜劇観を持っていた。この後、欧米視察やシェイクスピア翻訳を経て、彼の劇作は史劇へと向かう。
発表者は、2015年日本演劇学会秋の研究集会における口頭発表(「福田恆存の『明智光秀』に見られる『マクベス』観」)及び2019年の論文発表(「福田恆存の『明智光秀』に見られる悲劇観」)において、福田が、現代では失われたと彼が考える悲劇を、史劇を通じて回復させようと試みていたことを論じてきた。
本発表においては、当時の彼の喜劇観とはどのようなものであり、それがどのように作品に反映されていたのか、そしてそのことがどのように後の史劇『明智光秀』へと繋がるターニング・ポイントとなりえていたのかを考察したい。
奥景子(おく・けいこ)
明治大学大学院文学研究科演劇学専攻博士後期課程。現在は日本におけるシェイクスピア受容、特に戦後、福田恆存の翻案と翻訳を中心に研究を進めている。掲載論文「福田恆存の『明智光秀』に見られる悲劇観」(演劇学論集 日本演劇学会紀要68(2019))、口頭発表「福田恆存の『有間皇子』に見られる芸術観」(日本演劇学会 秋の研究集会(2016))他。
山下純照「『西洋演劇論アンソロジー』の使い方など」
予定より3か月あまり遅れて9月10日に刊行された本書には、約40名の本会会員が編集・執筆に携わり、2年半の時間が費やされてきた。この時点で一つのまとめを試み、本書をもとにさらに前に進む契機としたい。
本書の性格については6月の演劇学会大会のシンポジウムで報告し(その時点では未刊)、会場からいろいろな問いが投げかけられもした。この合評会の前半では、そのうち特に演劇史(の複数性)との関係をさらに議論したい。演劇論を軸として想像する西洋演劇史は必然的にそれじたい理論指向なものとなるだろう。が、そのことは言うまでもなく、それが唯一の歴史像であることを意味しない。本書が喚起する歴史像の空白を論じられれば幸いである。
もう一つの柱として、本書を大学その他の、演劇学の学びの場で、どのように使うかについて試案を示し、議論してみたい。読み方が指定されるような書物ではないだけに、例えば受講者に通読を指示するような使い方は考えにくい。授業プランとの関係で予習箇所を指定し、授業では難解箇所の解説や、その項目の意義の説明を加えることが考えられるが、具体的にどのようなモデルがあり得るのか。今回は宮城聰演出『アンティゴネー』2019年NY公演のレビューを踏まえ、本書のいくつかの項目がそれらと有意な緊張関係を結んでいることを伝えるモデルを示す。
山下純照(やました・よしてる)
成城大学文芸学部・大学院文学研究科教授。演劇学、ドイツ近現代演劇、および日本現代演劇の美学。本会事務局長および例会担当運営委員。日本演劇学会理事。『西洋演劇論アンソロジー』編集代表。比較的最近の論文:YAMASHITA, Yoshiteru, “Das Fastnachtspiel von „Rumpold und Mareth“ als verdecktes Modell für das Lustspiel Der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist“(『美学美術史論集』20, 2013)、「「もどき」の概念の現代演劇への適用可能性 : タールハイマー演出『エミーリア・ガロッティ』を中心に」(『成城美学美術史』23, 2017)。

皆様お元気ですか。下記の要領で例会を開催いたします。かなりの暑さが予想されますが、お越しいただければ幸いです。
■日時 2018年7月20日(土) 14:00~18:00
■場所 成城大学【3号館1F 311教室】
【*3号館は正門を入り、中庭左側の白い建物です。】
■内容
□14:00~15:30 論文合評会 分科会紀要『西洋比較演劇研究』18巻
田中里奈・新沼智之・伊藤真紀・萩原健(司会)
出典リンク https://www.jstage.jst.go.jp/browse/ctr/list/-char/ja
□15:45~18:00 シンポジウム「研究と上演のかかわりを考える」
内田健介・田中圭介・新沼智之
■要旨 論文合評会
本合評会は、分科会紀要『西洋比較演劇研究』掲載論文の内容をより深く咀嚼し、問題意識を共有するために開催いたします。最新18号に収められた4本の論文のうち、3本の著者を招き、各人の持ち時間を約30分として、それぞれの時間枠で、著者による論文概要紹介のあと、フロアとの意見交換をいたします。
論文が掲載された紀要はすでに下記リンクからアクセス可能です。できるかぎり論文をご一読の上、ご参加いただけると幸いです。扱う論文は次の通りです。
□田中里奈「A Jukebox Musical, or an »Austro-Musical«? – Cultural Memory in Localized Pop Music(al) I am from Austria (2017)」
□新沼智之「演技の近代化プロセスにおけるゲーテの演劇観」
□伊藤真紀「キャサリン・デュポン(Chatherine du Pont)のボストン公演―「能ダンス」の「声」」
■プロフィール
□田中里奈(たなか りな)
明治大学大学院国際日本学研究科博士後期課程。専門はドイツ語圏と日本のミュージカル,両文化圏間の演劇文化交流史。論文:「文化政策遂行機関としてのヴィーン劇場協会―オーストリア・ヴィーンにおける文化営為の政治性」(『明治大学大学院国際日本学研究論集』第8号,2018),「Local Bodies in Japanese Popular Musical Theater Today: Re-localization in the Transformation of the Musical Marie Antoinette」(国際演劇学会(IFTR)主催Helsinki Prize[非英語圏出身若手研究者奨励賞]受賞)。
□新沼智之(にいぬま ともゆき)
玉川大学芸術学部パフォーミング・アーツ学科准教授。専門分野は演劇学,西洋演劇史。主にドイツを中心とする西洋演劇の近代化のプロセスを研究。論文に「A.W.イフラントが目指した舞台づくり――視覚的要素の問題を中心に」『演劇の課題2』(三恵社、2015年),「18 世紀後半のドイツにおけるアンサンブル演技理念の萌芽と劇団規則」『西洋比較演劇研究』(Vol.12 No.2、2013年)ほか。
□伊藤真紀(いとう まき)
明治大学文学部教授。研究テーマは近現代の日本演劇。特に能楽などの伝統的な演劇における近代化の問題を研究している。女性と能楽との関わりに着目した論文に,「能舞台に上がった女性たち―大正十一年の『淡路婦人能』をめぐって」(『演劇学論集』56号 2013年)。「デュポン嬢の能―女性よる舞踊と能」(『文芸研究』95号 2005年)がある。また,日本の近代演劇についての論考に「小山内薫と『霊魂の彫刻』―『象徴的演劇』としての能―」(『文芸研究』98号 2006年)がある。
□萩原 健(はぎわら けん)
明治⼤学国際⽇本学部教授。専⾨:20世紀以降のドイツ語圏の演劇、および関連する⽇本の演劇。 研究と並⾏して、戯曲翻訳、字幕翻訳/制作/操作、稽古場通訳も⼿掛ける(⽇本語/ドイツ語)。訳書にフィッシャー=リヒテ『パフォーマンスの美学』(共訳)ほか、著書に『演出家ピスカートアの仕事 ドキュメンタリー演劇の源流』。近年は⽇本の演劇⼈のドイツ語圏での活動に関⼼を寄せる。
■要旨 シンポジウム「研究と上演のかかわりを考える」
芝居の作り手とその外部の者たちとの協働は演劇が芸術として発展するのに大きく寄与してきた。演劇の近代化プロセスにおいて、それまで芝居の作り手の中心にいた戯曲の提供者が立ち位置をいくぶん外部へと移し、文学者となって上演に影響力をふるうようになっていったこともそうした協働のかたちの一つであろう。さらに、20世紀に入ると芝居の作り手は様々なかたちで積極的に外部の者の力を借りるようになっていった。ブレヒトに協力者がいたことは有名で、ブレヒト研究ではしばしばそのことについてよく語られる。そして『三文オペラ』の台本のほとんどが協力者の一人であったエリザベート・ハウプトマンの手になるものだという暴露話もある。しかし、結局のところ実際にその協働の具体、すなわち彼女の功績がどれほどだったのかということについては推論の域を出ないようだ。20世紀の後半になると、芝居作りにおける知的な側面を支えるドラマトゥルク(ドラマターグ)という役職が、公式の協力者として格上げされるかたちで、ドイツを筆頭に世界的に、そしてようやく日本でも重要な役職として認識されるようになってきた。協働の具体は、それによって少しは外に向けられて語られるようになってきたと言えるのかもしれないが、それでもまだまだ歴史的な出来事として語られるには時間がかかりそうだ。それはなぜなのか。さらに、外部の者、特に研究者が芝居の作り手たちと協働し、上演に作用を及ぼしていくことの可能性あるいは問題点はどのように考えられるのか。そうしたことは我々研究者にとって多かれ少なかれ常に頭の中にある問題であろう。
本シンポジウムでは、2018年10月 の日本大学芸術学部における『初稿版 桜の園』公演(日本初演)および2019年5月の玉川大学芸術学部における『かもめ』公演で協働した演出家の田中圭介とチェーホフ研究者の内田健介の二人の経験を軸にしながら、研究と上演のかかわりについて考えてみたい。
■発表1 新沼智之「上演・演技・演出の構造について」
芝居作りに関することが話題になると―その性質からして避けることは非常に難しいのだが―どうしても一座の事情などに話が逸れていき、学問的な議論が難しくなる傾向がある。ここでは、そうした議論の混乱をできる限り生じさせない方策として、発表2・3の前に、「上演」、「演技」、「演出」などについてその構造がいかなるものかを整理してみたいと思う。それは、さまざまな協力・協働がある中で例えば「劇評」も協力・協働と言える―ドラマトゥルクの嚆矢とされるレッシングがその重要な仕事の一つとして行っていた定期的な劇評(それは『ハンブルク演劇論』に集約される)もこれに含まれよう―といった意見が出たときに、「劇評」は将来の上演に対して作用を及ぼすものであり、その「上演」自体には作用を及ぼさないので除外するといった線引きを可能にもし、ここで議論するべき事がらにおける混乱を少なからず避けることも可能にするだろう。
■発表2 内田健介「チェーホフ研究と実践の場への研究成果の提供」
発表者はこれまでロシアの劇作家アントン・チェーホフの研究を続けるなか、様々な形で演劇の実践の現場に関わってきた。演出家原田一樹が主宰する劇団キンダースペース公演「チェーホフ的チェーホフ」(2008)、「とある出来事」(2010)ではチェーホフの小説作品を元にした脚本を、また同劇団の「プラトーノフ」(2014)では時代考証を担当して以降、このほか劇作家の阿藤智恵、前嶋のの、嶽本あゆ美らのチェーホフ作品の上演にも協力してきた。そして昨年度、今回の発表者のひとりである日本大学芸術学部演劇学科公演に際して演出家田中圭介に『初校版・桜の園』を提供、今年度は玉川大学芸術学部パフォーミング・アーツ学科公演で『かもめ』の翻訳を提供した。今回は特に『初校版・桜の園』の上演までの過程において、どのような役割を果たしたのかを顧みながら、研究者が現場に関わることの意義について考えてみたい。
■発表3 田中圭介「既存戯曲の上演における演出家と研究者のプロセス~チェーホフ劇の上演を例に~」
演出家が既存の戯曲を上演する際に、何を手掛かりにすればよいのか。特にチェーホフ劇のように多くの上演がされてきたものについては、ことさらに現代性や独自の解釈を開陳するような上演も散見される。翻訳者でありチェーホフ研究者の内田健介との共同作業―日本初演となった『初校版・桜の園』翻訳・協力や『かもめ』新訳―の中で見えてきた、演出家の上演までのプロセスを例に、実践者と研究者のこれからの関わり方を検討していきたい。また、演出家が研究に触れる機会が少なく、そもそも研究を参照しようという意識が希薄であるという現状から、研究がより上演に寄与し、その上演が更なる研究材料となるような発展的関係性構築の方策を広く問いたいと考えている。
■プロフィール
□内田健介(うちだけんすけ)
千葉大学非常勤講師、早稲田大学演劇博物館招聘研究員。専門はアントン・チェーホフ、コンスタンチン・スタニスラフスキーを中心としたロシア演劇、日露演劇交流史。著書に『ロシア革命と亡命思想家』(共著、成文社)、『歌舞伎と革命ロシア』(共編著、森話社)ほか。論文に「スタニスラフスキー・システムにおける2つのポドテクスト」(ロシア語ロシア文学研究, 49, 2017年)、「チェーホフの『かもめ』におけるトレープレフとニーナの運命」(演劇研究, 35, 2011年)など。このほか劇団キンダースペース、俳優座、名取事務所などのチェーホフ作品などの上演に関わる。
□田中圭介 (たなか けいすけ)
演出家、ワークショップデザイナー、俳優指導者。玉川大学芸術学部パフォーミング・アーツ学科助教。武蔵野音楽大学大学院音楽研究科声楽専攻修了。ストレートプレイを中心に、演劇・オペラ・ミュージカルなど様々なジャンルの演出を手がけ、韓国の演劇祭にも招聘される。ワークショップデザイナー/ファシリテーターとしても様々な地域で活動しており、全国の小中学校・高校の他、地方自治体や企業と連携したワークショップの企画や取り組みなども行っている。青山学院大学ワークショップデザイナー育成プログラムの講師もつとめる。多摩美術大学・日本大学非常勤講師。
□新沼智之(にいぬま ともゆき)
玉川大学芸術学部パフォーミング・アーツ学科准教授。専門分野は演劇学,西洋演劇史。主にドイツを中心とする西洋演劇の近代化のプロセスを研究。論文に「A.W.イフラントが目指した舞台づくり――視覚的要素の問題を中心に」『演劇の課題2』(三恵社、2015年),「18 世紀後半のドイツにおけるアンサンブル演技理念の萌芽と劇団規則」『西洋比較演劇研究』(Vol.12 No.2、2013年)ほか。

間際の案内で申し訳ありません。初夏の駿河台で研究を深めます!
■日時:2018年5月11日(土)
■場所:明治大学駿河台キャンパス グローバルフロント 403N教室
※御茶ノ水駅に一番近い校舎の3階になります。4階ではありません。ご注意ください。
※アクセスは以下を参照下さい。
http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html
■内容
□研究発表 14:00~15:50
□住田 光子「ファース的な要素と人間の主体性の問題
――オールド・ヴィックの 『ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだ』 考」
質疑応答 15:00~15:50
□研究発表 16:10~17:00
北野雅弘「ソフォクレス『アンティゴネ』のいくつかの問題
―― ベスト・プレイズ2への翻訳の中から」
質疑応答 17:10~18:00
■発表要旨・発表者プロフィール
■住田 光子「ファース的な要素と人間の主体性の問題―オールド・ヴィックの 『ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだ』 考」
19世紀おわりに起こってきた芸術の非人間化という発想は、劇の登場人物のあり方とその遠近法に変化をもたらし、人間の主体から遠ざかることを考えさせることになった。トム・ストッパードの 『ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだ』(1967)では、そうした流れをくんだピランデルロ流の登場人物が活躍する。劇のさまざまな場面でリアリズムという言葉が出てくるように、「役者」 役の登場人物は演技のリアリズムを追求し、その一方、主人公のひとりの男 (ギルデンスターン) は、劇中劇の <死> のリアリズムに納得しない。人間の内面をさぐるようなやり取りは滑稽にもみえ、そこには笑いがある。批評家は、不条理の演劇のユーモアに関して、 世界の不条理を認識した笑いを自由にすることで、現実は解放されると述べている(ウルカー・エーカン)。本劇 には、不条理の演劇とも異なる笑いと不条理の世界の要素が共存しており、そうした要素ゆえに、ピランデルロ劇や不条理の演劇と異なる形で人間の主体性が強調されている。<芸術的な欺瞞> をおもしろがる観客がストッパード演劇には存在する。劇の人間の主体性の変容に着目したい。本発表では、おもに2017年にオールド・ヴィック・シアターで上演された 『ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだ』 のファース(笑劇)的な要素を通して、劇における人間の主体性の問題を考える。
□住田光子(すみだ みつこ)
津山工業高等専門学校総合理工学科准教授。専門分野は、英文学、演劇学。特に比較文学的アプローチから古典と現代舞台芸術のつながりを考える。専門は、シェイクスピア劇のアダプテーションと現代舞台演出意匠。ロベール・ルパージュら現代演出家の取り組みを研究する。おもな著書として、「ふたつの価値観のなかで―ジュリー・テイモアの映画 『タイタス』 における <オナー・キリング> の要素」 ( 『シェイクスピアの作品研究―戯曲と詩、音楽』 共著、英宝社、2016年) がある。
■北野雅弘「ソフォクレス『アンティゴネ』のいくつかの問題
―― ベスト・プレイズ2への翻訳の中から」
発表者は論創社による『ベスト・プレイズ2』でソフォクレスの『アンティゴネ』の翻訳を担当したが、その際に生じた以下の四つの問題を論じる。
- アンティゴネの物語はどこまで同時代の観客にとって既知であったのか。
アンティゴネはオイディプスとイオカステの間に生まれた娘で、オイディプスが自らの意思で諸国を放浪し、テバイで没した時に彼に付き従い、あポリュネイケスの埋葬によって処刑された。ギリシア悲劇は伝説に取材し、この物語自体は既知のものだとしばしば想定される。アンティゴネはアテナイの観客にどこまで、どのように知られていたのだろう。 - フェミニズムは『アンティゴネ』をどのように利用できるだろうか。
ヘーゲルがアンティゴネに親族関係の理念を代表させたことを受けて、アンティゴネには家父長的国家主義と対立するフェミニストの位置が与えられてきたが、それはどこまで正当化できるのだろうか。 - 上と密接に関係する問題だが、アンティゴネとイスメネの関係をどのように捉えるのが生産的だろうか。また、『アンティゴネ』でイスメネはどのような女性として理解できるのだろう。アンティゴネを称揚するフェミニストたちはイスメネについては沈黙してきたが、イスメネもまたフェミニズムのアイコンたりうるのではないか。
- テイレシアスの予言。
『オイディプス』ではテイレシアスは(いつからか)オイディプスの運命を知りつつ語ろうとしないが、オイディプスに強いられて予言を「謎」の形で提示する。『アンティゴネ』ではテイレシアスの予言のあり方はかなり異なっている。彼の予言をどのように理解するのが適切だろうか。
□北野雅弘(きたの まさひろ)
群馬県立女子大教授。美学、文芸学、古代ギリシアの演劇論研究。最近の研究論文はDemocracy and Athenian Tragedy: Parrhêsia as an Structural Em-Bodiment (English Journal of JSTR 1(2017)), 『芸術作品の定義』(「群馬県立女子大学紀要」38 (2018))など。共訳書として『デモステネス5』(京都大学出版会(2019))。

晴れやかな新年度となりました。今年も一年を展望する総会を開きます。ぜひご出席ください。
日時 2019年4月13日(土)午後3時~5時30分
場所 成城大学3号館3F 大会議室
http://www.seijo.ac.jp/access/index.html
3号館は、正門から中庭に進んで左側の建物です。
総会 15:00~15:45
2018年度活動および会計報告、運営委員改選、2019年度計画および予算などが議題になります。
例会 16:00~17:30(講演・質疑応答)
講演 北山研二氏(成城大学文芸学部教授)
「不可能な演劇または反復されない演劇−−−アルトーの「オリジナルのない分身」とは」
問題提起
アントナン・アルトー(1896-1948)の演劇は、不可能な演劇だと言われてきた。しかし、アルトーの後継者を名乗る、またそう見なされる者やグループが後を絶たない。グロトフスキー、カントール、ジャン・ジュネ、ベケット、リビング・シアター、ピーター・ブルック、暗黒舞踏(土方巽、室伏鴻、田中泯)、寺山修司、太陽劇団、ドアーズのジム・モリソン、カルメロ・ベーネー、ドゥルーズ=ガタリ… なぜか。彼らもまた目の前の演劇・パフォーマンス状況に深く絶望するがゆえに、新たな可能性をアルトーのうちに見いだせるからか。あるいは、演劇どころか文化までも問い直す者となると、アルトーこそ演劇の根源に、身体・思考・表象を支える文化制度を見据えるのだから、まさに演劇と文化の革命家となるからなのか。それらに答えるには、彼の「不可能の」演劇とは何かを考えなければならない。挫折したと言われる上演劇(「アルフレッド・ジャリ劇場」や『チェンチ一族』)とその前後の状況こそ(アルトーはバリ島の舞踊や、ルカス・ヴァン・デン・ライデンの《ロトの娘たち》やマルクス兄弟の『けだもの組合』『いんちき商売』に衝撃を受けて演劇観を変えたので)、彼の演劇とは不可分なのだから、それらを結び合わせて「何が」だけではなく、「どのように」不可能なのかを再考すべきではないか。
*終了後、3号館1Fホールにて懇親会があります。どうぞご参会ください。

今年度最後の例会は、動く時代を迎え「熟議」します。
パネルディスカッション
「演劇にみる《王の二つの身体》―軍神,天皇,Kaiserin―」
日時 2019年1月12日14時~18時
会場 成城大学3号館1F 311教室
コーディネーター・司会:小菅隼人(慶應義塾大学)
コーディネーター・ディスカッサント:萩原健(明治大学)
発表①:熊谷知子(明治大学)
発表②:稲山玲(明治大学)
発表③:田中里奈(明治大学)
エルンスト・H・カントーロヴィチは,著書King’s Two Bodiesにおいて,国王における「自然的身体(ボディ・ナチュラル)」と「政治的身体(ボディ・ポリティック)」の共存とその緊張関係をヨーロッパ中世政治神学の視点から考究した.「自然的身体」とは人間としての身体であり,可視的であり,病みもすれば死も迎える.他方,「政治的身体」とは象徴としての身体であり,不可視的であり,不変,不死の身体である.この二つの身体は,自然的身体の中に象徴的身体が含まれたり,また逆の形をとったり,あるいは並行しつつも儀式,衣装,所作,用語法など演劇的振舞いに媒介されて一時的に統合されたりする.しかし,その一方が「自然的身体」である以上,この二つの身体は,国王の退位や死によって分離し,新国王において,新たに再構成されることになる.平成の天皇が退位によって(生きたまま)政治的身体を失う(かもしれない)今日の日本において,この問題は演劇学がその独自の視点から考究すべき問題であろう.このパネルでは,象徴的身体はどのように成立しているのか? 自然的身体と象徴的身体はどのような関係において表象されるのか? 自然的身体と象徴的身体を媒介している演劇的メカニズムはどのようなものか? といった問題について,演劇というレンズを通して考えてみたい.
本パネルは,萩原健,宮川麻理子,田中里奈,熊谷知子,稲山玲,小菅隼人(代表)をメンバーとするJapanese Bodies / Royal Bodies 研究グループの一つの活動として行われる.小菅(司会)の趣旨説明の後,熊谷知子,稲山玲,田中里奈がそれぞれの視点から発表を行い,萩原健がディスカッサントとして論点を明確化する.その後,フロアに開きこの問題について議論を行いたい.この研究グループは,萩原,田中,宮川,小菅によって,国際演劇学会(IFTR)および国際パフォーマンス・スタディーズ学会(PSi)で既に3回の発表を行い,成果を『西洋比較演劇研究』(第17巻1号,2018)に公開した.さらに新たに熊谷,稲山を迎えて後,数回の打ち合わせ討論を行った.今回の発表にあたっては,カントーロヴィチ『王の二つの身体』(平凡社)とT・フジタニ『天皇のページェント―近代日本の歴史民族誌から』 (NHKブックス)を共通テキストとして,三人の発表者がそれぞれの専門分野を題材として発表を組み立てている.なお,この発表で言う「ロイヤル・ボディ」とは,狭い意味での国王に限らず,軍神や皇女を含めて,なんらかの意味で権威(Authority)を持ち,象徴的存在となっている身体を指している.(小菅隼人)
発表①:熊谷知子「「軍神」の二つの身体―眞山青果『乃木将軍』を中心に―」
発表要旨
日露戦争において旅順攻略を指揮した乃木希典は,大正元(1912) 年9月13日明治天皇大葬の日に妻とともに殉死した.そして日本が十五年戦争に向かうなか,乃木は講談,浪曲,映画など複数のメディアの題材となり,その「軍神」としてのイメージが広く流布していった.演劇において乃木を描いたもののなかでは,眞山青果による『乃木将軍』四部作(1929~1937)が最もよく知られている.もとは新国劇の沢田正二郎のために書かれた戯曲であったが,昭和4(1929) 年沢田が急死したため叶わず,すでに松居松翁の『乃木将軍』(1925)で乃木を演じていた二代目市川左団次が続編を引き継いで演じた.
まず,青果の乃木表象において興味深いのは,就寝時も着ていたと語り継がれる軍服姿のなかに,自らも二人の息子を戦線で亡くした父親としての悲痛を秘めていたという二重性である.この「悲劇の英雄」としての二重性こそが,大衆に訴求する大きな要因であったと思われる.次に,演じた俳優の身体に関していえば,乃木のみならず東郷平八郎やムッソリーニなど生涯数々の偉人や英雄を演じた左団次の「立派な」体躯は,乃木希典の実像とは大きく異なるということである.しかし,実際の乃木を知らない観客たちは,左団次演ずる乃木こそが乃木らしいと感じていたのである.
戦後,主に司馬遼太郎の『殉死』(1967)や『坂の上の雲』(1968~1972)によって,乃木には今度は「戦下手な愚将」としてのイメージが定着していくことになるが,今回は井上ひさしの『しみじみ日本・乃木大将』(1979)を補助線として,戦争を介在して複層的に表象された「軍神」の身体について考えたい.
発表②:稲山玲「戦後日本演劇における天皇の身体表象 野田秀樹作品を中心に」
演劇における「王と天皇」の表象を考える場合,日本の天皇表象の特性はそれがしばしば「不在」によって表象されるという点であろう.第二次世界大戦後,天皇制の問題を扱う作品は継続的に生み出されてきたが,多くの場合,天皇の身体は舞台上に現れなかった.例えば宮本研『明治の柩』(1962),佐藤信『阿部定の犬』(1975),岸田理生『リア』(1997),井上ひさし『夢の痂』(2006)なども,それぞれに天皇制と向き合う作品でありながら,天皇そのものは登場しない.
対して野田秀樹作品においては,天皇は他の登場人物と同じように舞台上に登場する.しかし同時にその身体は,不安定なものである.例えば『透明人間の蒸気』(1991)においては,天皇の分身であるところの「スサノオ」は透明人間であり,「目にまみえず」しかし「死に至らず」という中途半端な存在だと説明される.また,『贋作・桜の森の満開の下』(1989)に登場する天武天皇は,天皇を中心とした国家の枠組を構築するとともに,歴史を都合よく書き換える人物である.同作において天皇は国家の中心であり,同時に国家の欺瞞の象徴でもある,という両義性を付与されているのだ.
本発表においては,天皇が登場しない天皇制劇の一例として井上ひさし『夢の痂』との比較も交えつつ,野田作品における天皇の扱われ方を考察する.それにより,日本の演劇人が天皇という描き難い存在とどのように対峙してきたのか考える端緒としたい.
発表③:田中里奈「皇后・王妃の身体表象の多重性,または宝塚化されたKaiserin/Queen」
発表要旨
近代以来,マスメディアの発達に伴い,皇室の表象はスペクタクル化された.なかでも皇后・王妃という存在は,国家的象徴としてだけでなく,近代国家を支える「家庭」的な女性イメージとの兼ね合いの中で,様々なメディアに繰り返し取り上げられてきた.さらに大衆音楽劇の場合,地域的文脈および主催団体の思惑に応じた翻案がみられる.
この関連で注目されるのは,宝塚歌劇によるミュージカル『双頭の鷲』(2016)だ.本作は,ジャン・コクトーの同名の戯曲(1947)に基づき,王妃の象徴と実体の矛盾を描く一方で,同劇団の伝統的な娘役を超えた試みがなされている.王妃役の実咲凜音は,『ベルサイユのばら』(1976初演)のマリー・アントワネット役(2014),そして『エリザベート-愛と死の輪舞-』(1996初演)のエリザベート役(2016)と,宝塚歌劇を代表する娘役のキャラクターを演じてきた.これらの役柄は,東西の皇后・王妃のイメージと女性の社会的役割を受けて形成され,その初演時の型が世代を超えて継承・再解釈されてきた.いわば,『双頭の鷲』には,本義的な皇后・王妃の存在の二(多)重性のみならず,宝塚歌劇に特有の多重的な身体性が読み取れる.本発表はこの後者に着目し,『ベルサイユのばら』から『双頭の鷲』に至るまでの皇后・王妃の表象の継承と変遷を,同時代の社会的背景と宝塚歌劇の様式という観点から分析し,演劇における皇后・王妃の身体の多重性について論じてみたい.
発表者プロフィール
熊谷知子(くまがい・ともこ)
明治大学文学部兼任講師.専門は近代日本演劇.これまで小山内薫作・演出,二代目市川左団次主演による上演とその時代背景の分析を中心に研究を進めてきた.「小山内薫と晩年の偉人劇―『森有礼』『戦艦三笠』『ムッソリニ』」(『交差する歌舞伎と新劇』神山彰編,森話社,2016年),「中山太陽堂と小山内薫―化粧品会社と近代日本演劇の一側面」(『興行とパトロン』同,2018年)ほか.
稲山玲(いなやま・れい)
明治大学文学部助手.研究テーマは野田秀樹を中心とした現代日本演劇.最近の論文としては,「野田秀樹 『真夏の夜の夢』における 「多層的物語」 と 「終末論的世界」」(『西洋比較演劇研究』2017年3月号,日本演劇学分科会西洋比較演劇学研究会),「『野田版・国性爺合戦』に見る野田秀樹の国家イメージ」(『演劇学論集』2018年春号,日本演劇学会)他.
田中里奈(たなか・りな)
明治大学大学院国際日本学研究科博士後期課程.専門はドイツ語圏と日本のミュージカル,両文化圏間の演劇文化交流史.最近の論文:「文化政策遂行機関としてのヴィーン劇場協会 ―オーストリア・ヴィーンにおける文化営為の政治性」(『明治大学大学院国際日本学研究論集』第8号,2018).研究発表:「The Emigrant Marie Antoinette: The Re-Contextualization by Japanese Bodies in Musicals」(国際演劇学会(IFTR)年次大会,セルビア,2018).
コーディネーター/ディスカッサント
萩原健(はぎわら・けん)
明治大学国際日本学部教授.専門は現代ドイツ語圏の演劇・パフォーマンスおよび関連する日本の演劇・パフォーマンス.近年は日本の作り手による日本国外での上演に関心を寄せる.著書に『演出家ピスカートアの仕事』(2017年,森話社),共訳にフィッシャー・リヒテ『パフォーマンスの美学』(2009年,論創社)ほか.
コーディネーター/司会
小菅隼人(こすげ・はやと)
慶應義塾大学理工学部教授.専門は舞踏,および,英国チューダ朝演劇.楠原偕子先生の指導によって舞踏研究に導かれた.また,学部・大学院より,中世英文学を専門とする指導教授のもとでチューダ朝演劇の文脈においてシェイクスピア研究を進めている.『腐敗と再生:身体医文化論』(編著,慶應義塾大学出版会,2004),The Routledge Companion to Butoh Performance (共著,Routledge, 2018) ほか.

早くも年の暮れとなりました。12月例会なしに一年を締めくくることはできません。できれば終了後、忘年会代わりのささやかな席を設けたいと考えております。多数ご参加ください。
*終了後の懇親会に参加される方は、11月27日までに 山下:y3yamash★seijo.ac.jp あて、そのむねご連絡ください(★をアットマークに換えてご送信ください)。
日時 2018年12月8日(土) 14:00~18:00
場所 成城大学7号館1F 712教室
*7号館は正門を入り、中庭の右奥の建物です。
研究発表
川野真樹子 「川上音二郎一座『ハムレット』(1903)における女性キャラクターの表象」
井上優 「岩田豊雄の中のシェイクスピア――福田恆存演出『ハムレット』(1955年)の背景から」
要旨
川野真樹子 「川上音二郎一座『ハムレット』(1903)における女性キャラクターの表象」
戯曲を上演するという行為には俳優の身体を通して登場人物を解釈し、表象するという手続きが含まれる。そのため観客にとって俳優のイメージと舞台上で彼らが表象する劇中人物とを切り離して受容することは難しい。1903年に山岸荷葉と土肥春曙が翻訳・翻案し、川上音二郎一座が上演した翻案『ハムレット』では、女優、女役者、女形という異なる身体性を持つ役者たちが共演しており、それぞれの持つ身体イメージや演技手法が女性キャラクターの舞台上での表象に作用していたと考えられる。この翻案『ハムレット』(1903)は、河竹登志夫が『日本のハムレット』(1972)で指摘したように、翻案といえどもかなり翻訳に近い形を保っている。しかし山岸荷葉によれば「出勤俳優の都合」で原作に登場しない女性キャラクターを追加しており、また、川上の妻である貞奴が演じたオフィーリアの出番も原作に比べて増加している。これらの事実は『ハムレット』の翻案が俳優ありきでなされたことを示すものとして無視することはできない。また、吉原ゆかりは『江見水蔭翻案・川上音二郎一座上演『オセロ』(1903)の研究』(2004)において、俳優の身体性から川上一座の翻案『オセロ』(1903)のビアンカ(翻案では琵琶香)の表象について読み解いた。同様に俳優の身体性から翻案『ハムレット』(1903)の女性たちについて読み解くことも可能ではないだろうか。
本発表では、当時の劇評や、翻案戯曲の原作からの変更箇所を照らし合わせることで、川上一座がどのように女性キャラクターを解釈し、舞台上に表象しようとしていたのかを明らかにしたい。
発表者プロフィール 川野真樹子
明治大学大学院文学研究科・博士後期課程在籍中。研究テーマは近代日本におけるシェイクスピア受容。
学会発表:セミナー「映画で考えるシェイクスピアの多様性」(第57回シェイクスピア学会)、2018年。
井上優 「岩田豊雄の中のシェイクスピア―福田恆存演出『ハムレット』(1955年)の背景から」
1955年、福田恆存が翻訳・演出した文学座公演『ハムレット』は、日本のシェイクスピア上演史上、画期的な成功であった。この公演の背景に、福田がロンドンで見た、マイケル・ベントール演出、リチャード・バートン主演の『ハムレット』(1953)の感動体験があったことはよく知られている。実際福田自身、この公演は、イギリスで見た「ベントール演出の徹底したコピー」と語っているし、従来、その文脈で語られてきた。
だが、この上演実現の背景には、もう一つ、当時の文学座の幹事の一人であり、獅子文六の筆名で小説家としても知られる岩田豊雄の支持があった。これは、福田自身が明言していることでもあり必ずしも知られていない事実ではない。しかし、岩田自身がなじんだのはフランス演劇であり、シェイクスピアの接点はほとんどないことを考えると、岩田による福田シェイクスピア支持はにわかに納得できるものではない。なぜその岩田が福田のシェイクスピア上演を後押しすることになったのか。そしてそれはどういう意図であったのか。
そうした岩田豊雄の観点からこの『ハムレット』上演を読み解いていくと、そこに見えてくるのは、この上演自体がかなり危うい偶然の上に成立していたという事実である。岩田自身の、きわめて特殊なシェイクスピア体験から、この上演を改めて見直していきたい。
※本発表は2018年10月13日(土)に津田塾大学小平キャンパスで行われたシェイクスピア学会での口頭発表を増補・改訂したものである。
発表者プロフィール 井上優(いのうえ・まさる)
明治大学文学部准教授。専門分野は演劇学、西洋演劇史。特にシェイクスピアを中心とする禁断の演劇の表現モードの変遷を研究。近年は演劇人としての岩田豊雄の業績の再評価を複数の機会で行ってきている。 最近の論文に、獅子文六(岩田豊雄)における身体―『青春怪談』(1954)に見る不安定な性―(『西洋比較演劇研究』2018 年17 巻 1 号)、訳書にラッセル・ジャクソン『シェイクスピア映画論』(共訳、開文社出版、2004年)、共著書に『演劇の課題』『演劇の課題2』(共著、三恵社、2011年および2015年)、『シェイクスピアと日本』(編著、風間書房、2015年)など。

本分科会ではこれまでも音楽劇のシンポジウムをおこなってきました。今回はオペレッタに焦点をあてる貴重な機会となります。ぜひ多数お越しください。
日時:2018年10月13日(土)14:00-18:00
会場:成城大学8号館3F 831教室
シンポジウム「1920年代〜30年代のオペレッタとその周辺」
14:00〜15:30
発表1:森佳子「オッフェンバック作品の復活と変容—20世紀フランス・オペレッタ史の視点から」
発表2:大林のり子「ラインハルトの大劇場演出における非言語表現の展開―無言劇とオペレッタ」
〈休憩 10分〉
15:40〜17:00
発表3:小川佐和子「映画とオペレッタのあいだ:1930年代におけるエリック・シャレルとラルフ・ベナツキー」
発表4:大田美佐子「ヴァイルの音楽劇改革におけるオペレッタ」
〈休憩15分〉
17:15〜18:00
討論・意見交換
【趣旨】
今回のシンポジウム企画は、まず1920年代〜30年代のオペレッタ、特にヴァイマル期のベルリンが出発点となっている。しかし話題は、フランスからベルリンへ、そしてベルリンからヨーロッパ各地やアメリカへ、オペレッタを介して広がりを見せた20世紀前半の舞台創造の一端を超領域的な視点で扱うという目論見へと進展しつつある。個々の発表では、20年代〜30年代のオペレッタを取り巻く状況を押さえつつ、具体的には、ヴァイマル期のベルリンで舞台製作に携わり、その後、客演や亡命、あるいは映画というメディアを介して国境を越えていった事例に、それぞれの視点から触れていく。おそらく各々の考察からは、芸術や文化の国際化の問題なども浮かび上がるだろう。また、オペレッタと隣接ジャンルとしての音楽劇・無言劇・パントマイム・映画との関連の中で、当時の舞台芸術や大衆娯楽の展開を探る道筋は、今日の舞台芸術のあり方にも通底する問題を浮かび上がらせるに違いない。
【発表要旨・発表者プロフィール】
発表1 森佳子「オッフェンバック作品の復活と変容—20世紀フランス・オペレッタ史の視点から」
オペレッタというジャンルは、19世紀中頃のフランスでオッフェンバックによって創始され、ドイツ語圏などに広まった。しかし1890年代に入ると、フランスのオペレッタは衰退期に入り、ミュージック・ホールのレヴューに取って替わられる。しかしそこでは、頻繁にオッフェンバックの音楽が使われた。
ベル・エポック期を通して、レヴューが大衆化していく一方で、オッフェンバック復活の兆しが見えてくる。例えば1904年のムーラン・ルージュの『オッフェンバック・レヴュー』、1911年の《ホフマン物語》再演などが、20〜30年代の「オッフェンバック・ルネサンス」へとつながる。そして1933年、オッフェンバックの伝記を基にした、メレのミュージカル・コメディ『王子たちの通り道』がマドレーヌ劇場で初演され、大変な反響を呼んだ。本発表では、これらの「広がり」を見ることで、20世紀の劇場文化におけるフランス・オペレッタの位置付けを考える。
森佳子(もり よしこ)
日本大学他非常勤講師。博士(文学)。早稲田大学オペラ/音楽劇研究所招聘研究員および同大学イタリア研究所招聘研究員。専門は音楽学(主にフランスのオペラ/音楽劇)。
主な著書に『笑うオペラ』『クラシックと日本人』(共に青弓社)、『オッフェンバックと大衆芸術:パリジャンが愛した夢幻オペレッタ』 (早稲田大学出版部、学術叢書)、『オペレッタの幕開け:オッフェンバックと日本近代』(青弓社)、訳書に『音楽のグロテスク』(青弓社)、共著に『初期オペラの研究』『オペラ学の地平』(共に彩流社)などがある。
発表2 大林のり子「ラインハルトの大劇場演出における非言語表現の展開―無言劇とオペレッタ」
昨年5月例会でマックス・ラインハルトのオペレッタ演出について話す機会をいただいた。オペレッタを扱うことで、ラインハルト演出のポピュラリティやユニバーサリティに関する新たな考察の可能性が開かれたように思う。1910年以後に本格化したラインハルトの大劇場演出における総合芸術創造への志向、つまり非言語表現の重視と、それにともなう芸術家間での協働製作を考える時、オペレッタ演出における舞踊や音楽、そしてパントマイムなどの表現は、同時期のギリシャ悲劇やシェイクスピア劇、そして無言劇など、彼の祝祭的な舞台演出に深く結びついている。一方で、ラインハルト演出の非ドイツ語圏での展開では、この非言語表現に重点を置いた無言劇とオペレッタが高い汎用性を発揮していく。
そこで今回は、無言劇に積極的に取り組んだ作家カール・フォルメラー(1878-1948)のラインハルトとの協働を軸に考えてみたい。彼は『アンチゴーヌ』『オレステイア』などギリシャ劇の翻訳に加え、1910年〜20年代には、大戦を挟んで欧米で製作された幾つかの無言劇の台本に携わる。そこから舞踊や音楽、サイレント映画、さらには1920年代後半から30年代のベルリンやその他の国々での大衆文化との接点を探っていく。
大林のり子(おおばやしのりこ)
明治大学文学部准教授。専門は演劇学・演劇史。20世紀前半の欧米演劇における協働製作について、主に演出家マックス・ラインハルトの国際的な場における協働製作に注目し、近年は両大戦間の時代における舞台芸術のあり方を再考している。論文に『ラインハルト演出『奇蹟』アメリカ公演(1)--その興行的戦略--』(『演劇学論叢』11号、2010年)、『第一次世界大戦期ベルリン・ドイツ劇場のレパートリーにみる民衆劇-ライムント喜劇『ラッペルコップ』演出-』(『演劇学論叢』14号、2015年)、『マックス・ラインハルトのオペレッタ演出-新たな祝祭劇への接点(1)』(『近現代演劇研究』7号、2018年)など。
発表3 小川佐和子「映画とオペレッタのあいだ:1930年代におけるエリック・シャレルとラルフ・ベナツキー」
映画はその誕生時から、隣接する芸術ジャンル、とりわけ演劇界との人的・技術的・芸術的交流が盛んであった。オペレッタとの関係も、いまだ映画が「無声」であった19世紀初頭から築かれ、それは1930年代以降に「トーキー」技術が発展することでさらなる展開を迎えることとなる。
本報告では、ラルフ・ベナツキー作曲の『白馬亭にて』(1930年、ベルリン大劇場)、『アクセル、天国の扉の前で』(1936年、アン・デア・ウィーン劇場)およびエリック・シャレル監督の『会議は踊る』(1931年、ウーファ社)をとり上げる。『白馬亭にて』では、シャレルが演出を担当した点に注目し、オペレッタと映画の人的交流の側面を主に見る。映画を題材にしたオペレッタ『アクセル、天国の扉の前で』では、ハリウッドの諷刺という内容面に注目し、作品分析を行う。オペレッタ映画『会議は踊る』では、映画におけるシャレルの演出を考察する。以上の事例をつうじて、1930年代における映画とオペレッタの協働の展開を考察していきたい。
小川佐和子(おがわ さわこ)
京都大学人文科学研究所助教。専門は映像学。早稲田大学文学研究科演劇映像学コース博士課程終了。博士論文は「1910年代の比較映画史研究:初期映画から古典的映画への移行期における映画形式の形成と展開」(2012年)。チューリヒ大学映画学科客員研究員(2012-13年)を経て現職に至る。在任中にウィーン大学文献・文化学科東アジア学研究所へ所外研修(2015-2017年、オーストリア政府奨学生、研究課題「19世紀後半から1930年代にかけての映画・演劇をめぐる日欧比較研究」)。
主著『映画の胎動:1910年代の比較映画史』(人文書院、2016年)。オペレッタ関連の論文に「「命かけて只一度」:《会議は踊る Der Kongress tanzt》をめぐる映画とオペレッタの演出」(『季刊iichiko』第131号、2016年)。
発表4 大田美佐子「ヴァイルの音楽劇改革におけるオペレッタ」
クルト・ヴァイル(1900-1950)は、20年代半ばからベルリン、パリ、ニューヨークと亡命によって活動場所を変えながら、音楽劇を作り続け、その創作全体は「音楽劇改革」として捉えられている。創作された音楽劇のジャンルは多岐にわたるが、「モダニズム」と「ポピュラリティ」の狭間で試行錯誤した彼にとって、「オペレッタ」もまた重要なジャンルであった。しかし、興味深いことに、1933年までのベルリン時代に「オペレッタ」は作曲されていない。ヴァイルが明確にオペレッタと表現していたのはパリ時代に作曲された《Kuhhandel》(1934)とニューヨーク時代に作曲された《The Firebrand of Florence》(1944)。オペレッタとは、ヴァイルの音楽劇改革にとってどのような存在であったのか。今回は、1920年代末から30年代にかけての「新しいオペレッタ」としての《三文オペラ》をめぐる議論を起点に、20世紀前半の「オペレッタ」論を考察していきたい。
大田美佐子(おおた みさこ)
神戸大学大学院人間発達環境学研究科准教授。専門は音楽文化史、音楽美学。東京藝術大学音楽学部楽理科で音楽学を、学習院大学大学院人文科学研究科でドイツ演劇を学ぶ。ウィーン大学音楽学研究所留学 (オーストリア政府奨学生) を経て,ウィーン大学人文学研究科博士課程修了(音楽学)。博士論文は「芸術の要請と 社会的効果 1930年代へと向かうクルト・ヴァイルの音楽劇」。2013-14年 ハーバード大学音楽学部客員研究員。2003年より新聞などで舞台批評の分野でも活動。ヴァイル関連の論文には「アメリカで見た景色─クルト・ヴァイルの社会派音楽劇の軌跡─」(岩波『文学』所収2014年3,4月号)などがある。音楽文化史と受容史を接続する「越境的・対話的音楽文化史」の観点から、現在、若手研究者も巻き込んで、キャロル・オジャ教授(アメリカ音楽史)との共同研究を進めている。

酷暑の候、皆様いかがお過ごしでしょうか。下記の要領で例会を開催いたします。お目に掛かれれば幸いです。
日時 2018年7月28日(土) 14:00~18:00
場所 成城大学3号館1F 311教室
*3号館は正門を入り、中庭左側の白い建物です。
内容
現在進行形の演劇(トーク&ディスカッション) 14:00~16:00
瀬戸山美咲・田ノ口誠悟「『ジハード−Djihad—』現在進行形の演劇」
論文合評 16:10~18:00
萩原健・横堀応彦・寺尾恵仁(Skype参加)・山下純照(司会)
「『演劇学論集』66 特集「ドラマトゥルク/ドラマトゥルギー」をめぐって」
出典リンク https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjstr/66/0/_contents/-char/ja
要旨 「『ジハード−Djihad—』現在進行形の演劇」
2014年12月のベルギー初演後、注目を集め続けている演劇作品『ジハード−Djihad−』。上演の実現を目指す人々の輪は広がり、全世界ですでに42万人がこの作品を観ている。
この作品は、モロッコ移民二世であるイスマエル・サイディが、排外主義の広がるヨーロッパの状況に危機感を抱き執筆した。物語のきっかけは、ベルギーで生まれた移民二世のムスリムの若者3人が、「ジハード(聖戦)」に参加するためにシリアに向かうというもの。彼らは、まるで旅行にでも行くかのようにベルギーをあとにするが、旅の途中でそれぞれの抱える悩みが明らかになっていく。彼らはベルギー社会とムスリムの戒律のはざまで自分たちの可能性を狭められている。そして、その行き場のなさの受け皿として過激思想が存在していることが明らかになっていく。
サイディ氏は自らも出演しながら上演を続け、上演後には観客とディスカッションの時間を持ってきた。パリ同時多発テロの標的となったバタクラン劇場の被害者や遺族を対象に上演をおこなったこともある。また、ベルギー・フランス両政府からの要請で、ティーンエイジャー向けの上演も続けている。笑いの要素も非常に多く、ティーンエイジャーたちはスタンドアップコメディ感覚で舞台を観ているうちに、日常と地続きの戦争に引きずり込まれる。舞台作品としては非常にシンプルな形を持ちながら、過激思想に染まる若者が置かれている状況について、過不足なく、非常に巧みに描かれた戯曲だ。
日本では2016年12月のリーディングを経て、今年6月にさいたまネクスト・シアターによる上演が実現した。観客も俳優も「同質」という幻想の強い日本でこの作品はどう受け止められたか。そして技能実習生など実質的には移民と見なされる人々が増加していくことが予想される日本において、今後考えられることと、そのとき演劇の果たす役割について考えたい。
プロフィール
瀬戸山美咲(せとやま みさき)
劇作家・演出家・ミナモザ主宰。代表作に『彼らの敵』(第23回読売演劇大賞優秀作品賞)『指』『ファミリアー』『ホットパーティクル』『始まりのアンティゴネ』など。ロンドンバブル『ヒロシマの孫たち』(脚本)など地域の市民とつくる演劇にも携わる。『ジハード−Djihad−』は2016年の国際演劇協会主催「紛争地域から生まれた演劇」にておこなわれたリーディングおよび2018年のさいたまネクストシアターØによる上演で演出を担当。
田ノ口誠悟(たのくち せいご)
早稲田大学・文京学院大学非常勤講師。専門:演劇学、20世紀フランス演劇史、舞台翻訳。『ジハード』上演で戯曲翻訳を担当。『ジハード』関連の出版物:「ジハード−Djihad−」(翻訳と解題)、『国際演劇年鑑2017 戯曲集』(国際演劇協会日本センター報告集)、2017年3月。 「『ジハード』翻訳雑感:グローバリゼーションをめぐる卓越した思想劇」、『日仏演劇協会会報7号』(日仏演劇協会)、2017年5月。
要旨 論文合評会
この合評会は、親学会である日本演劇学会機関誌『演劇学論集』最新号の特集「ドラマトゥルク/ドラマトゥルギー」に収められた4本の論文のうち、3本の著者を招いて、分科会としてその内容をより深く咀嚼し、問題意識を共有するために開催するものである。例会企画者・山下は、同誌編集委員長(当時)として特集の立ち上げからかかわり、特集責任者に藤井慎太郎氏を招いた。残念ながら藤井氏はパリでの研究休暇中のため合評会への参加はかなわない。論文執筆者の一人も別の研究会の運営のため不参加となるが、それ以外の執筆者に登壇願う。ただしそのうちの一人寺尾氏は現在ドイツ・ライプツィッヒ大学演劇学研究所に留学中のため、本会としては初めてのSkypeによる中継を試みることになる。
論文が掲載された雑誌は既に演劇学会会員には配布されているが、そうでない参加者諸氏もリンクからアクセス可能なので、できるかぎり論文を一読の上ご参加いただきたい。扱う論文は次の通りである:
・横堀応彦「<フェスティバル化>する時代におけるドラマトゥルギー」
・寺尾恵仁「語りのドラマトゥルギー」
・萩原健「築地小劇場のドラマトゥルギー」
以上。
プロフィール
萩原 健(はぎわら けん)
明治大学国際日本学部教授。専門:20世紀以降のドイツ語圏の演劇、および関連する日本の演劇。 研究と並行して、戯曲翻訳、字幕翻訳/制作/操作、稽古場通訳も⼿掛ける(⽇本語/ドイツ語)。訳書にフィッシャー=リヒテ『パフォーマンスの美学』(共訳)ほか、著書に『演出家ピスカートアの仕事 ドキュメンタリー演劇の源流』。近年は、日本の演劇人のドイツ語圏での活動に関心を寄せる。
横堀応彦(よこぼり まさひこ)
立教大学・跡見学園女子大学兼任講師。 演劇学、ドラマトゥルギー研究。 東京藝術大学大学院音楽研究科博士後期課程修了。博士(学術)。ライブツィヒ音楽演劇大学にて、ドラマトゥルギーを専攻(ロータリー財団奨学生)。 論文:「<フェスティバル化>する時代におけるドラマトゥルギー」『演劇学論集 日本演劇学会紀要』66(2018)、「投票する観客たち」『舞台芸術』19(2015)ほか。
寺尾恵仁(てらお えひと)
演劇学・独文学専攻。ライプツィヒ大学演劇学研究所博士課程。「反復されるフィグーア――クリストフ・マルターラー演出『ムルクス』における歴史批判」(『ドイツ文学』第154号所収)により第58回(2018年)ドイツ語学文学振興会奨励賞受賞。
山下純照(やました よしてる)
西洋比較演劇研究会事務局長。成城大学文芸学部教授。この研究会の30周年記念事業の一つ『西洋演劇論アンソロジー』(仮称)の編集・執筆で忙殺されている。

学問研究に好適な季節、若手とベテランの充実した研究発表です。多数ご参会ください。
日時 2018年5月19日(土) 14:00~18:00
場所 成城大学3号館1F 312教室
*3号館は正門を入り、中庭左側の白い建物です。
内容
研究発表 14:00~15:00
丸山達也「ポストドラマ演劇におけるドラマ上演—ニコラス・シュテーマンの『群盗』演出において脱テクスト化される言葉—」
質疑応答 15:00~15:50
研究発表 16:10~17:10
山下一夫「台湾の影絵人形劇と弋陽腔」
質疑応答 17:10~18:00
発表要旨・発表者プロフィール
丸山達也「ポストドラマ演劇におけるドラマ上演—ニコラス・シュテーマンの『群盗』演出において脱テクスト化される言葉—」
ハンス=ティース・レーマンによれば、彼の提唱した「ポストドラマ演劇」という概念は、決して反/非ドラマ的であるわけではなく、ドラマ/テクストを、上演で知覚される他の様々な要素と同列に扱うものである。そのため、同概念で捉えられる演劇は必ずしもドラマと断絶関係にあるのではなく、ドラマもその範疇において「ポストドラマ的」に上演され得る。
では、ポストドラマ演劇においてドラマを上演するとは具体的にどういうことなのか。本発表では、フリードリヒ・シラーの『群盗』(ニコラス・シュテーマン演出,2008年)をその一例として取り上げ、上演分析を通じてこれを検証する。単純にテクスト(とその解釈)を提示するのではなく、観客を常に、一義的には捉えきれない「緊張関係と逆説性」の中に置こうとするシュテーマンの演出手法には、まさにポストドラマ的な特徴が見て取れる。彼の演出する『群盗』では、ドラマとして構成されたテクストは個々の場面、ないしより小さな単位に分解されている。また、俳優たちは特定の登場人物に固定されることなく、戯曲中の言葉を多彩かつ過剰なやり方で発話することにより、言葉/台詞とその帰属先である登場人物との間、そして舞台上の俳優と登場人物との間に一致とズレを生じさせる。
このような一致とズレのダイナミズムによって、観客の認識が揺さぶられた結果、言葉がドラマにおける台詞という役割から解放されるプロセスを、本発表ではエリカ・フィッシャー=リヒテの「現象的肉体」と「記号的身体」という二つの身体概念を援用しながら具体的に提示するとともに、シュテーマン演出の『群盗』が、「ポストドラマ的」な演出として、シラーの言葉そのものが持つ魅力に、新たに光を当てるものであることを示したい。
プロフィール:丸山達也(まるやま たつや)
獨協大学大学院外国語学研究科・博士後期課程満期退学(2018年3月)。研究領域は、フリードリヒ・シラーを中心にドイツ近代文学・演劇、現代のドイツ語圏演劇。論文:「『群盗』について―フランツ・モールのもつ二重の役割―」(獨協大学大学院紀要『BRÜCKE』第27号,2014年)、「Zur Räuber-Rezeption seit den 60er Jahren」(『BRÜCKE』第28号,2015年)。
山下一夫「台湾の影絵人形劇と弋陽腔」
台湾の人形劇は一般に手袋人形劇が優勢だが、南部の高雄市にはわずかながら影絵人形劇も分布している。手袋人形劇が福建省から伝来した北管戯や、北京から流入した京劇などの音楽を用いるのに対し、影絵人形劇は広東省に由来する潮調を使っている。この潮調は、中国四大声腔の一つである弋陽腔の地方変種である潮劇と音楽が共通する。中華圏の伝統演劇では、新たに作品を作る際に「作曲」が行われることは無く、常に既存の曲調が用いられる。そのため演劇の種類も「どのメロディを使っているか」によって定義されるが、そうすると、同じメロディを用いていれば、仮に人形劇であってもそれは同一の「劇種」、ということになる。もちろん、人形劇には人間の演劇には無い様々な要素が存在するが、そうした観点から捉えると、台湾の影絵人形劇は潮劇と「同じ種類」と言うこともできるだろう。本発表では、こうした台湾の影絵人形劇の「劇種」の問題について、中国演劇史における位置づけや、台湾伝来の状況なども検討しながら、考察して行きたい。
プロフィール:山下一夫(やました かずお)
慶應義塾大学理工学部准教授。専門は中華圏の古典小説・伝統演劇・宗教信仰。『全訳封神演義』全4冊(共訳、勉誠出版、2017年~2018年)、『明清以來通俗小説資料彙編』(共編、博揚文化事業有限公司、2016年)、『近現代中国の芸能と社会―皮影戯・京劇・説唱』(共著、好文出版、2013年)など。

日時 2018年4月14日(土)午後2時~5時15分
場所 成城大学3号館3F 大会議室
http://www.seijo.ac.jp/access/index.html
3号館は、正門から中庭に進んで左側の建物です。
総会 午後2時~3時
2017年度活動および会計報告、2018年度計画および予算などが議題になります。
例会 午後3時15分~5時(講演・質疑応答)
講演 西村太良 「見えるものと見えないもの」
講演要旨
ギリシア悲劇が実際にどのように上演されたかについては判らないことがたくさんありますが、基本的なルールとして劇場の空間的制約があったことは確かだと思われます。すなわち観客が見ることのできるのはコロスの位置するオルケーストラーと俳優たちが出入りするスケーネーに限られていたということです。その外の世界を観客が見ることはできません。このことは叙事詩のように言語だけを媒体としたジャンルと決定的に異なる点です。幕とか場という形式を持たないギリシア劇にあっては一度場の設定が決まればコロスを含む劇中人物の見る世界と観客の見る世界は基本的に同一であるということになります。しかし、この空間的制約は言葉によって補完されていました。舞台上で直接立ちまわりが演じられることは殆どありませんでしたが、使者の報告という形により舞台の外で起こった事件が言葉によって舞台上の人物と観客に伝えられ、また舞台裏からの声によって間接的に事件が暗示されるという趣向も少なからず用いられていました。ただ視覚的であろうと言語的であろうと与えられる情報は舞台と観客席で共有されるという原則が了解されていたと思われます。しかし、時として言葉によって舞台上にその存在が指示されているにもかかわらず観客には見えない場合もあります。あるいはまた逆に観客には視覚的に見えているにもかかわらず舞台上の俳優には見えていない、あるいは別様に見えているという設定の場合もあります。これはある意味では上に述べたギリシア劇の上演上の基本的ルールから逸脱しているのではないかとも思われます。今回はこの点についていくつかの作品を取り上げて具体的に検討してみたいと思います。
プロフィール:西村太良1949年生まれ、慶應義塾大学文学部および文学研究科修了、慶應義塾大学文学部教授、文学部長、常任理事、言語文化研究所所長を経て、現在名誉教授、アテネ大学、オクスフォード大学留学、専門は西洋古典学、古代ギリシア抒情詩、悲劇、現代ギリシア語など。翻訳に『ギリシア悲劇全集』,『ギリシャ喜劇全集』(岩波書店)ほか多数。
*終了後、3号館1Fホールにて懇親会があります。どうぞご参会ください。

間際のお知らせになりまして、まことに恐縮です。今年度最後の例会は、昨年末から継続のシンポジウム、および個人研究になります。前回に続き、多数の方にお目にかかれますことを期しています。
日時 平成30年1月20日(土) 14:00~18:00
場所 成城大学7号館 731教室(3F)*前回と同じ場所です。
14:00~16:10 シンポジウム<ポストドラマ演劇:20年後の受容と検証Ⅱ>
14:00 ~ 14:15 はじめに 山下純照
14:15 ~ 15:00
発表1 江口正登『アメリカ合衆国における(ポスト)ドラマ理論の展開』
(発表25分+議論15分。交代5分)
15:00 ~ 15:40
発表2 北川千香子『オペラにおけるポストドラマ演劇 ― クリストフ・シュリンゲンジーフの《パルジファル》演出(2004)を例として』
(発表25分+議論15分)
15:40 ~ 16:10 シンポジウムを振り返って 山下純照(総括・司会)
休憩10分
16:20 ~ 18:00 研究発表
稲山玲「野田秀樹『透明人間の蒸気』における、悲劇で終わらない『ロミオとジュリエット』と天皇制」
(発表50分+質疑応答50分)
*例会後、新年会を兼ねた懇親会を行います。
会場は7号館地下ラウンジ(会費制 3000円)
発表要旨・発表者プロフィール
<ポストドラマ演劇:20年後の受容と検証Ⅱ>
発表1 江口正登
『アメリカ合衆国における(ポスト)ドラマ理論の展開』
アメリカ合衆国という文脈の中でポストドラマ概念について考える際、同概念とパフォーマンス研究というディシプリンとの関係について考えることは不可避の作業である。ポストドラマの概念とパフォーマンスの概念は、いずれもドラマ概念の相対化を伴うという意味では共通する志向を持ちつつ、すれ違う側面も大きい。アメリカにおけるポストドラマ概念の受容について検討することは、ヨーロッパの演劇研究とアメリカのパフォーマンス研究という、雑駁ではあるがそれなりに当を得ている二項対立の委細を具体的に検討するための事例的価値を持つと思われる。本発表ではこの点に関して、『ポストドラマ演劇』およびこれに関連するレーマンのテクスト、また、『ポストドラマ演劇』英訳版に対するエリノア・フックスの批判的な書評およびこれに対するレーマンと英訳者カレン・ユルス=ムンビーの反論を中心的な材料として検討する。
ところで、近年のアメリカ合衆国では、ドラマと書かれたもの、パフォーマンスとエンボディメントをそれぞれ同一視した上で、この二つのペアを単純に対立させてきた――その上で後者の優位を主張してきた――パフォーマンス研究の立場に再考を迫る議論が生じてきている。本発表では、とりわけ代表的な議論として、W・B・ウォーゼンの『ドラマ:詩とパフォーマンスの間に』(W. B. Worthen, Drama: Between Poetry and Performance)について検討する。ドラマをパフォーマンスの対立物ではなく、そのためのエージェンシーと考える同書の立場は、翻って、パフォーマンスおよびポストドラマの概念を、より立体的な仕方で考えていくための助けとなるだろう。
江口正登
立教大学現代心理学部映像身体学科助教。パフォーマンス研究、表象文化論。論文:「大森靖子、みんなのうたはだれのうた?」(『ユリイカ』第49巻7号、2017年)、「パフォーマンスの場はどこにあるのか」(共同討議、田中均・武藤大祐・森山直人と、『表象』第10号、2016年)、「ジョン・ジェスラン『ファイアフォール』のアクシデント」(『西洋比較演劇研究』第15巻第1号、2015年)、「カメラが演じる/語るとき--ジョン・ジェスランの『スノウ』」(『西洋比較演劇研究』第13巻第2号、2014年)など。
発表2 北川千香子
『オペラにおけるポストドラマ演劇 ― クリストフ・シュリンゲンジーフの《パルジファル》演出(2004)を例として』
ポストドラマ演劇の一つの重要なジャンルであるオペラは、台詞劇、パフォーマンス、ダンスといった舞台芸術とは異なり、ある特殊な緊張の場に置かれている。ポストドラマ演劇は、ドラマの言語テクスト、そこに描かれた語る主体や筋行動が中心であるとは考えず、上演を成り立たせるすべての演劇的要素を等価に扱う演劇と定義づけられる。オペラ芸術において「テクスト」とは、言語テクスト(台本)のみならず、音楽テクスト(楽譜)をも意味する。音、響き、リズム、テンポ、身体性、空間性、身振りなどのポストドラマ的要素、すなわちドラマという範疇では捉えきれない要素が、すでにこの音楽テクストのなかで規定されている。さらに、音楽テクストは上演空間で歌われ演奏されることによって音声化・音響化されることを前提としているため、いかなるオペラも多かれ少なかれポストドラマ性を内在させていると言える。
同時に、音楽テクストはオペラ上演の進行プロセスを決定づけるものであり、必然的に演劇的要素のヒエラルキーの上位に位置する。そのため、オペラが音楽テクストから逸脱することは基本的に不可能であり、楽譜を素材の一つとみなしてテクストを解体したりテクストに介入したりすることは現代でもタブー視されている。つまりオペラ芸術は、テクスト上の制約、さらにはオペラ劇場や制度の構造的な制約の下に置かれているのである。
しかしそうした制約への抵抗や摩擦こそが、新たな知覚経験や意味の地平を生み出す生産的な力を生み出している。このことを検証するために、オペラ演出史に大きな波紋を呼んだクリストフ・シュリンゲンジーフの《パルジファル》演出(バイロイト音楽祭、2004年)を例に取り上げる。ここでは、シュリンゲンジーフの美的戦略(極端あるいは過剰への傾向、記号の横溢、リゾーム状に生じては破壊されるイメージ、時間と空間の拡張、多様なメディアの投入、逸脱した身体など)が、いかなる知覚作用をもたらし、また原作のテクストといかなる連関を作り出し、それによって伝統の枠組みに強く依存するオペラ芸術の「超越」を試みているかを明らかにしたい。
北川千香子
慶應義塾大学准教授。演劇学、オペラ研究。2013年ベルリン自由大学哲学人文学科演劇学研究所修了、同大学にてPh.D.取得。主な著訳書:マルティン・ゲック著『ベートーヴェンの交響曲――理念の芸術作品への九つの道』(単訳、音楽之友社、2017)、『キーワードで読むオペラ/音楽劇研究ハンドブック』(共著、アルテスパブリッシング、2017)、マルティン・ゲック著『ワーグナー』上下巻(共訳、岩波書店、2013/2014)、“Versuch über Kundry – Facetten einer Figur“ (単著、Peter Lang、2015)。
<研究発表>
稲山玲
「野田秀樹『透明人間の蒸気』における、悲劇で終わらない『ロミオとジュリエット』と天皇制」
本発表においては野田秀樹『透明人間の蒸気』(1991年初演)を取り上げ、そこに描きこまれた野田の天皇制に対する問題意識を読み取ることを目的とする。野田秀樹は1980年代後半から継続して翻案作品を手がけており『透明人間の蒸気』は約4年ぶりのオリジナル作品となった。
オリジナル作品ではあるが、本作は全体としてシェイクスピア『ロミオとジュリエット』のパロディとなっている。ただしそれは悲劇で終わることができない『ロミオとジュリエット』である。本作でロミオにあたるのは結婚詐欺師のアキラ、ジュリエットにあたるのは盲目の少女ケラである。2人は鳥取砂丘で出会い、結婚の約束をする。劇中では、幾度か心中場面のパロディがあるが、いずれも行為は完結しない。悲劇には「死」という絶対的な終末が不可欠だが、本作において終末は常に先送りされてしまうのである。
上記の『ロミオとジュリエット』のパロディと平行して進行するのが、アキラが現人神へと仕立て上げられていく物語である。鳥取砂丘では昭和天皇の勅令を受けた華岡軍医らが「20世紀で滅びてしまうもの」を収集し、21世紀に送る任務を遂行している。彼らは21世紀へ送る肉体としてアキラを選ぶが、転送装置の故障でアキラは透明人間になってしまう。透明人間となったアキラは「神様」と呼ばれ、徐々に現人神へと祀り上げられていく。この描写は明らかに天皇制への言及と言えるだろう。
終末が先送りにされる世界観と天皇制の問題はどのように結びつくのだろうか。時代背景も含めて考察したい。
プロフィール:
明治大学大学院文学研究科・博士課程在籍中。研究テーマは野田秀樹を中心とした現代日本演劇。論文として「野田秀樹『真夏の夜の夢』における「多層的物語」と「終末論的世界観」」(『西洋比較演劇研究』第16号)。

西洋比較演劇研究会2017年12月例会のご案内(詳細版)
すでに発表題目のみお知らせしましたシンポジウムの詳細がまとまりましたので、ご案内いたします。内容に鑑み、全体の時間を20分ほど延長しました。
日時 平成29年12月16日(土) 14:00~18:30
場所 成城大学7号館 731教室(3F)
シンポジウム<ポストドラマ演劇:20年後の受容と検証Ⅰ>
14:00 ~ 14:15 問題提起 山下純照(司会)
14:15 ~ 15:40 第一部 レーマン理論の検証/外部との折衝
発表1 平田栄一朗「脱措定的な差異としてのポストドラマ演劇」
(発表25分+議論25分)
発表2 井上由里子「『ポストドラマ演劇』とフランス演劇の間にみられる互恵性」
(発表25分+議論10分)
休憩10分
15:50 ~ 17:35 第二部 具体的検証/受容の拡大
(各発表25分+議論10分)
発表3 針貝真理子「ベルギー・フランデレン文化圏における「ポストドラマ演劇」―ニードカンパニー『ロブスターショップ』における封じられた声の演出を例に―」
発表4 鈴木美穂「イギリスにおけるポストドラマ的演劇の状況:「登場人物」をめぐって」
発表5 高橋慎也「ポストドラマ演劇の観点から照射する現代日本演劇―岡田利規の 戯曲・上演を例として―」
休憩10分
17:45 ~ 18:30 第三部 フロア・ディスカッション
発表要旨・発表者プロフィール
問題提起 山下純照
「ポストドラマ演劇」概念の、学術的なレベルでの検証や、受容の研究は、ドイツ語圏、英語圏、フランス語圏、そして日本において継続的になされてはきたものの、実はまだこれからという状況である。その一方で、ポストドラマ演劇と言える様々な現象じたいは、日本でも、英語圏でも、フランス語圏でも展開している。そろそろ各国演劇研究者による共同の、検証作業と受容の研究が必要な段階に入ったのではないだろうか。こうした情勢を踏まえ、本会では二回にわたってこの概念をめぐるシンポジウムをおこないたい。
そのさい当然ながらハンス=ティース・レーマンの『ポストドラマ演劇』における理論が出発点になる。しかし本書にはポストドラマ演劇というときの「ポスト」の意味合いは何かといった複数の基本的な問題点がある。レーマンはポストドラマは「反ドラマではない」と説明しているが、さらなる解明が必要である。またポストドラマ演劇におけるテクストと上演の多様な関係性や、「政治演劇」とは異なる、「演劇の政治性」をひらくものとしてのポストドラマ演劇の可能性といったように、同書の投げかける問題系は多岐にわたる。こうした諸問題の少なくとも基本的ないくつかに、理論的および具体的研究を通じてアプローチしたい。
山下純照
日本演劇学会理事・西洋比較演劇研究会事務局長。演劇学会紀要『演劇学論集』編集委員長。成城大学文芸学部教授。近現代ドイツ演劇・演劇理論。
発表1 平田栄一朗
「脱措定的な差異としてのポストドラマ演劇」
1999年に上梓され、その後20数各国語に翻訳されたハンス=ティース・レーマンの著『ポストドラマ演劇』が演劇界と演劇研究に大きな反響を呼び起こしたことに疑問の余地はないだろう。他方、その論が複雑かつ多岐に亘っているため、同書の意義や意図が明確ではないことも確かである。
この見通しがたい多種多様さを踏まえつつ、本発表は、同書に一貫する三つの点を指摘することで一定の指針を示したい。一つ目は、同書は「ポストドラマ」という概念を前面に押し出しているものの、それと同時に「演劇とは何か」という問いを立て、それに対して答える姿勢である。同書はポストドラマという概念を最初に念頭に置いて、この概念に上演の実例を当てはめたのではなく、舞台芸術に固有の多種多様な特徴は何かという問いを考察することを主眼とする。この考察を重ねるなかでレーマンは、従来の演劇観(ドラマ中心の演劇)はもはや有効ではないという結論に達して、「ポストドラマ」という概念が提唱されたと考えるべきである。
二つ目は、同書が、演劇の特徴を脱措定的な差異の運動体にあると考え、それを個々の舞台作品や演劇的事象に照らし合わせて解き明かそうとする姿勢である。例えば演劇に特有な状況、すなわち「今ここ」に立ち現れ、観客に経験化されるプロセスとその諸構成要素(身体、時間、空間、言語、声、メディア、出来事など)は、一義的な概念で収まり切れない異質なものの運動体として捉えようとする。それゆえに眼前の俳優身体が脱身体で物質的でもあるとみなされたり、舞台上のリアルな時間が戯曲の時間と異なる「もう一つ」の時間とみなされたり、言葉や声が作者・登場人物ではない他者の言葉や声でもあると指摘される。曖昧とも取れるこの論述において一貫するのは、演劇の個々の現象を、一義的アイデンティティで固定化する、すなわち、措定することを避けることで、その現象のダイナミズムを捉えようとする試みである。
三つ目は、主体に対するラディカルな問い掛けである。舞台上の人物は、俳優であり登場人物であるだけでなく、集合体の人間や、仮面を付けていないのに付けた者であると指摘される。観客は、眼前にいる人物や出来事をしっかりと見て把握するが、それでもわからない不明な何かがあるという観劇の限界が指摘される。このように俳優や観客の自明性がラディカルに問われ、私(たち)が私(たち)であるのは不確定な状況でしか成り立たない隠れた実態が、個々の演劇的状況から繰り返し論じられる。
これら三つの指摘はドラマよりも演劇の状況に当てはまる。『ポストドラマ演劇』はドラマの有効性の限界を指摘しただけでなく、演劇の固有性を(二つ目・三つ目の例に暗示される)脱構築的な人間観・世界観で説明する。本発表は、上記の三点を手掛かりにして同書の意義を検証する。
平田栄一朗
演劇学・ドイツ演劇研究。慶應義塾大学文学部教授。1997年慶應義塾大学文学研究科博士課程満期退学。博士(文学)。主な著訳書『ドラマトゥルク』(三元社)、『在と不在のパラドックス――日欧の現代演劇論』(三元社)、『Theater in Japan』(共編著、Theater der Zeit社)、『ニーチェ 三部作』(翻訳、論創社)、『バルコニーの情景』(翻訳、論創社)、『パフォーマンスの美学』(共訳書、論創社)、『ポストドラマ演劇』(共訳書、同学社)。
発表2 井上由里子
「『ポストドラマ演劇』とフランス演劇の間にみられる互恵性」
2002年刊行の仏訳『ポストドラマ演劇』の序文において著者レーマンは、テクスト分析中心のフランス演劇研究、なかでも近現代演劇のドラマトゥルギー研究を率いるジャン=ピエール・サラザック(1946年-, パリ第三大学名誉教授)の論の限界を指摘した。これに対してサラザックは2007年に異議を唱え、2011年には再度レーマンが持説を展開している。
この一連の議論は、おそらく両者の間にいくつかの誤解があったために、平行線を辿ることになった。その原因のひとつに、レーマンの批判対象が1981年に発表されたサラザックの「ラプソディー的rhapsodique」概念に限られていることが挙げられる。このことは、近年のフランスにおけるテクスト研究について共通認識が欠けていたことを示している。なぜなら、2000年代には、サラザックをはじめとするパリ第三大学の教授陣の薫陶を受けた研究者によって、身体や舞台を視野に入れたテクスト分析の手法が考案され、「音声性oralité」 や「演作者auteur en scène」などの新概念が提出されているからである。
こうした概念が「ポストドラマ演劇」から着想を得たとは考えにくいが、そこから刺激を受けた可能性を否定することもできない。だとすれば、「ポストドラマ演劇」理論とフランスの演劇研究は、緊張関係にあるようにみえて、じつのところ互恵関係を結んでいるのではないだろうか。それは、現代演劇の多様な実践を捉えるのにアルトーとマラルメの理論が有効であることを示した「ポストドラマ演劇」理論の功績にも現れているように思われる。
井上由里子
静岡文化芸術大学講師。演劇学・フランス演劇研究。論文に「ヴァレール・ノヴァリナの転換期における演出家クロード・ビュシュヴァルトの役割――『時に住むあなた』、『食事』、『架空のオペレッタ』演出をめぐって」(『演劇学論集』第62号、2016年)、 « La variation des personnages dans L'Espace furieux de Valère Novarina »(Les études françaises au Japon, Presse Universitaire de Louvain, 2010)など。
発表3 針貝真理子
「ベルギー・フランデレン文化圏における「ポストドラマ演劇」― ニードカンパニー『ロブスターショップ』における封じられた声の演出を例に―」
レーマンの「ポストドラマ演劇」は、1980年代以降にダンスを中心に興隆したベルギー・フランデレン文化圏における舞台芸術からも多大な影響を受けており、彼の地においてポストドラマ的演劇は現在もなお重要な位置を占めている。本発表ではその一例として、造形芸術から出発したキャリアを持つヤン・ローワースによって1986年に設立され、演劇テクスト、俳優術、美術、音楽、ダンスが等価に扱われるポストドラマ的試みを続けているニードカンパニーの『ロブスターショップ (2006)』を取り上げる。
ニードカンパニーの舞台では、彼らが拠点を置くベルギーの首都ブリュッセルの複雑な言語環境を反映して、オランダ語、フランス語、英語、さらに日本語などの多言語が混在している。ここでは、国語文学としての「ドラマ」を上演するという、ドイツなど周辺諸国で演劇が伝統的にもっていた前提が放棄されている。
『ロブスターショップ』では、非オランダ語話者演じる難民や移民、物言わぬクローン、昏睡状態の子供といった、地位あるフランデレン男性を中心に語られる筋行動の周縁に位置付けられた人々が登場するが、彼らの声、および彼らとの共鳴を焦点化する上で、ポストドラマ的な演出が効果的に用いられている。本発表では、筋行動を構成する言語を語れぬことでそこから疎外される者たちを前景化するポストドラマ的手法の例を提示し、その意義とさらなる課題について考察したい。
針貝真理子
2016年ベルリン自由大学演劇学科博士課程修了。慶應義塾大学他非常勤講師。専門は日欧の現代演劇における「声」の演出分析と聴覚空間論を中心とする演劇美学。現在、越境演劇論や公共圏としての劇場空間についても研究を進めている。
著書:Ortlose Stimmen. Theaterinszenierungen von Masataka Matsuda, Robert Wilson, Jossi Wieler und Jan Lauwers, Bielefeld, transcript, 2018.(印刷中)
発表4 鈴木美穂
「イギリスにおけるポストドラマ的演劇の状況:『登場人物』をめぐって」
2006年『ポストドラマ演劇』が英訳されて以来、「ポストドラマ演劇」という用語は英語圏、特に現代イギリスの作品が論じられる際にも適用されてきた。サラ・ケイン、マーティン・クリンプ、ティム・クローチなどがポストドラマ的劇作家と見なされ、中でもクリンプの『彼女の生についての試み』、ケインの『4.48サイコシス』は英語圏における代表的なポストドラマ的作品としてしばしば名前が挙げられる。この二つの作品に共通するのは、テクストに役名の記載がないことである。レーマンはこういった戯曲を「もはやドラマ的ではないテクスト」と呼び、このようなテクストにおいては登場人物の対話や劇の筋は消え「言葉の自律化」が起こっているという。「言葉の自律化」とは、これまで人物に属する台詞としてのみ機能してきた戯曲の言葉の変容を示す重要な指摘である。しかし役名の記載がないテクスト及びその上演には、本当に「登場人物」が存在しないのだろうか。役名を記載しないということは、テクストの解釈、俳優が発する言葉と俳優との関係性など、演劇の上演を構成するさまざまな要素に揺さぶりをかける試みである。近年イギリスでは役名の記載のない戯曲が多く書かれており、『ポストドラマ演劇』の出版から約20年を経た今、こういったテクストがどのような演劇を目指したものなのかをより丁寧に見ていく必要があるだろう。本発表ではキャリル・チャーチルの『7人のユダヤ人の子どもたち』(2009)と『ラブ・アンド・インフォメーション』(2012)における登場人物のあり方を分析することを通してこの問題について考えたい。
鈴木美穂
早稲田大学大学院文学研究科芸術学(演劇映像)専攻博士後期課程単位取得退学。University of Essex, Department of Literature, Film, and Theatre Studies, MA in Literature修了。早稲田大学演劇博物館招聘研究員。東京工業大学、明治大学非常勤講師。専門はイギリス現代演劇、キャリル・チャーチル研究。論文に「憑依のダイナミクス―演劇論としてのキャリル・チャーチル『小鳥が口一杯』」(『西洋比較演劇研究』、2015年)、「キャリル・チャーチルの『フェン』における身体をめぐって―ダブリングという観点から」(『日本演劇学会紀要』、2013年)など。
発表5 高橋慎也
「ポストドラマ演劇の観点から照射する現代日本演劇―岡田利規の戯曲・上演を例として―」
レーマン著『ポストドラマ演劇』は、1990年代以降の日本演劇を理論的に記述しようとする際に、主として二つの利点を持つ。一点目はヨーロッパ演劇と日本演劇に共通する要素を共通の理論や術語に依拠して記述することが可能となることによって、日欧演劇の同時代性を指摘し、日欧の演劇創作者の交流と研究者の交流を促進できることである。二点目は『ポストドラマ演劇』には記述されていない上演例や理論的視点を確認することによって、現代日本演劇を解釈するための新たな理論を構築することができることである。今回の発表ではドイツを中心にヨーロッパ各地で高い評価を得てきた岡田利規の舞台上演を例として、これら二点について述べていきたい。一点目の例としては言葉と身体表現のズレから生じる「統合の回避」(『ポストドラマ演劇』訳書105頁)、言葉と身体表現の持つ記号としての多義性と物質としての多様性から生じる「並列/非ヒエラルヒー」(110頁)、パフォーマンス性に対するアフォーマンス性(334頁)などを指摘したい。これは岡田が『遡行』の中でキーワードとして使用している「並置」(41頁)、日常的な言葉と身体のノイズ(105頁)、レイヤー(28頁)、イメージ(194頁)という用語を「ポストドラマ演劇」の観点から解釈する際に有効である。二点目の例としては岡田の指摘する「幽霊」(165頁)としての俳優身体である。これは能や古典における霊媒としての日本の古典演劇の身体観を現代演劇に継承したものと解釈することができる。
高橋慎也
中央大学文学部教授。専門はドイツ演劇、日独比較演劇。特に1990年代以降のポストドラマ演劇研究、ドイツ演劇システム研究、岡田利規研究。論文:「現代ドイツにおける『ハムレット』受容とポストドラマ演劇 : 『ハムレット』上演データ分析による受容動向」(中央大学紀要. 言語・文学・文化 116)。「近年のドイツ演劇上演データ分析 : ドラマ演劇からポストドラマ演劇への転換」(中央大学ドイツ文化 70)

深まり行く秋、久々の研究例会です。どうぞ多数お集まりくださいますようお願いします。今回は時間がふだんと異なります。会場も最近よく使う3号館ではなく奥まった建物となります。不便をおかけします。
日時 平成29年10月21日(土) 13:30~18:20
場所 成城大学5号館 会議室(1F)
*キャンパスマップ①の建物です。⑤は違います。使いにくいマップで申し訳ありません。
http://www.seijo.ac.jp/about/map/
中庭を通り、7号館=③の前を通り過ぎてどん詰まりまで進み、右サイドになります。
1. 「西洋演劇論アンソロジー」(仮称)「執筆に関する意見交換会」 13:30~15:00
2. 研究発表 15:10~18:20
宮川 麻里子「舞踏のテクスト――大野一雄『睡蓮』創作メモの分析を中心に」
井上 優「獅子文六(岩田豊雄)の身体観――『青春怪談』(1954)に見る不安定な身体」
発表要旨・発表者プロフィール
■研究発表1 宮川 麻里子「舞踏のテクスト――大野一雄『睡蓮』創作メモの分析を中心に」
言葉によって構築されたイメージは、どのように身体を動かすのだろうか。また、舞踏家によって書かれた言葉から、彼が志向した運動や踊りを見出すことができるのだろうか。舞踏家・大野一雄について論じる際、上記の問題点は避けて通れない。これまで、大野は即興を大事にし、舞台上で自由に「魂の踊り」を舞うと形容されることが多かった。しかし1977年以降、レパートリーとなっていく「作品」を制作した際には、それを実現するために膨大な言葉を書いたメモを残している。本発表はこのメモを中心に分析し、言葉やイメージを書き付ける過程がどのように舞台の動きに反映されているのか、言葉のなかにどのような「踊り」を見出せるのか、迫ってみたい。
大野のこの創作メモは、デコード可能な記号で書くノーテーションシステムとは異なる。あるいは、言葉によって身体を変容させることを目指した、土方巽による「舞踏譜」との類似点は見出せるものの、他者への伝達という視点は大きく異なっている。発表者はこれまで『ラ・アルヘンチーナ頌』(1977)、『わたしのお母さん』(1981)を例に、記憶が様々な文章の引用によって補填されていくさまや、海外公演に伴う変化、モダンダンスの影響や土方巽の言葉による振付の痕跡を指摘してきた。本発表では土方の死後に制作された『睡蓮』(1987)を例に、大野が探究した動きに接近する。その手がかりとなる先行研究として、ジュリー・ペランによるシモーヌ・フォルティのテクスト分析があげられる(« Une lecture kinésique du paysage dans les écrits de la chorégraphe Simone Forti »)。彼女はダンサーの主体や動きの生成においてエクリチュールが担う役割を検討している。こうした議論を参照しつつ、大野が『睡蓮』で目指した踊りを、「アンフォルム」と関連付けながら考えていきたい。
宮川麻里子(みやがわ・まりこ)
東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得満期退学。開智国際非常勤講師。大野一雄の舞踏、とりわけ創作メモと動きの関連を中心に研究を行う。その他、『シアターアーツ』等に舞台批評も執筆。
■研究発表2 井上 優「獅子文六(岩田豊雄)の身体観――『青春怪談』(1954)に見る不安定な身体」
本発表は、文学座の創設者のひとりである岩田豊雄が獅子文六のペンネームで1954年読売新聞紙上に発表した『青春怪談』に見られる、彼の身体観を考察することを目的とする。岩田は、演出家として文学座に関わってきたが、創作活動としては小説執筆が中心で、戯曲執筆はほとんど行ってはこなかった。だが、娯楽作品を専らとし、一見演劇からは遠いように思われる彼の小説も、丹念に読み解いていけば、そこに岩田自身の演劇観・演劇人としての立ち位置が見て取れる。その観点から、改めてこの『青春怪談』を考察すると、この小説には、当時は意識されることがほとんどなかったであろう、舞台に立つ者の身体をめぐるアクチュアルな考察が浮上する。
この『青春怪談』は、東京のバレエ団に所属する千春とその婚約者慎一とを主人公とし、その周辺人物を巻き込んだドタバタ騒動を描く娯楽作である。だが、一見呑気な物語の展開の中で描かれるのは、精神的・身体的不安からバレエの演技の安定を欠くようになっていく主人公千春の姿である。しかも、バレエ団という背景に通常なら期待されるであろうダンサーとしての自己実現の物語は、ここにはない。描かれるのは、それぞれ、「男性性」「女性性」が大幅に希薄である主人公二人が、生物学的な性と内面的な性のかい離の可能性を憂慮しながら、自分たちのジェンダーを確認する作業である。今日であれば、パフォーマティヴなジェンダーの構築ともいうべき視点が、この時期に導入されているとも言えよう。設定の卓越性とテーマの今日性と、その両方の観点から見ても、この作品の先見性は、評価すべきであろう。
バレエ団という設定の背景には岩田豊雄の滞仏時(1922-25)のバレエ・リュス体験があることは容易に推測されるが、それ以上に、ここには岩田の身体観・演技観が色濃く表れているように思われる。その観点からこの作品を改めて読み解き、岩田豊雄の身体間を確認していきたい。
井上優(いのうえ・まさる)
明治大学文学部准教授。専門分野は演劇学、西洋演劇史。特にシェイクスピアを中心とする禁断の演劇の表現モードの変遷を研究。近年は演劇人としての岩田豊雄の業績の再評価を複数の機会で行ってきている。
訳書にラッセル・ジャクソン『シェイクスピア映画論』(共訳、開文社出版、2004年)、共著書に『演劇の課題』『演劇の課題2』(共著、三恵社、2011年および2015年)、『シェイクスピアと日本』(編著、風間書房、2015年)など。
*例会終了後、懇親会を行います。恐縮ですが、参加可能な方はあらかじめご連絡いただけますと幸いです。
(当日は他大学との合同運動会のため使用できるスペースが限られているため、できればどこか予約したいと思います)
連絡先:山下 y3yamash@seijo.ac.jp

本会の記念すべき企画へのスプリングボードです。どうぞ多数、ご参加ください。
日時 平成29年7月29日(土) 14:00~18:00
場所 成城大学3号館312教室
http://www.seijo.ac.jp/access/index.html
3号館は、正門から中庭に進んで左側の建物です。
■「西洋演劇論アンソロジー」(仮称):構想発表
発言者:
全体構想・・・山下純照/ 英語部門・・・小菅隼人・安田比呂志・井上優・松田智穂子・山下純照/ ドイツ語部門・・・小林英起子・新沼智之・萩原健・山下純照/ フランス語部門・・・萩原芳子・奥香織/ その他の言語部門・・・未定
■趣旨
日本演劇学会分科会「西洋比較演劇研究会」は来年2018年に30周年を迎えます。記念事業の一環として、ギリシャ・ローマから西欧近代をへて20世紀までを扱う「西洋演劇論」のアンソロジーを出版することになりました。演劇史の骨格をなす古典的なテクスト群をはじめ、最近の歴史を画した新しい理論までを扱い、抜粋箇所を厳選し、基本的に原典にもとづいて新訳を作成した上で、それぞれの文脈を解説する文章をつけることを想定しています。学部・大学院等の教育研究機関での、演劇概論や西洋演劇通史といった授業での教科書または副読本に使えて、学生・研究者が論文作成にあたって参照し、かつ引用元にできる資料集とします。一冊で20世紀までの西洋演劇思想史がほぼカバーできる、歴史に残る文献を目指します。
方針としては、過去の類書(『世界演劇論事典』評論社、1979年)との差異化を図ります。すなわち「底本などの書誌情報を明記する」「訳者を明記する」「ブレヒト、アルトー、エイベル、シェクナー、レーマンら20世紀の演劇論をカバーする」「研究の中で新たに光が当たった対象を取り上げる」などがあげられます。
とりあげる原著者は70人程度になる見込みです。本の構成は時代別になることが予想されますが、今回の構想発表会では、各言語部門別に、とりあげる予定の論者・テクストとその担当予定者について現時点の見込みを説明します。解説記事に書くべきポイントなどについて、時間の許す限り意見交換したいと思います。
例会終了後、懇親会を行います。

本年度第2回例会を下記の日程で開催します。奮ってご参加ください。
【会場が成城大学ではなく明治大学に変更となります。ご注意ください】
5月20日(土) 14時~18時
明治大学駿河台校舎グローバルフロント3階403N教室
※御茶ノ水駅に一番近い校舎の3階になります。4階ではありません。ご注意ください。
※アクセスは以下を参照下さい。
http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html
【研究発表1】
ミュージカル『エリーザベト』の日本での翻案をめぐって
田中里奈(明治大学大学院)
【研究発表2】
マックス・ラインハルトのオペレッタ演出—新たな祝祭劇との接点
大林のり子(明治大学)
【研究発表1 発表要旨】
ミュージカル『エリーザベト』の日本での翻案をめぐって
今日、オーストリア・ヴィーン発のミュージカルが世界的に浸透している。このいわゆるヴィーン・ミュージカルは、第二次世界大戦後のヴィーンで、アメリカで成立したミュージカルをローカライズすることで誕生した。それが1990年代以降、第三国へ輸出され、さらに、輸出先の現地で繰り返しローカライズされている。つまり、ヴィーン・ミュージカルの場合、一つの作品の中に、上演されてきた/される各地域での翻案が多層的に蓄積されている*。
このような手法で展開されているヴィーン・ミュージカルは、いまや世界中(2017年4月現在、16言語21か国)に広まっており、1996年以来は特に日本で繰り返し上演されている。なかでも『エリーザベト(Elisabeth)』の日本翻案である、宝塚歌劇『エリザベート ―愛と死の輪舞―』(1996年初演)および東宝『エリザベート』(2000年初演)はほぼ毎年再演され、その都度演出が改訂されている。
これら日本版の現在までの推移をみると、宝塚版がスター俳優を軸としたエンタテインメント性の強いレヴューに仕立てられたのに対し、東宝版は一場面ごとの要素を徐々に増していき、独自の発展を遂げていった。とはいえ、いずれもいわば要素過多の「オーバー」エンタテインメントと言え、ここでは、過去の上演にまつわる記憶を有した観客が現行の上演の見どころを取捨選択し解釈する、という観劇体験が半ば自明視されている。そしてドイツ語圏と日本における上演研究史に照らし合わせたとき、それはいわば「イメージの洪水」(フィル 2008)であり、また種々雑多な演目の数々がひとつの公演の中で供される「演芸」(神山 2006: 17)としても位置づけられうる。
*ヴィーン・ミュージカル前史については、『西洋比較演劇研究』, No. 16掲載の拙研究ノート「第二次世界大戦後のヴィーンにおけるミュージカル受容史(1956-1990)-フォルクスオーパーおよびテアーター・アン・デア・ヴィーンを中心に-」をご参照ください。
[参照文献]
フィル・ズザンネ(2008)「脱構築と映像洪水の間から生まれる創造的ビジョン:ポストモダン演劇美学の自由」『国際文化学研究:神戸大学大学院国際文化学研究科紀要』32: 99-126.
神山彰(2006)『近代演劇の来歴 歌舞伎の一身二生』森話社.
田中里奈(たなか りな)
明治大学大学院国際日本学研究科博士後期課程。専門はドイツ語圏・日本のミュージカル、文化受容論。日英および日独翻訳・通訳としても活動。業績では、本研究会紀要16に研究ノート「第二次世界大戦後のヴィーンにおけるミュージカル受容史(1956-1990)」、論文に“Musicals in Post-Globalization: the Case of ‘Ever-Growing’ Musicals from Vienna via Japan” (Revisions, A Multilingual Open Access Journal on Culture in East Asia, 2017)ほか。
【研究発表2 発表要旨】
マックス・ラインハルトのオペレッタ演出—新たな祝祭劇との接点
本発表では、1900年代から1930年代までの激動の時期の演出家マックス・ラインハルト(1843-1943)の仕事を、オペレッタ演出という軸で見直すことにより、当時の演劇および劇場の役割が変容していく過程をあらためて再考する。
ラインハルトの舞台演出における音楽や舞踊などの要素は、彼が何度も新演出を重ねた『夏の夜の夢』にも少なからずその特徴を見ることができるだろう。また、彼の名を国際的に有名にした演目には、欧州諸国の都市を巡った大劇場演出の『オイディプス』、英語圏においての言語の枠に縛られないパントマイム劇『ズムルン』や『奇蹟』などが挙げられる。特にパントマイム劇においては音楽や舞踊の役割はより重要なものとなり、言葉よりも視覚と聴覚に働きかけるスペクタクル演出が彼の代名詞ともなっていく。その背景には1910年代前後のゲオルク・フックスとの関わり、あるいは1919年から始まるザルツブルク音楽祭の企画など、ラインハルトと当時の協働者たちの祝祭的な演劇への志向があったことは言うまでもない。
一方で、ラインハルトや協働者にはオーストリア出身者が多く集い、彼らの活動の背景には、19世紀後半のウィーンの街の空気が少なからず感じられる。時にそれは舞台演出において戦略的に、そのものではなく何かと折衷した形で取り入れられ、色々な祝祭的場の創出に貢献するのだが、戦争を経験した後の世代にとっては、幾分懐古的な色合いを帯びた甘ったるいものとなっていく。
今回注目するラインハルトのオペレッタ演出については、オペレッタの歴史あるいは映画との関係において話題にされることが少なからずあるようだが、新奇性という点を重視する演劇史的な観点からは、幾分保守的な演目と見えて、あまり取り上げられることのないものかもしれない。しかし改めて見直してみると、そこには彼が目指した祝祭劇の別の姿が浮かび上がってくるように思われる。
大林のり子(おおばやし のりこ)
明治大学文学部准教授。演劇学・演劇史。20世紀前半の欧米演劇における協働製作について、主に演出家マックス・ラインハルトの国際的な場における協働製作に注目し、近年は両大戦間の複雑な時代における演劇のあり方を再考している。論文には『ラインハルト演出『強制結婚』とモリエールのコメディ・バレエ』(『演劇学論叢』13号、大阪大学大学院演劇学研究室紀要、2013年) 、『第一次世界大戦期ベルリン・ドイツ劇場のレパートリーにみる民衆劇-ライムント喜劇『ラッペルコップ』演出-』(『演劇学論叢』14号、大阪大学大学院演劇学研究室紀要、2015年)など。

日時 2017年4月15日(土)午後2時~5時
場所 成城大学3号館1F 311教室
http://www.seijo.ac.jp/access/index.html
3号館は、正門から中庭に進んで左側の建物です。
総会 午後2時~3時
2016年度活動および会計報告、2017年度計画および予算などが議題になります。
例会 午後3時15分~5時(講演・質疑応答)
講演 本杉省三「劇場の近代化:その進化と退化」
*終了後、懇親会があります。どうぞご参会ください。
(講演要旨)
私たちは、前の時代よりも今の時代の方が、更には次の時代の方がより優れたものになっている、複雑なものになっている、発展して行くと思っている。おかげで生活が豊かになる、快適に過ごせると思っている。そうした社会に技術が貢献している。劇場の演出技術も、古くから舞台機構・照明・音響などさまざま工夫が考案され、より素早く、より安全で、より効果的なものが誕生してきた。おかげで季節や天候・時間に左右されず意のままになる場を獲得することが出来た。その意味で劇場空間は進化していると言えるかも知れない。そうした建築や劇場機能の改善ために私自身も研究を行ってきた。
しかし、進化は同時に退化と共にある。ある機能が向上して行くことで、それまで有していた機能が退化して行く。あるいは、進化がある時点で停止し形式化される。空間の形式化は、社会の制度と結びついてより強固なものになって行く。そうした用心深さは、多額な費用を要する建築には確かに必要だ。しかし、それが劇場空間の創造力を削ぐものになって欲しくない。ある時期発展的と見られていた物事が、時間的経過とともに形式化し退化して行く。その結果、当初の意味が失われてしまう。そうした反省を込めて劇場建築を振り返ってみたい。
講演者プロフィール 本杉 省三(もとすぎ しょうぞう)
神奈川県横浜市生まれ。日本大学理工学部特任教授(工学博士)。1974年日本大学大学院修了後、同大学助手、ベルリン自由大学演劇研究所留学(DAAD奨学生)、同大学教授等を経て2016年より現職。劇場・ホールに関する様々な研究活動を行うと共に、シアターコクーン、新国立劇場、愛知芸術文化センター、新潟りゅうとぴあ、つくばカピオ、静岡グランシップ、ビックハート出雲、クレアこうのす、Kunstlinie Almere、まつもと市民芸術館、サントミューゼ上田、台中國家歌劇院等の計画・設計に携わる。主な著書は、「劇場空間の源流」、「劇場・コンサートホール」、「地域に生きる劇場」、「建築設計資料集成/展示・芸能」等。

会員の皆様、今年もお世話になりました。
来年早々、本年度最後の例会を行います。ふるってご参集ください。
日時 2017年1月7日(土) 14:00~18:00
場所 成城大学 3号館1F 311教室
音楽劇シンポジウム:「音楽劇」とは何か――演劇研究からのアプローチの可能性
発表1:奥香織「オペラ=コミックとは何か― 18・19世紀パリにおける存在意義を考える」
発表2:森佳子「演劇史のなかのオペラ―ポスト・ヴァーグナーを例に」
発表3:藤原麻優子「言葉・音楽・ダンス―ミュージカルにおける「統合」と劇作術の可能性」
発表4:萩原健「ハイナー・ゲッベルスの〈Music Theatre〉」
コメンテーター:丸本隆
全体要旨:「音楽劇」とは、ドラマの進行において音楽が重要な役割を果たす演劇全てを含み、オペラ以外にも様々な形式が考えられる。しかしながらその定義は明確ではなく、また演劇学の観点からの研究も十分であるとは言い難い。本シンポジウムでは、主に西洋の「音楽劇」の多様なあり方について考察し、今後の演劇研究における新たな可能性を探ることを目的とする。
発表要旨・発表者プロフィール
発表1 奥香織「オペラ=コミックとは何か― 18・19世紀パリにおける存在意義を考える」
オペラ=コミックとは何か、という問いに答えることは容易ではない。歌と台詞が混在する歌劇の一種(この種の作品を上演する劇場名でもある)という定義が可能ではあるが、時代を経る中で演劇的要素が強い作品からオペラに近いものへと重心が移動し、また内容も喜劇的なものから感傷的なものへと移行する。この変容は、ジャンルとしての発展と独自性を求めたゆえに生じたものであるが、次第にオペラとの差異は不明瞭となり、最終的にオペラ=コミック作品は創作されなくなる。
ジャンルとして永続し得なかったこと、大衆的・商業的な側面が比較的強いことなどから、オペラ=コミックは演劇史や音楽史において軽視されがちである。しかし同時代の受容に目を向けると、この音楽劇は「すぐれてフランス的」(19世紀初頭)と評され、またマスネの《マノン》が示唆するように、結果としてナショナル・アイデンティティを表象するものともなっている。本発表では、これらの点に注目し、語の定義ではなく、オペラ=コミックがその形式/空間ゆえに18・19世紀のパリで何を成し得たのか、特異な「混成ジャンル」としての存在意義と重要性について検討したい。
奥香織(おく かおり)
パリ第4大学博士課程修了。博士(フランス文学・文明)。現在、日本学術振興会特別研究員、明治大学ほか非常勤講師。専門はフランスの舞台芸術、日仏演劇交流。現在の主な研究対象は17-19世紀フランスの舞台実践、演劇美学。論文:「初期オペラ=コミックのドラマトゥルギー―権力、観客との関係性をめぐって―」(『演劇映像』第57号、早稲田大学演劇映像学会、2016)、「感覚の知を表象する場としてのマリヴォー劇―「恋の不意打ち」の構造と機能をめぐって―」(『総合社会科学研究』第3集8号/28号、総合社会科学会、2016)など。
発表2 森佳子「演劇史のなかのオペラ―ポスト・ヴァーグナーを例に」
19世紀のオペラにおいてドラマと音楽を一つにする試みは、18世紀イタリアのナポリ派で完成した形式(ナンバー・オペラ)の脱却から始まり、ヴァーグナーで頂点に達したと言われる。具体的には、まず1830年頃にフランスで「グランド・オペラ」という総合芸術の形式が現れ、その後ヴァーグナーはライトモティーフの手法でドラマと音楽の新しい関係性を提示し、同時代の作曲家の大部分がその影響下にあったことは確かだろう。
しかしオペラ研究において、「ドラマあるいは演劇と音楽」に関する問題は、むろんそれらに限らず、普遍的なものである。発表では、ポスト・ヴァーグナーの流れをくみ、オペラを演劇として位置付ける過程で生まれた「自然主義的オペラ」(ブリュノー、マスネ、プッチーニ等。ヴェリズモも含む)を例に取り上げる。そのうえで、「演劇史におけるオペラの意義」が時代とともにどのように変化して来たのかを模索してみたい。
森佳子(もり よしこ)
日本大学他非常勤講師、早稲田大学オペラ/音楽劇研究所招聘研究員。博士(文学)。フランスを中心としたオペラ、音楽劇の研究を行う。主な著書に『笑うオペラ』『クラシックと日本人』(共に青弓社)、『オッフェンバックと大衆芸術ーパリジャンが愛した夢幻オペレッタ』(早稲田大学出版部)など。
発表3 藤原麻優子「言葉・音楽・ダンス―ミュージカルにおける「統合」と劇作術の可能性」
ミュージカルは台詞・歌・ダンスを用いるジャンルであり、言葉と音楽とダンスが「ひとつになっている」と説明される。この考えかた、すなわち言葉と音楽とダンスの「統合」は、1940年代にリチャード・ロジャースとオスカー・ハマースタイン2世が発表したミュージカル・プレイによって大きく打ちだされ、1940~1960年代のミュージカル「黄金期」を生みだすことになった。多様な形式のミュージカルが作られる現在でも、実践と批評の双方において、言葉・音楽・ダンスの統合はミュージカルにおけるひとまずの基本だといえるだろう。
しかし、言葉と音楽とダンスが「統合されている」とは、いったいどのような状態なのだろうか。近年のミュージカル研究は、この「統合」という概念を疑い、あるいは捉えなおすことで大きな転換を迎えている。発表では、ミュージカルの上演史・研究史での「統合」の変遷と、言葉・音楽・ダンスを用いるジャンルであるミュージカルの特徴について考えたい。
藤原麻優子(ふじわら まゆこ)
早稲田大学演劇博物館招聘研究員。博士(文学)。専門はミュージカル、音楽劇。最近の論文に「「これはどんなミュージカルなの?」--メタミュージカル試論」(『西洋比較演劇研究』15-1)、批評に「「なんで歌っちゃったんだろう?」2.5次元ミュージカルとミュージカルの境界」(『ユリイカ』2015年4月増刊号)。
発表4 萩原健「ハイナー・ゲッベルスの〈Music Theatre〉」
「音楽劇」はおそらく、「音楽が伴う劇」「音楽が前面に立つ劇」と一般的には解されるが、「音楽化された劇」「音楽による劇」とも解しうる。そのように考えると、ドイツ語圏の場合、代表例として舞台作曲家出身のスイスの演出家、クリストフ・マルターラーの仕事が挙がるが、本発表ではもうひとつのラディカルな例として、ドイツの作曲家・演出家ハイナー・ゲッベルスの一連の作品群、特に〈Music Theatre〉の名で括られるそれらに注目する。
ゲッベルスの作品は、これまで日本公演はあった一方、日本語による研究ではまったくと言っていいほど追究されてこなかった。彼が1980年代から現在まで、繰り返し発表している、演奏会、演劇、サウンド・インスタレーション、あるいはその総合とも形容しうる、ジャンル分けのきわめて困難な一連の仕事について概観し、現代の音楽劇が示しうる多様な姿について、そしてそれを研究対象とした場合のアプローチについて考えたい。
萩原 健(はぎわら けん)
明治大学国際日本学部教授。現代ドイツ演劇および関連する日本の演劇。音楽劇関連の業績では、共著に『ステージ・ショウの時代』(2015)、『オペラ学の地平 総合舞台芸術への学際的アプローチ 2』(2009)、論文に「発酵する人々 マルターラー演出『巨大なるブッツバッハ村』が示す現代社会の悲哀」『演劇学論集 日本演劇学会紀要』57 (2013) ほか。
コメンテータープロフィール
丸本隆(まるもと たかし)
早稲田大学名誉教授。研究対象:ドイツ演劇、演劇制度、日欧比較演劇、(現在の重点は)オペラ/音楽劇。早稲田大学演劇博物館COE、オペラ/音楽劇研究所でオペラ研究プロジェクトを主宰(2002-2015)。関連著作:「ヴェルディとリソルジメント・オペラ」(『演劇学論集』日本演劇学会2014)。“A Song for Kingdoms: Takarazuka's Attempt to Adapt the Opera Aida.” Geilhorn, B., et al., eds. Enacting Culture. Munich, 2012。「”劇場監督”制度からみたドイツの公共劇場」(伊藤他編『公共劇場の10年』美学出版 2010)。『オペラ学の地平』(共編著、彩流社 2009)。“Opera Culture in Japan” Japan Spotlight. 2007。『演劇学のキーワーズ』(共編著、ぺりかん社 2007)。『初期オペラの研究』(編著、彩流社 2005)。„Das Frauen-Ensemble Takarazuka, seine Tradition und Gegenwart“(『演劇センター紀要』早稲田大学 2005)。『オペラの18世紀』(編著、彩流社 2003)。

たいへん、ご案内が遅れて恐縮です。すでに7月の総会および9月例会のさいに日時ともお知らせしましたように、10月は英語による例会で、ドイツ語圏演劇についてのミニ・シンポジウムとなります。ミュンヒェン大学から気鋭の演劇学者を迎えての集会となりますので、皆様ぜひともご参加いただけますよう。
日時 2016年10月15日 14:00~18:00
場所 成城大学7号館1F 716教室
シンポジウム(仮題) Aspects of Contemporary German-Language Theatre
発表
(1) Shinya Takahashi, "Theater System and Theater History in Germany since 1960's: Turn from Dramatic to Postdramatic Theater"
(1960年代以降のドイツの演劇システムと演劇史 - ドラマ演劇からポストドラマ演劇への転換
高橋慎也)
(2) Andreas Englhart, "Political Theatre Today? Postdramatic Theatre and/or New Realism in German-Language Contemporary Theatre"
(政治演劇はいま? ― ポストドラマ演劇と(あるいはそれとも)ドイツ語圏現代演劇における新リアリズム アンドレアス・エングルハルト)
(3) Yoshiteru Yamashita, "A 'Modoki' in the Contemporary German Theatre: Michael Thalheimer’s direction of Emilia- Galotti"
(現代ドイツ演劇における「もどき」 ― ミヒァエル・タールハイマーの『エミーリア・ガロッティ』演出 山下純照)
発表者紹介
高橋慎也(たかはし しんや)
中央大学文学部教授。専門はドイツ演劇、日独比較演劇。特に1990年代以降のポストドラマ演劇研究、ドイツ演劇システム研究、岡田利規研究。論文:「現代ドイツにおける『ハムレット』受容とポストドラマ演劇 : 『ハムレット』上演データ分析による受容動向」(中央大学紀要. 言語・文学・文化 116)。「近年のドイツ演劇上演データ分析 : ドラマ演劇からポストドラマ演劇への転換」(中央大学ドイツ文化 70)
アンドレアス・エングルハルト (Dr. Andreas Englhart)
ミュンヘン大学文化学部演劇学科講師。専門領域は19世紀から現代にいたるドイツ語圏演劇。バイエルン州立演劇アカデミー講師、俳優養成学校講師も兼任。ドイツ現代演劇における戯曲の役割を重視する立場から研究を行っている。ボート・シュトラウスに関する論文によって博士号を取得。ミュンヘン大学で教授資格を取得。主な著書:Einführung in die moderne Theaterwissenschaft (『現代演劇学入門』、共著), Einführung in das Werk Friedrich Schillers(『フリードリッヒ・シラー作品入門』), Das Theater der Gegenwart (『現在の演劇』), Junge Stücke. Junge Autorinnen und Autoren im Gegenwartstheater『若手作家作品集 現代演劇の若手作家たち』
山下純照 Prof. Yoshiteru Yamashita
成城大学教授。大阪大学大学院にてガダマーの『真理と方法』で修士号。その後ドイツ及び日本の近現代劇及び上演の研究。フリードリヒ・シラー、ハインリッヒ・フォン・クライスト、ブレヒト/ミュラー、ジョージ・タボーリ、鈴木忠志、野田秀樹、宮城聰らについて論文がある。現在の関心は1) 記憶の演劇の諸テーマ、2) 日本の伝統的美的概念の近現代演劇解釈への応用。

風の気配に秋を感じるこの頃、みなさまいかがお過ごしですか。9月例会の案内を差し上げます。とても興味味深い題目がそろいました。ぜひ足をお運びください。
日時 2016年9月24日(土) 14:00~18:00
場所 成城大学 7号館723教室
研究発表
舘野太朗「ページェントの展開―「江の島縁起ページェント」を例に―」
松田智穂子「国民を創る、女性を創る―Jean Smallのモダン・パジェントNana Yah(1980)」
日比野啓「素人演劇運動の「間隙」としてのミュージカル:能代ミュージカルを例として」
発表要旨・発表者プロフィール
舘野太朗「ページェントの展開―「江の島縁起ページェント」を例に―」
坪内逍遥のページェント実践は、1921年10月2日に陸軍戸山学校で文化事業研究会によって上演された「熱海町の為のページェント」の試演にとどまり、上演計画の相次ぐ中止と実働機関たる文化事業研究会の解散によって挫折に至った。しかし、逍遥の弟子を自認する人びとは、その後も逍遥の構想を実現させようとしてきた。
鎌倉市腰越に住んでいた演劇学者の飯塚友一郎は、片瀬青年団から海開きの趣向のアイデアを求められ、ページェントの開催を提案し、1937年から1940年まで江の島でページェントが上演された。この「江の島縁起ページェント」では、当地の伝説をモチーフとしたストーリーが現地住民と飯塚の指導していた日本大学の学生らによって演じられ、龍の作り物を使った練り物行列を組み込むなどの見た目本位の演出が試みられた。また、飯塚は音楽に当地の祭り囃子を用いたり、江島神社の神職に口上を述べさせたりした。逍遥はページェント実践の方策として「既存の祭礼及びそれに類似の行事を根本的に改造して、十分に現代化する事」を提案しており、飯塚は土地にもとからある祭礼や藝能を再構成することで「現代」に相応しい「祭礼」を作ろうとしていたのではないだろうか。本発表では「江の島縁起ページェント」を中心に、逍遥の後継者たちが試みたページェント実践の可能性と限界を検討したい。
舘野太朗(たちの たろう) 地役者(立役・敵役)、研究者(民俗藝能・日本藝能史)。1985年生まれ。2009年、筑波大学第二学群日本語・日本文化学類卒業。2012年、筑波大学大学院人文社会科学研究科国際地域研究専攻修了。修士(国際学)。論文は「地芝居の現在とその課題」(『筑波大学地域研究』34、2013)が入手しやすい。
松田智穂子「国民を創る、女性を創る―Jean Smallのモダン・パジェントNana Yah(1980)」
1900-40年代に世界各地で上演され、一大ブームを巻き起こしたモダン・パジェントは、第二次大戦前後にラジオやテレビの普及を受けて急速に廃れた。しかしながら、英語圏カリブ海地域では、モダン・パジェントの形式とコンセプトを踏襲する作品の上演の例が散発的に見られた。形式的には、観客を巻き込む、あるいは参加させる野外歴史劇であり、コンセプトとしては、観客の参加により、コミュニティの一致団結を強く促すという極めて政治的・社会的意味合いでの効果を狙っていた。
ジャマイカでコミュニティ演劇のコンセプトに則って活動するSistren Theatre Collective(姉妹演劇集団)が上演したJean Small作Nana Yahもまた、このようなモダン・パジェントの一つだった。本劇団は、識字率の低い労働者階級の女性の教育を目的に、10名の女性教師(多くは労働者階級出身)が中心となって1977年にアマチュア活動を開始し、議論、稽古、上演のプロセスを通して、同階級の女性が直面する様々な社会問題―貧困、失業、家庭内暴力、教育、医療、犯罪など―をテーマに取り組んでいる。本発表ではまず、このような特色を持つ活動を行うシストレン演劇集団が、Nana Yah上演において、すでに下火となっていたモダン・パジェントという形式をあえて踏襲することでいかなる効果をあげたかを述べる。次に、このようなモダン・パジェントの基本的な特徴を押さえつつ、Nana yahには、さらに①カリブ性―Storytellerの伝統― ②女性の焦点を当てるという二つの特徴がさらに付け加えられている点を明らかにする。
松田智穂子(まつだ ちほこ) 専修大学准教授。現在、北米および英語圏カリブ海地域の黒人コミュニティにおけるモダン・パジェントの上演に関心を寄せている。「「凱旋のジャマイカ」(1937年) : モダン・パジェントに見る多人種・多民族」2015年『専修大学人文科学研究所月報』278号、65-78頁
日比野啓「素人演劇運動の「間隙」としてのミュージカル:能代ミュージカルを例として」
能代ミュージカルは秋田県能代市で一九八〇年から始まり、二〇一六年までに三十五回の公演を行ってきた、息の長い市民ミュージカルだ。土地の伝説や名所を題材にした市民参加型のミュージカルとしては、一九七六年から始まり、現在まで続く遠野物語ファンタジー(岩手県遠野市)が先行する。しかしこれは「市民劇」という括りのもとで台詞劇も上演してきたので、ミュージカルと銘打って音楽劇のみを上演し続けてきた組織としては能代ミュージカルが国内で最も長く続いていることになる。
本発表では、能代ミュージカルや遠野物語ファンタジーをはじめとする、日本各地のコミュニティ・シアターが音楽劇上演に取り組んできた数々の事例を紹介することで、一九七〇年代後半以降、「ミュージカル」上演に対する根強い情熱が各所に見られたことをまず確認する。次に、コミュニティ・シアターが「ミュージカル」上演を次々と手がけてきた理由として(1)オペラやオペレッタのような高尚文化ではなく、アメリカン・ミュージカルが喚起するミドル・ブラウな志向(その「舶来」趣味も含めて)が好まれたこと(2)一九三〇〜四〇年代、国民劇創出の気運の(何度目かの)高まりとともにその一環として「素人演劇」の重要性が唱えられた際のモデルとなっていた新劇が、七〇年代後半以降その権威を失ったこと(3)新劇の文学性・非演劇性への異議申し立てとして登場し、その多くは音楽劇でもあったアングラ・小劇場がその「難解さ」ゆえに新劇に取って代わる新たなモデルになり損なったこと(4)七〇年代後半以降、左翼運動の退潮とともに「うたごえ」運動の政治性がかえって際立つようになり、「声をあわせて歌う」ことで共同性を獲得する契機が他に求められていたこと、の四点を挙げる。コミュニティ・シアターによる「ミュージカル」上演とは、各地の演劇・文化活動の歴史において生じた空白を埋めるようにして出てきた運動であり、「中央」の動向、すなわち東京における供給と需要の関係が生み出した一九六〇年代中葉の第一次ミュージカル・ブームや、一九八〇年代前半の第二次ミュージカル・ブームとは無関係に生じた現象であることを示したい。最後に、参加型アートが提示する社会包摂の理念を批判したクレア・ビショップ『人工地獄』への再反論として、アートの両義性や社会とアートの緊張関係のような、ビショップが依拠するブルジョア的芸術観に組み込むことができないような素人演劇の意義について考える。カントが『判断力批判』で示した美と崇高の区別を手掛かりに、素人演劇がもたらす崇高(そして道徳的善)こそがその本来の意義なのだというのが発表者の主張である。
日比野啓(ひびの けい) 成蹊大学文学部教授。演劇史・演劇理論。現在の関心は日本近現代演劇と合衆国の音楽劇。年度末に刊行予定の編著『戦後ミュージカルの展開』(仮題・森話社)と『アメリカン・レイバー』(仮題・彩流社)をはじめとする原稿執筆とその準備に追われ、気の休まることのない日々を現在送っている。

何かと慌ただしく年に二度の「師走」があったかと思われるほどですが、そんなときこそ研究成果にひたる時間を確保していただきたく、ご案内します。(※文末に紀要投稿に関するお知らせがあります)
日時 2016年7月9日(土) 14:00~18:00
場所 成城大学 3号館312教室
研究発表
稲山玲「野田秀樹・潤色『真夏の夜の夢』における終末論的世界観」
星野高「東京のレヴュー1925 —1920年代ブロードウェイ・レヴューと日本の大衆演劇—」
発表要旨・発表者プロフィール
稲山玲「野田秀樹・潤色『真夏の夜の夢』における終末論的世界観」
野田秀樹は、1980年代後半~90年代初頭にかけてシェイクスピアの翻案作品を連続的に上演した。劇団・夢の遊眠社の解散直前、1992年8月に上演された『野田秀樹の真夏の夜の夢』(主催:東宝 会場:日生劇場)は、その最後を飾る作品である。
原作からの大きな改変点は、第一に舞台設定が日本に置き換えられている点、第二に悪魔メフィストフェレスが登場する点である。若者4人はそれぞれの板前、料亭の娘、煮方の娘に改変され、彼らが迷い込む森は富士の麓の「知られざる森」の麓に設定されている。その森に、パックになりすましたメフィストが侵入する。メフィストは負の感情を抱える人物と契約し、彼らが口にせず飲みこんだ呪いの言葉を糧に森を破滅に追い込もうとする。メフィストは森に「終末の危機」を持ちこむのである。
今回の発表では、この「終末論的世界観」に着目して本作の分析を試みる。当時、世紀末を目前に控えた日本では、『ノストラダムスの大予言』(五島勉 祥伝社 1973年)に代表される「終末」ブームが再び盛り上がりを見せていた。それはオカルトやアニメといったサブカルチャーの文脈で大衆的な興味と結び付き、膨大に消費されていた文化である。そうした社会的空気の中で、野田はシェイクスピア作品を日本に移入するにあたり「終末の危機」を付与し、またラストにおいてはその「終末の危機」に分かりやすい終わりもたらしてみせたのだ。本作の中で野田は「終末」をどのように描き出したか、また、「終末の危機」を打破するものとして何を打ち出したのか、明らかにしていきたい。
稲山玲(いなやま れい) 早稲田大学卒、明治大学大学院文学研究科・博士課程在籍中。研究テーマは野田秀樹を中心とした現代日本演劇。学会発表としてThe impact of Peter Brook’s A Midsummer Night’s Dream on the Japanese directors(IFTR 2014年)、『野田秀樹作『三代目、りちゃあど』における「国家元首」のイメージ形成』(日本演劇学会 2015年)他。
星野高「東京のレヴュー1925 —1920年代ブロードウェイ・レヴューと日本の大衆演劇—」
1920年代のブロードウェイ・レヴューと日本の大衆演劇との関係については、これまであまり論じられていない。本発表ではまず、1925年の松旭斎天勝の帝劇興行とブロードウェイ・レヴューとの結びつきを明らかにする。その上で、それに関連した二つの公演を取り上げて、1920年代の日本の大衆演劇におけるブロードウェイ・レヴューの影響を考察する。
1925年6月、東京の帝国劇場で奇術師・松旭斎天勝の「帰朝記念興行」が行われた。このとき公演の呼び物となったのが「ジャズ演奏およびジャズ・ダンス」と短い劇が連続する「寸劇」だった。このうち、ジャズ・ダンスとして上演された「サム・ボデー・ラヴス・ミイ」が、前年のブロードウェイ・レヴュー「ジョージ・ホワイトのスキャンダルズ1924」で上演され、ヒットした、ジョージ・ガーシュインの「Somebody Loves Me」であり、寸劇として演じられた「自働電話室」「或る倶楽部」「二つが一つ」が、それぞれやはり前年のブロードウェイ・レヴュー「パッシング・ショウ1924」のなかの「The Telephone」「Some Club」「Two in One」である可能性が高い。天勝は、同時代的に、1920年代のブロードウェイ・レヴューを日本の舞台に持ち込んでいた。
こうした天勝とブロードウェイ・レヴューとの結びつきを踏まえて、当時の東京の演劇界を見わたすと、次の二つの公演が注目される。一つは同じ帝国劇場で、天勝の公演に続けて上演された益田太郎冠者の『高速度喜劇』であり、もう一つはやはり同じ1925年4月に浅草の観音劇場で行われた「高田雅夫・原せい子帰朝披露公演」の中の『ミュジカル・レヴュ』である。
このあと、1920年代を通じて、天勝と高田、太郎冠者(および帝国劇場)と高田は、共に仕事をしていくことになる。
1925年の三つの公演を起点として、彼らが1920年代に示した活動の軌跡は、ブロードウェイ・レヴューに触発されたひとまとまりの動きとして、捉えられるのではないだろうか。
星野高(ほしの たかし) 近代日本演劇史研究者。明治大学大学院文学研究科演劇学専攻博士後期課程単位取得満期退学。2011〜13年、早稲田大学演劇博物館助手。現在、早稲田大学演劇博物館招聘研究員。論文:「〈銀座モダン〉の余香—女優森律子の生人形と三世安本亀八−−」(『日本人形玩具学会誌:かたち・あそび』第26号、日本人形玩具学会、2016)、「帝劇の時代—ヴァラエティ・シアターとしての大正期帝国劇場−−」(『商業演劇の光芒』所収、森話社、2014)。
★お知らせ★
分科会紀要『西洋比較演劇研究』への投稿を受け付け中です(投稿規定・執筆要領については下記、分科会HPをご覧ください)。
昨年度(2015年度)より、「論文」と「研究ノート」の二つの枠が設けられました。次号の投稿締切日は「2016年11月1日」です。過去の例会で発表された方を始め、多数の方々からの投稿をお待ちしています。
http://comparativetheatre.org/?page_id=11

日時 2016年5月14日(土) 14:00~18:00
場所 成城大学 3号館312教室
研究発表
杉山博昭「聖史劇の宗教画、宗教画の聖史劇
― ルネサンス期イタリアの眼差しが媒介する照応関係」
片山幹生「中世フランス演劇とは何か?
― フランス演劇史における中世の位置づけとその可能性について」
発表要旨・発表者プロフィール
杉山博昭「聖史劇の宗教画、宗教画の聖史劇
― ルネサンス期イタリアの眼差しが媒介する照応関係」
古典劇の再生は、演劇史のみならず文化史における重要事項として、ルネサンスという運動の中心に位置したとみなされる。たしかに15世紀末のイタリア各地の宮廷において、古典劇は繰り返し上演されていた。じつは、このめざましい人文主義的成果に隠れて、ひそかに、しかし急激に制作機会を減らしていったもうひとつの演劇が存在する。それが聖史劇le sacre rappresentazioniである。とりわけ一度に3万人以上の見物客を集めた記録も伝わるフィレンツェ聖史劇は、出版ブーム到来前夜、15世紀ヨーロッパ最大のメディアと呼ぶことも可能だろう。
他方、文化的、宗教的、政治的に興味深い考察対象であるにもかかわらず、聖史劇研究はながらく停滞を余儀なくされてきた。それはおもに資料的限界によるものである。その限界にたいして、発表者は文献学や社会史研究の方法論を参照しつつ、さらに同時代の図像資料に注目することで聖史劇再構成の展望を模索してきた。これは絵画と演劇を一方向の影響関係に縛りつける試みではなく、双方向の照応関係のもとに捉える試みである。つまり問題は「聖史劇の見物客が宗教画の鑑賞者になるとき、もしくはその逆のケースにおいて、いかに受容者の経験は想定されるのだろうか」ということになる。
この問題を考えるべく、本発表では「受胎告知」「キリストの昇天」「聖霊降臨」という3つの主題に注目し、聖堂内でおおがかりな舞台装置を駆使した上演と同時代の図像資料を比較する。そのうえで「受胎告知の夜」「昇天の階梯」「聖霊の光熱」といった要素を検討し、演劇研究と美術史研究のあいだに広がる閾の可能性を提示したい。
杉山博昭(すぎやま・ひろあき)早稲田大学高等研究所助教
国際基督教大学教養学部卒業。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。京都教育大学非常勤講師などを経て現職。専門は西洋演劇史、西洋美術史、表象文化論。著書に『ルネサンスの聖史劇』(中央公論新社、2013年、第5回表象文化論学会賞奨励賞)、論文に『パンとサイコロに賭けられるもの —— 聖史劇の聖別と瀆聖』(『表象』第10号、2016年)など。
片山幹生「中世フランス演劇とは何か?
― フランス演劇史における中世の位置づけとその可能性について」
中世([英]Middle Ages、[仏]Moyen-Âge)とは古代と近代の「中間の時代」である。フランス演劇史においては、5世紀から15世紀にわたる中世の1000年間はほぼ空洞として扱われ、古代ギリシア・ローマと近代が直結しているかのように語られることは珍しくはない。中世フランス演劇は演劇史のなかで古代演劇とも近代演劇とも断絶した存在となっている。
この発表では9世紀から16世紀にいたる中世演劇の諸ジャンルの見取り図を提示しその特質を示すことで、中世フランス演劇とはどのようなものであったかを明らかにしたい。また20世紀以降の演劇で中世演劇がどのように取り上げられたかを確認し、中世演劇が現代において持ちうる可能性について考えたい。
中世演劇史は9世紀から14世紀までの前期と15・16世紀の後期の二つの時代に区分したほうがとらえやすいだろう。ヨーロッパで文献の上で、演劇的活動を確認することができるのは9世紀以降である。西洋演劇史では教会の典礼の枠組みのなかで発達した「典礼劇」をヨーロッパ演劇の源としている。初期中世演劇では「典礼劇」の他、修道院の学僧たちが古代ローマ劇を模倣して書いたラテン語劇がいくつか残っている。また13世紀の都市では、ジョングルールと呼ばれる芸人や兄弟会(コンフレリー)と呼ばれる互助組織が、多様な主題に基づく演劇作品を制作・上演した。しかしあらゆる文芸が口承によって伝えられ、演劇的状況で演じられていたこの時代には、演劇と他の語り物文芸の境界はしばしばあいまいであり、作品の数も多くはない。
いわゆる中世フランス演劇が最も活動的だったのは15、16世紀である。この時代には町の広場などで上演された聖史劇(ミステール)、受難劇(パッション)、寓意道徳劇(モラリテ)、笑劇(ファルス)、阿呆劇(ソティ)、独白劇(モノローグ)などのさまざまな演劇ジャンルが花開いた。
しかしこれらの中世劇の諸ジャンルは16世紀後半の宗教戦争の頃には急速に衰えてしまう。スペイン喜劇、イタリアのコメディア・デラルテ、プレイヤッド派による人文主義演劇が17世紀のバロック演劇、古典主義演劇の成立に寄与するのに対し、フランス中世演劇の諸ジャンルの遺産は、笑劇を除いて、ほとんど次世代のフランス演劇に継承されることはなく、忘れ去られてしまった。
17世紀から19世紀のあいだ、フランスでは中世劇の存在はほぼ忘却されていたが、19世紀になると文献学の発達により、作品の校訂が進展し、再びその存在が知られるようになった。20世紀に入ると中世劇の復活上演が行われたり、中世劇のスタイルを模倣した作品が発表されたりするようになった。今発表では、20世紀以降の中世劇のあり方、とらえ方についても言及する。
片山幹生(かたやま・みきお)
早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学。パリ第10ナンテール大学DEA取得(フランス文学・比較文学)。早稲田大学、武蔵大学非常勤講師。専門は中世フランス文学およびフランス演劇。論文:「13世紀演劇テクストの流動性:初期フランス語演劇作品と語りものジャンル」『西洋比較演劇研究』(第10号)、p.45-58、2011年;「初期フランス語演劇作品写本の話者指示表記:演劇的パラ・テクストの確立とジャンルの受容の問題について」『西洋比較演劇研究』(第4号)、p.19-32,2005年。翻訳:C・トリオー/C・ビエ(著)、佐伯隆幸(日本語版監修)『演劇学の教科書』東京:国書刊行会、2009年。

日時 2016年4月9日(土)午後2時~6時
場所 成城大学3号館312教室
http://www.seijo.ac.jp/access/index.html
3号館は、正門から中庭に進んで左側の建物です。
総会 午後2時~4時
2015年度活動および会計報告、2016年度計画および予算などが議題になります。後半では、30周年記念行事をめぐるディスカッションをおこないます。
例会 午後4時15分~6時
講演 狩野良規 「映像と舞台中継の間――シェイクスピア史劇を題材にして」
*終了後、3号館1F学生ホールで懇親会があります。どうぞご参会ください。
講演 狩野良規 「映像と舞台中継の間――シェイクスピア史劇を題材にして」
2015年12月の例会シンポジウム「ライブ×メディア――演劇と映像の関係性をめぐって」に触発されて、しゃべってみる気になりました。ポイントは2つ。
1.舞台中継は平成になってから格段に技術的進歩をとげています。昔の舞台中継のイメージを持っている人たちの固定観念を揺さぶってみたい。
2.一口に映像といっても、最初から映画にする場合と舞台中継とでずいぶん違う。
また、昨年のシンポジウムは包括的な議論でしたので、今回は材料を1つに絞り、ケース・スタディにします。演劇と映画の大きな違いのひとつはセリフ量にあると思います。そこでネタは“饒舌なる”シェイクスピア劇。沙翁のイングランド史劇の第2四部作、『リチャード二世』、『ヘンリー四世』第1部・第2部、『ヘンリー五世』をオールロケーション撮影によってテレビ番組化した『空ろな王冠』(BBC、2012年)と、同じ演目の舞台をロイヤル・シェイクスピア劇団(RSC)が映画館観賞用に配信した作品のDVD(除RSC『ヘンリー五世』)を見比べます。ナビゲーターのおしゃべり45分、DVDの鑑賞45分、質疑応答30分の予定(は未定)でいます。
狩野良規(かのうよしき)
1956年、東京都生まれ。青山学院大学教授。専攻はイギリスおよびヨーロッパ文学・演劇学・映像論。著書に『シェイクスピア・オン・スクリーン』(三修社)、『スクリーンの中に英国が見える』(国書刊行会)、『ヨーロッパを知る50の映画』正・続(国書刊行会)、論文に「テューダー朝におけるバラ戦争観」、「BBCシェイクスピア覚書」など。

日時 2016年1月9日(土) 14:00~18:00
会場 成城大学7号館3F 733教室
研究発表
藤原麻優子
「2.5次元ミュージカルへのアプローチ」
村井華代
「ドラマ国家の未完のドラマ──イェホシュア・ソボル『シューティング・マグダ(パレスチナの女)』とイスラエル」
要旨・プロフィール
藤原麻優子 「2.5次元ミュージカルへのアプローチ」
要旨
近年、「2.5次元ミュージカル」と呼ばれる演劇ジャンルが人気を博している。「2.5次元ミュージカル」という名称について、2.5次元ミュージカル協会公式サイトには「2次元で描かれた漫画・アニメ・ゲームなどの世界を、舞台コンテンツとしてショー化したものの総称」とある。しかし、たとえば「ミュージカル版『デスノート』(2015年、日生劇場ほか)は2.5次元ミュージカルなのか」あるいは「宝塚歌劇は2.5次元なのか」という問いがあるように、2.5次元ミュージカルという名称の含意するところは一定のジャンルの作品を翻案した舞台というだけではない。そこで本発表では、これまでその商業的な側面や2.5次元性について着目されてきた2.5次元ミュージカルについて、ミュージカル研究の立場からのアプローチを試みる。多くのミュージカルが何かしらの原作を翻案したものであるとき、2.5次元ミュージカルと従来のミュージカルとでは何が、どのように異なるのか。本発表ではまず、漫画・アニメを原作とするミュージカルが2.5次元ミュージカルにいたるまでの変遷をたどる。次に、2.5 次元ミュージカルと称される舞台の特徴を分析する。そして、これらの特徴を従来のミュージカルと比較することで、2.5次元ミュージカルについて考察を行いたい。
プロフィール
早稲田大学第一文学部卒業後、同大学院文学研究科博士課程単位取得満期退学。博士(文学)。早稲田大学文学学術院演劇映像専修助手などを経て現在早稲田大学演劇博物館招聘研究員。
村井華代 「ドラマ国家の未完のドラマ ──イェホシュア・ソボル『シューティング・マグダ(パレスチナの女)』とイスラエル」
要旨
イェホシュア・ソボル(Yehoshua Sobol, 1939-)は、イスラエルの現代劇作家で最も世界に知られる存在である。日本でも1995 年6月、彼の『GHETTO/ゲットー』(イスラエル初演1984)が、ひょうご舞台芸術により上演されたことはつとに有名だ。ヴィルナ・ゲットーに実在したユダヤ人劇団を描いたその戯曲が、阪神大震災後の演劇人に対しても特別な意味を持ったことを、生々しく思い出す人も多いことだろう。
だが本発表では、『GHETTO』と共に広く知られる『シューティング・マグダ(パレスチナの女)』(Shooting Magda / The Palestinian Woman [Paletinait], 1985)を通じて、現代イスラエルの劇作家としてのソボルに目を転じたい。『GHETTO』ではユダヤ人評議会の存在が、ドラマをユダヤ受難劇ではなく生存することそれ自体のジレンマへと導いたが、『マグダ』では80年代の国民の一人であるアラブ人女性の視点から、実現したシオニズム的「夢」としての国家イスラエル像が「悪夢」となる様が描かれる。いわば、特定の視点からドラマ化されてきた現実が、ここでもその担い手たちによって解体されてゆくのだが、『マグダ』ではその過程がメタシアター的に露出している。
戯曲の舞台は、イスラエル国籍のアラブ人女性サミラの実体験に基づくTV映画を、ユダヤ系・アラブ系が混在するキャスト・スタッフで撮影しているスタジオ。締切直前であるにもかかわらず俳優たちの主張が入り乱れ、撮影は一向に進まない。ドラマはファルス的に混乱し、サミラと監督兼俳優ベネシュが共同で執筆したシナリオのラストは霧に包まれる。
国家イスラエルの成立という《ドラマ》は、ソボルによっていかに《完成しないドラマ》として解体されているか。イスラエルをテーマ化したいくつかの映画を導入として用いつつ、同国を代表する劇作家の批判的視点を読み解いてゆきたい。
プロフィール
西洋演劇理論。これまで現象学・神学・反演劇主義などの見地から、地域・時代を横断して演劇を論じる可能性を模索してきたが、2012年よりイスラエル演劇の研究に特化。共立女子大学文芸学部教授。
論文「S.アンスキ『ディブック』とユダヤ演劇の近代」『共立女子大学・共立女子短期大学総合文化研究所紀要』20号(2014)、「イスラエル/パレスチナ対立への演劇的アプローチ──『シルワンの孔雀』(2012) を中心に」同21号(2015)ほか

西洋比較演劇研究会12月例会シンポジウム「ライブ×メディア―演劇と映像の関係性を
めぐって」
2015年12月19日土曜日 14:00-18:00
会場 成城大学3号館 311教室 http://www.seijo.ac.jp/access/index.html
パネリスト:岡原正幸(慶應義塾大学)、辻佐保子(早稲田大学)、田ノ口誠悟(早稲田大学)
【司会】小菅隼人(慶應義塾大学)
コメンテーター:熊谷知子(明治大学)山下純照(成城大学)
マクルーハンは、『メディア論』の副題を、 “The Extension of Man” 「人間の拡張」として、言語や数を始めとする人間の「発明した」あらゆる表現媒体を「メディア」ととらえ、それらの媒体による人間の拡張可能性を指摘しました。マクルーハンは、声や身振りといった生得的な身体の直接表現と「メディア」を対置的なコミュニケーションと捉えており、前者が使われる部族社会(Tribal Society)を「メディア以前」の社会としています。マクルーハンの用語法を援用すれば、通常我々がイメージしている劇場はメディア以前の共同体ということになるでしょう。これまで、演劇には、ごく当たり前のように、「舞台は生物(なまもの)」、「実演の魔力」、「俳優のエネルギー」と言った神秘化が付され、演劇は、舞台上の身体と観客席の身体が同一の場に存在し、「直接的に」伝達される芸術とされてきました。
まず、ここで問題になるのは、俳優の「エネルギー」の支配が及ぶ範囲はどこまでか、という問題でしょう。マクルーハンの議論によれば、メディアに依らずに伝達できる範囲ということになるかもしれません。しかし、同じ時間、同じ場所に存在していても、つまり現前していても、現前効果が非常に薄い場合もあるでしょう。たとえば野球の試合において、外野席の一番後ろで見る野球体験と、テレビでアップやプレーの再現を交えながらで観る場合とどちらが現前効果はあるのでしょうか?
次に、時間的な差異は現前/現前効果という点からどのように考えたらいいのでしょうか? 2006年、ロンドンのパラディアム劇場で初演された『ロンドン・パラディアム劇場のシナトラ』では、スクリーンの中のフランク・シナトラ(1915‐1998)は、自らの生涯を語り、実際のオーケストラの演奏にシンクロして歌います。スクリーンの前では実在の20人のダンサーが踊り、時にはスクリーンを出入りします。パラディウム劇場はシナトラが1950年にイギリス・デビューを果たしたまさにその場所です。シナトラはすでに亡くなっていますので、ライブ・パーフォーマンスでありながら、このショーでは主演俳優がスクリーンの中にしか登場しません。このイベントは、ライブ・パーフォーマンスという観点からどのように位置づけられるのでしょうか?舞台上のダンサーと映像の中のシナトラは、存在論的にどのような違いがあるのでしょうか?シナトラの現前効果はシナトラの現前を実現しないのでしょうか?
さらに、私たちは、演劇を論じる場合、多くの場合映像を利用しますが、それは、厳密な意味で演劇研究とは言えないのでしょうか?慶應義塾大学アートセンター土方巽アーカイブには、1986年に亡くなった土方の資料(主として映像)を求めて、ほぼ毎日のように、海外から研究者やダンサーが訪れます。一方、現在50歳代以上の中には、土方巽と一緒に活動をした研究者・ダンサーが残っています。映像でしか土方を知らない世代の研究者は、実際に土方巽の舞台経験のある研究者には、何らかの意味でも、及ばないのでしょうか?
パネリストの方々には司会者から3つの問いかけをしてあります。①演劇のメディアによるライブ性の拡張可能性をどこまで認めるか、②メディア化された演劇映像にどのような可能性と限界があるか、③メディア化された演劇映像を研究材料として使う場合にどのような問題があるのか。各報告者には、上記3つの問いに対する答えを織り込んでいただき、それぞれのご専門の具体例を1~3例ほど示してくれるように依頼してあります。シンポジウムでは、最初に私が若干の趣旨説明をした後、まず、パネリストに各25分以内で報告をしていただき、その後、パネリスト間のダイアローグを行い、休憩にします。その後、コメンテーターの発言に続いて、ダイアローグをフロアに開きたいと思います。多分演劇体験の根本にも及ぶであろうこの大きな問題を、皆様と一緒に考えたいと思います。 (小菅隼人)
●岡原正幸(慶應義塾大学)
「パフォーマティヴ・ターン以後の認識実践」
社会学的な認識実践の歴史において、個人・身体・主体の系と、社会・役割・システムの系は長きにわたって、主人公の役を互いに奪い合ってきた。1980年代以降、両者の調停は幾度となく繰り返され、純粋な社会理論の次元では主人公を分け合っている現状である。他方、生きられる経験を主軸として身体性に着目する認識実践が90年代以降登場する。今回の私のトークでは、専門としてきた社会学実践の動きを参照しながら、演劇という出来事における「ライブ×メディア」の問題を考えたい。デリダが西欧哲学の流れで批判した現前の形而上学、それと同型の経験構造は近代社会の成り立ちの根幹にもあり、私たちの日常意識を形成するものでもある。およそあらゆる社会制度は、芸術も文学も演劇も、この形而上学を「事実」として受容することで、あるいはそれを日々実践的に再生産(パフォーマンス)することで運営されてきた。演劇学や社会学という研究実践、認識実践もその例外ではない、この点に注目しながら、司会者の問いかけに答えられたらと思う。
【プロフィール】
岡原正幸(おかはらまさゆき)
慶應義塾大学文学部(社会学専攻)教授。慶應義塾大学経済学部卒業。ミュンヘン大学演劇学専攻。慶應義塾大学社会学研究科博士課程修了。ハンブルク大学パフォーマンス・スタディーズセンター客員研究員。専門は、感情社会学、障害学、アートベース・リサーチ、パフォーマンス・エスノグラフィなど、著作としては『感情を生きる ~パフォーマティブ社会学へ』(慶應義塾大学出版会、2014年)『感情資本主義に生まれて ~感情と身体の新たな地平を模索する』(慶應義塾大学出版会、2013年)『生の技法 ~家と施設を出て暮らす障害者の社会学』(第3版文庫版 生活書院、2012年)『黒板とワイン ~もうひとつの学び場「三田の家」』(慶應義塾大学出版会、2010年)『ホモ・アフェクトス ~感情社会学的に自己表現する』(世界思想社、1998年)などがある。
●辻佐保子(早稲田大学)
「ベティ・コムデン&アドルフ・グリーン作品における複製メディアの機能とその変容についての考察? ブロードウェイ・ミュージカルに生じた『ライブ×メディア』の転換を背景として」
ブロードウェイ・ミュージカルにおけるライブ・パフォーマンスと複製メディアとの関係は、1960年代後半から1970年代にかけて、大きく変化していく。ロック・ミュージカルの勃興を皮切りに、電子サウンドが本格的に取り込まれ、劇場へのスピーカー設置が進行し、マイクの使用も常態となる。複製メディアの導入によって、ブロードウェイ・ミュージカルにおける「ライブ×メディア」のあり方やライブ性という概念はどのように変容や再検討が迫られたのだろうか。
本発表では、脚本家・作詞家のベティ・コムデン&アドルフ・グリーンに光をあて、作中に登場する複製メディアの機能分析を通して、「ライブ×メディア」を巡る時流の変化に際した同時代的な反応を浮き彫りにすることを目指す。具体的には、『フェイド・アウト ? フェイド・イン』(1964)、『アプローズ』(1970)、『雨に唄えば』(1985)を取り上げて、身体性の強調から、現前する身体の「正統性(オーセンティシティ)」の相対化と強化へと複製メディアの機能が変化し、併せてライブ・パフォーマンスとしてのあり方が問い直されていることを、上述の時流の変化との結びつきを指摘しながら明らかにする。(なお発表では触れないものの、当該時期には上演映像のアーカイブ化やトニー賞授賞式のテレビ放送も開始する。可能であれば、演劇映像を巡る可能性や限界、諸問題は発表後のダイアローグで触れたい)
【プロフィール】
辻佐保子(つじさほこ)
早稲田大学文学研究科助手・博士後期課程在籍。専門はアメリカン・ミュージカルとミュージカル映画。論文:「ミュージカル『特急二十世紀号に乗って』における楽曲の機能 - スクリューボール・コメディからの翻案という背景を踏まえて」『早稲田大学大学院文学研究科紀要』(2014年、59号第3輯)「電話・俳優・「パフォーマティブ」な演劇のモード - ミュージカル『ベルがなっている』論」『表象・メディア研究』(2013年、3号)、「"Time is Precious Stuff" - ミュージカル『オン・ザ・タウン』における時間表象についての考察」『演劇映像学』(2013年)
●田ノ口誠悟(早稲田大学)
「近現代演劇における「ライブ性」を拡張した諸表現について―フランスの例を中心に」
本シンポジウム「ライブ×メディア―演劇と映像の関係性をめぐって」は、「芸術作品」としての演劇を長らく条件づけてきた「ライブ性」「現前性」という美的概念を相対化し、これまでの演劇を見直してみようとするものといえる。インターネットの発達によって「劇場にいない観客(ウェブカメラの向こうの観客)」という現象が生じ、なにを持って演劇体験とするかが問題となっているのである。
私は、この問題提起について、特にフランス近現代演劇を例にして考えてみたい。まず、「演劇はライブの芸術である」という視点が比較的最近批評家の間で生まれた美学の一つに過ぎないことを指摘する。そのうえで、「ライブとしての演劇」という視点からはみ出る(それゆえ従来の演劇史においてはさほど尊重されなかった)事例をいくつか紹介する。考えてみれば、アルフレッド・ド・ミュッセの「肘掛け椅子の演劇」からステファン・ケーギの「携帯電話の演劇」まで、欧米においては実に多くの演劇人がさまざまなメディアを使って演劇のライブ性の範囲を広げてきたのである。
【プロフィール】
田ノ口誠悟(たのくちせいご)
早稲田大学大学院文学研究科博士課程在籍。専門:二十世紀フランス演劇、主な論文:「演劇とデモクラシー――政治的言論生産装置としてのジャン・ジロドゥ『ジークフリート』」、『フランス語フランス文学研究』(日本フランス語フランス文学会)103号
◆上記の内容はこちらからPDFでもダウンロードできます。
こちらの参考資料もご覧ください。

後期最初の例会を以下の日程で行います。
若手研究者によるシンポジウムです。ぜひ奮ってご参加ください。
日時:2015年10月10日(土)14:00?18:00
会場:成城大学 3号館 1F 312教室 http://www.seijo.ac.jp/access/index.html
内容:シンポジウム「演劇の近代化と俳優術の変容」
1. 新沼 智之
「西洋演劇における演技の近代化の変遷」
2. 奥 香織
「タルマの舞台実践にみる俳優術の変容とフランス演劇の近代化」
3. 村島 彩加
「明治・大正期の日本演劇における狂気の表現-演劇写真を手掛かりとした一考察-」
コメンテーター:神山彰
司会:山下純照
【趣旨】
近代演劇は19世紀末、リアリズムや自然主義の文脈あるいはその影響下で成立する。一つの美学的・芸術的視点によって舞台を統一しようとする意志のもと、演出家が登場するのもまたこの時代である。しかしながらこれらの事象は突然現れたものではない。その萌芽が、例えば18世紀の市民劇やディドロの理論にみられることは知られているが、実践の場においてもまた、前段階としてさまざまな試みが行われていた。例えばドイツでは、エクホーフやイフラントの演技や劇団統制がアンサンブル演技に先立つものとして存在する。フランスでは、18世紀中葉から、より自然な朗唱、物語の世界に即した衣装が探求され始める。一方、日本演劇においても、近代以降の俳優の表現方法に見られる変容の萌芽は、前近代に見出すことが可能である。しかし、それが近代以降にどのように実現されていったのかは、当時の文脈をふまえた上で、「前近代」の表現方法との比較をすることで、真に明らかにすることができると考えられる。
演劇史をあくまでも流れとして捉える中で、近代演劇もまた固定したものではなく、継続的な変化を遂げながら、しかしそれでいて何らかのイメージをもって演劇の在り方を把握するための道具概念として理解され得る。それによって、例えばポストモダンへの眼差しが可能になるわけであるが、本シンポジウムでは逆に近代演劇というゴールを設定してみることで、それ以前の演劇史がどのように描き出されるかを、ドイツ、フランス、日本を主たる研究対象とする三名が、演技を中心に考えてみたい。時にないがしろにされがちな「前近代」をしっかりと把握することは、近代演劇へと新たな眼差しを向ける機会ともなるのではないか。
【発表1】
発表者:新沼 智之
題目:「西洋演劇における演技の近代化の変遷」
発表要旨
「アンサンブル演技」は西洋演劇の近代化における演技のあり方の一つの到達点と言えるだろう。本発表では、18世紀半ばにまでさかのぼり、そこから19世紀末に完成する「アンサンブル演技」をゴール地点として、演技の近代化の変遷を概観したい。そこで、発表者が主張したいことは、「アンサンブル演技」が完成するまでに4つの段階を経たということである。
第1段階は、古典主義から市民劇への移行における劇作上の変化である。18世紀の半ばに登場した散文の市民劇では、ト書きが多く書き込まれるようになり、俳優はそれを身振り・表情を使って演じることが要求されるようになる。そしてそれはすぐさま、戯曲に書き込まれていない身振り・表情が俳優主導で増大していくという第2段階に入る。 ここで取り上げたいのが、対話者の台詞を「聞く演技」である。さらに、その「聞く演技」が拡張するかたちで第3段階に至る。すなわち、集団演技への意識が生まれる段階である。ここで「アンサンブル演技」という演技のあり方がはっきりと目指されるようになっていく。その主導的役割を担ったのがザクセン=マイニンゲン劇団であるのは言うまでもない。そして最後の第4段階として、スタニスラフスキーのモスクワ芸術座を挙げねばならない(ただ、それはそれまで定着してこなかった、以上に列挙してきたことがらを徹底的に実践し根付かせたとまとめることができ、歴史的には極めて重要なことではあるが、いわば質的向上にすぎないと言えるので、今回は―― もちろん念頭には置くが――特に深入りはしないことにする)。
プロフィール
明治大学ほか非常勤講師。研究テーマはドイツを中心とする西洋演劇の近代化のプロ
セス。論文に「A.W.イフラントが目指した舞台づくり――視覚的要素の問題を中心
に」『演劇の課題2』(三恵社、2015年)、「18 世紀後半のドイツにおけるアンサン
ブル演技理念の萌芽と劇団規則」『西洋比較演劇研究』(Vol.12 No.2、2013年)ほか
。
【発表2】
発表者:奥 香織
題目:「タルマの舞台実践にみる俳優術の変容とフランス演劇の近代化」
発表要旨
フランスでは、特に18世紀後半以降、演劇の近代化が進む。舞台上の客席の廃止によって演技空間が広がり、上演に求められるスペクタクル性も変容していく。こうした中で登場する俳優タルマは、一世代前からルカンやクレロンによって試みられてきた衣装や演技(朗唱)の改革を土台とし、実践面におけるさらなる改革を試みる。
タルマは衣装を史実に基づいたものにしようと努め、朗唱から約束事を排除することで、舞台の 「リアリズム」を探求する。しかしながら、「自然さle naturel」という語を用いて表現される演技は、絵画や版画、同時代人の証言を参照すると、実際には様式化され、誇張されたものである。また、改革の試みは基本的に古典悲劇の枠内で行われ、演劇観の根底にあるものも伝統的な模倣観である。これらの点には伝統と革新の間で揺れ動く俳優の姿が見受けられるが、この両義性にこそ、近代化の過程にあるフランス演劇の在り方、古典主義的な上演空間から逸脱しようとする姿を見出すことができるのではないか。
本発表では、舞台の近代化という観点から重要であるタルマの試みに光をあて、伝統的な部分、革新的な部分を浮き彫りにしつつ、タルマが求めた「リアリズム」、彼自身が強調した「自然さ」とはいかなるものであったのかを明らかにしたい。改革を可能にした社会背景、当時の思想との関係も検討したいと考えている。
プロフィール
早稲田大学文学研究科博士課程単位取得退学、パリ第4大学博士課程修了。現在、日
本学術振興会特別研究員、早稲田大学ほか非常勤講師。専門はフランスの舞台芸術、日
仏演劇交流。現在の主な研究対象は18世紀フランスの舞台実践、演劇美学。論文:「マ
リヴォーにおける「露呈」の演劇性」(『日仏国際シンポジウム 演劇と演劇性』、早
稲田大学演劇映像学連携研究拠点、2014)、「ルサージュの初期作品にみるアルルカン
の表象」(『西洋比較演劇研究』 Vol.14 No.2、西洋比較演劇研究会、2015)など。
【発表3】
発表者:村島 彩加
題目:「明治・大正期の日本演劇における狂気の表現-演劇写真を手掛かりとした一考
察-」
発表要旨
明治30年代後半、俳優の演技において「表情」の重要性を指摘する声が高まるのと同時期に、演劇写真においても、俳優の「表情」をとらえることに眼目を置いた写真が撮影されるようになる。本報告では、それらの写真の中でも「狂気」の表情をとらえたものに注目する。
当該時期に「狂気」の表情を捉えた写真が目につくようになる背景には、それをモティーフとした作品の上演があることは言うまでもない。近代以前より、日本演劇において「狂気」は重要な モティーフであったが、その表現には定型、約束事があった。しかし、明治維新以降、心理学・精神科学の隆盛とともに、一般社会における「狂気」の概念が変化し、「狂人」とされる者の扱いには変化が起こっていた。そうした時流の中で、俳優たちは「狂気」をどのように表現しようとしたのか。
本報告では、五代目尾上菊五郎とその息子である六代目が共に扮した『水天宮利生深川』船津幸兵衛役における狂気の表現の工夫の違いや、帝劇女優・森律子が扮した『遺伝』(益田太郎冠者作)おかよ役の役作りを例に考察すると共に、近代以前・以後で劇作家(狂言作者)たちが「狂気」をどのように描いたのかという相違点も、複数の作品を挙げて検証し、その表象の一環として、演劇写真がどのような役割を果たしたのかも併せて考察したい。
プロフィール
明治大学大学院文学研究科演劇学先行単位取得退学。現在、日本学術振興会特別研究
員(PD)、明治大学兼任講師。専門は近代日本演劇(演劇写真、歌舞伎の近代化、宝塚
)。最近の論考に「七代目松本幸四郎の「変相」研究とその周辺―舞台化粧指南書Maki
ng Upからの影響を中心に―」『西洋比較演劇研究』Vol.11 No.2(日本語版、2012)、
「近代歌舞伎と宝塚歌劇の交流」『歌舞伎と宝塚歌劇―相反する、密なる百年―』(開
成出版、2014)、「演劇写真研究の泰斗・安部豊の仕事―その成果と活用をめぐって―
」『演劇の課題2』(三恵社、2015)がある。

学期末のたいへん忙しい時期ではありますが、演劇・舞踊研究のフロンティアへ、どうぞ多数の方が足をお運びくださいますよう、お待ちしています。 ※紀要投稿についてはこの記事の末尾に案内がございます。
日時 2015年7月18日(土) 14:00~18:00
場所 成城大学 3号館3F大会議室
研究発表
川野惠子(14:00~15:55)
「近世フランス舞踊論(メネストリエ、カユザック、ノヴェール)における劇的バレエ作品概念の変遷――デッサンからアクシオンへ」
松田智穂子(16:05~18:00)
「ブラック・ナショナリズムとモダン・パジェント―W.E.B.デュボイスにみる」
要旨・プロフィール
川野惠子「近世フランス舞踊論(メネストリエ、カユザック、ノヴェール)における劇的バレエ作品概念の変遷――デッサンからアクシオンへ」
要旨:
18世紀バレエ・ダクシオン運動の嚆矢と位置づけられるJ.-G.ノヴェールの著作『舞踊とバレエについての手紙』(1760)について、昨今の研究は17世紀にC.-F.メネストリエが著した舞踊理論書『劇の諸規則にしたがう新旧のバレエについて』(1682)からの借用の問題を指摘する。これまで18世紀バレエ・ダクシオン運動内における理論上、あるいは実践上の違いについて多くの研究がなされてきたが、この指摘は17世紀古典主義時代における劇的バレエ作品概念と18世紀のバレエ・ダクシオン運動との共通点、及び相違点を考察することが今後の重要な研究課題であることを示しているといえよう。そこで本発表はメネストリエ、カユザック(『新旧の舞踊、あるいは舞踊の歴史的論説』1754年)、ノヴェールによる舞踊論について考察し、近世フランス舞踊論における劇的バレエ作品概念の変遷を明らかにすることを目的とする。
メネストリエはバレエ固有の制作諸規則として「構想の統一(unité de dessein)」を指摘する。これは選択する題材に資するあらゆるものを枚挙し、作品を成立させようとする制作諸規則であり、もっぱら制作上の統一性を問題とする。一方18世紀のカユザック、およびノヴェールはダンス・アン・アクシオン(danse en action)といって劇的バレエ作品における筋/アクシオンの問題を重視する。カユザックはこれを筋の継起的統一性において、ノヴェールはより瞬間的な場面の統一性において追求する。ただしこれらは制作上の統一性というより、観客の関心における統一性の問題であることが重要である。つまり、18世紀バレエ・ダクシオン運動は観客の関心を作品制作の重要な原理に据え、この点が古典主義時代とは異なるバレエ・ダクシオン運動の劇的バレエ作品概念の特色といえよう。
プロフィール:
(かわの・けいこ) 大阪大学大学院文学研究科博士課程。日本学術振興会特別研究員(DC2)。専門は美学、近世フランス舞踊論。論文:「J.-G.ノヴェール『手紙』(1760)における舞踊の語り――アクシオン概念の検討を軸に」『美學』242号(美学会、2013年)、167~178頁。「J.-G.ノヴェール『手紙』(1760)における独創性概念――自然としての個別的身体」『芸術学』第18号(三田芸術学会、2014年)、52~66頁。
松田智穂子「ブラック・ナショナリズムとモダン・パジェント―W.E.B.デュボイスにみる」
要旨:
ヨーロッパ中世から早期近代に頻繁に上演されたパジェントは、1905年にルイス・ナポレオン・パーカーが英国で「民衆劇」を上演したことをきっかけに復活し、爾来世界各地へ広がった。米国には早くも1908年に伝わり、瞬く間に全米主要都市で行われたるようになる。英国では階級間の軋轢の解消が重視されたが、米国では移民融合がパジェントの重要なテーマとなり、社会および芸術の改革運動、そして歴史を描くことを通じて共同体意識を生成する運動として発展した。
20世紀米国で活躍した黒人社会学者・活動家W.E.B.デュボイス(1868年-1963)は、こうした米国式パジェントが概してアングロ・アメリカン中心の内容、活動だった点を指摘し、ブラック・ナショナリストの観点から自らパジェント作品を執筆・制作した。米国の黒人コミュニティに働きかけ、さらには白人世界に対して、黒人の感受性をアピールするためである。
黒人初のパジェントとされるThe Star of Ethiopia(1915年初演、その後4度再演)では、デュボイスはエチオピアニズムに傾倒し、米国黒人のルーツと人種的誇りの拠り所をアフリカの神話的なイメージに求めた。しかしながら、1932年に発表されたGeorge Washington and Black Folkでは、白人中心主義的な米国の正史、つまり近代国家・米国の創世神話の中に黒人の存在と活躍を書き加えようとした。本発表では、これらのパジェント作品は、デュボイスが生涯追究しつづけた米国黒人の「二重意識」にひとつの解消法を提示していたことを明らかにする。
プロフィール:
(まつだ・ちほこ) 2011年、一橋大学言語社会研究科より博士号取得。現在、専修大学経済学部専任講師。専門は20世紀以降の英米および英語圏カリブ海地域の演劇および演劇文化。
論文:“ ‘Her Breathing… fills the Lungs of the Theatre’: A Woman on a Caribbean Stage in Derek Walcott’s A Branch of the Blue Nile (1983). ” (Dorsia Smith, et al. Critical Perspectives on Caribbean Literature and Culture.New Castle: Cambridge Scholars Publishing, 2010.)、 “Derek Walcott: A Caribbean ‘National Theatre’ vs. Neo-Colonialist Tourism” (Comparative Theatre Review Vol. 13, No. 1, 2014.)
*質疑応答の活発化のため、発表者にあらかじめ基本的な先行研究ないし参照文献をご教示いただいています。お二方が上げてくださった文献を記します。
川野氏(再掲):
Laura Carones, “Noverre and Angioloni: polemical Letters”, in: Dance Reseach, vol. V. no.1, Spring (Edinburgh University Press, 1987), pp.42-54.
譲原晶子「メネストリエのバレエ理論からみたノヴェール――『舞踊とバレエについての手紙』(1760)における借用を巡って――」『美學』244号(美学会、2014年)、121~132頁。
松田氏:
モダン・パジェントの基礎知識について
https://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/handle/2065/31506
【紀要投稿についてのご案内】
分科会紀要『西洋比較演劇研究』の新しい投稿規定・執筆要領が分科会HPにアップロー
ドされています。今年度(2015年度)より、「論文」と「研究ノート」の二つの枠が設
けられました。次号の投稿締切日は「2015年11月1日」です。過去の例会で発表された
方を始め、多数の方々からの投稿をお待ちしています。
http://comparativetheatre.org/?page_id=11

日時 2015年5月16日(土)14:00-18:00
場所 成城大学3号館3F 大会議室 http://www.seijo.ac.jp/access/index.html
今回は紀要『西洋比較演劇研究』について、最新号の論文合評と、「Vols.11-14 を振り返る」の二本立てとなります。
1『西洋比較演劇研究』Vol.14 合評会 14:00- 16:00
本会紀要『西洋比較演劇研究』第14巻第1号(英語)・第2号(日本語)に掲載された論文の合評会です。これまでも同様の合評会を何度か行なって参りました。紀要がウェブ上公開となってからは、2回目となります。それぞれ内容を要約することなく、ただちに各30分ほどの質疑応答をおこないたいと思います。ご参会予定の方は、ぜひともリンク先からPDFファイルをダウンロードして論文を読んでおいでください。
『西洋比較演劇研究会』第14巻第1号
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/ctr/14/1/_contents
『西洋比較演劇研究会』第14巻第2号
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/ctr/14/2/_contents
全体司会:萩原健
Fumio Amano, "Zeami’s Poetics as Manifested in T?ru"
討論者: 毛利三彌
Akihiro Odanaka, "Revenge and the Marketplace: A Study of Chikamatsu Hanji’s Travel Game while Crossing Iga"
討論者:井上優
奧香織「ルサージュの初期作品にみるアルルカンの表象」
討論者:安田比呂志
鈴木美穂「憑依のダイナミックス??演劇論としてのキャリル・チャーチル『小鳥が口一杯』」
討論者:小菅隼人
2「『西洋比較演劇研究』Vols.11-14 を振り返る」 16:15-18:00
次号より編集部の交代を控え、電子化・ウェブ上公開をはたした11号(2011年)からの内容や編集方針についての検討を行います。
司会:小田中章浩
討論者:山下純照、日比野啓

日時 2015年4月11日(土)午後2時~6時
場所 成城大学3号館3F
http://www.seijo.ac.jp/access/index.html
3号館は、正門から中庭に進んで左側の建物です。
総会 午後2時~3時
運営委員の一部交代、2014年度活動および会計報告、2015年度計画および予算などが議
題となります。
例会 午後3時15分~6時
講演1 小菅隼人「PSi #21 Fluid States 2015 Tohokuの開催について」
講演2 山下純照「PS=パフォーマンス・スタディーズを意識した演劇研究の可能性」
*終了後、懇親会を行います。どうぞご参会ください。

気鋭の若手、充実の中堅による発表3本です。
いつもと時間帯が異なりますのでご注意ください。
日時 2015年1月10日(土) 13:30~18:30
会場 成城大学7号館 731教室
研究発表
1 關智子 (発表13:30~14:20、質疑応答14:20~15:10)
2 大浦龍一(発表15:20~16:10、質疑応答16:10~16:50)
3 譲原晶子(発表17:00~17:50、質疑応答17:50~18:30)
研究発表1 關智子:
挑発のドラマトゥルギー:サラ・ケインの戯曲に通底する「演劇性」
発表要旨
サラ・ケインは90年代のイギリスを代表する劇作家である。1991年の処女作発表から99年に自殺するまでの9年間の間に8本の戯曲を遺しており、彼女の作家人生の短さにもかかわらず、それらの形式は大きく変化している。
既に個々の作品については多くの分析がなされており、またそれぞれの相違についてはしばしば指摘されるものの、何がケインの作品すべてに共通しており、それがどのように重要であるのかということについての研究はいまだ不十分だと言わざるを得ない。
そこで本発表ではケイン作品のドラマトゥルギーに焦点を当て、その核の抽出を試みる。
具体的には、最初期のモノローグ作品集『病』(未出版)から遺作『4時48分サイコシス』までの戯曲をいくつかの視点から分析し、それらに通底するケインの問題意識について考察する。この分析により、ケインの作品を貫いているのは観客に対するなんらかの働きかけであることがわかり、さらにこの観客への指向性こそが、(特に後期の)およそ上演を前提としているとは思われないテクストでさえも、演劇のために書かれたテクストであることを保証していると考えられる。そしてこのことから、まったく別種であるように思われる「イン・ヤー・フェイス演劇」と「ポストドラマ的」なテクストの間に共通点を見出すことができるだろう。
以上のように本研究は、ケインの作品の根底には常に観客を目指す工夫があることを指摘し、またケインのドラマトゥルギー分析によって90年代以降の英戯曲に見られる大きな変化を理解する手がかりを得ることを試みるものである。
【プロフィール】
關 智子(せき・ともこ)
日本学術振興会特別研究員(DC2)。早稲田大学大学院文学研究科博士課程。専門は90年代以降のイギリス戯曲。国際演劇評論家協会会員、演劇批評ウェブマガジン「シアターアーツ」編集部員。「不在の登場人物と創造=想像力のメカニズム―マーティン・クリンプ『彼女の生に対する試み』論―」(『演劇学論集日本演劇学会紀要57』、2013年)、『ポストドラマ時代の創造力』(藤井慎太郎監修、白水社、2013年、編集補佐)他。
研究発表2 大浦龍一:
松居松葉とバーナード・ショー ―文芸協会公演『二十世紀』を中心に―
発表要旨
バーナード・ショーが1895年12月から翌96年5月にかけて執筆した7作目の戯曲You Never Can Tellは、1899年11月にthe Stage Societyによって初演された。しかし、この作品は本来商業劇場での上演を目論んで書かれたものだが、実現しなかった。この作品が世間的に注目されるようになったのは、1906年のグランヴィル・バーカーによるコート座での上演であった。バーカーは興行師ヴェドレンと組んで1904年から1907年にかけてコート座で商業劇場では上演の機会の少ない作品の連続上演を行っていた。合計32作のうち11作がショーのものだった。このコート座でのYou Never Can Tell上演の観客席に二代目左団次と外遊中の松居松葉の姿があった。
それから6年後の1912年11月、松葉は文芸協会の有楽座公演ためにYou Never Can Tellを『二十世紀』という題で翻訳し、自身で演出した。実はこれは彼が手がけた最初のバーナード・ショー作品ではなく、すでに同年6月に『運命の人』The Man of Destinyの演出をしていた。しかし、そのときの翻訳は楠山正雄であり、協会の試演場での試演であった。そして、『二十世紀』は一幕物の『運命の人』と異なり、四幕の本格喜劇であった。また、松葉の演出による最初の文芸協会公演であった。
松葉にとっては、彼が吸収してきた英国エドワード朝演劇のエッセンスを発揮できる機会だったはずだ。ところが、当時の劇評を読むとあまり芳しいとはいえない。文芸協会内部での坪内逍遥
派と島村抱月派の対立などの裏事情も含め、この公演の問題点を考察したい。
【プロフィール】
大浦 龍一(おおうら・りゅういち)
明治大学文学研究科博士課程単位取得退学。現在、大阪芸術大学通信部講師。日本バーナード・ショー協会事務局長。専門は英国ヴィクトリア・エドワード朝演劇、共著:『バーナード・ショーへのいざない』日本バーナード・ショー協会編(文化書房博文社、2006)、論文:「女神の黄昏 ―晩年のパトリック・キャンベル夫人―」(『バーナード・ショー研究』12号、日本バーナード・ショー協会、2011)、「日本演劇におけるバーナード・ショー元年」(『バーナード・ショー研究』13号、日本バーナード・ショー協会、2013)など。
研究発表3 譲原晶子
イリ・キリアンの舞台外空間――奥行きの闇と舞台袖
発表要旨
イリ・キリアン(1947- )は現代を代表するバレエ振付家として知られている。一晩ものの物語バレエよりも小品を得意とするこの巨匠の作風について、舞踊学者セイヤーズは「非物語劇的バレエnon-narrative dramatic ballet」――すなわち、明確な物語はもたないがドラマティックな表現性をもつ作品――と評し、また彼の『詩編交響曲』(1978)と『墜ちた天使』(1989)の「熟練した群舞操作の類似性」について指摘している。
本発表ではこの2作の他に『結婚』(1982),『かぐや姫』(1988),『サラバンド』(1990),『プチ・モ>ル』(1991)を含む彼の初期から中期にかけての作品群において、手法と呼ぶべきある共通の群舞デザイン・システム(あるいは空間構成システム)が使用されていることを指摘する(この手法は、オハッド・ナハリン、ナチョ・デュアトなど他の振付家の作品にも利用されているのが観察できる)。論者はこの手法を「点―線―面の手法」と名付け、この手法がもつ意味と機能を検討する。
考察で着眼することのひとつに、「ダンサーが舞台に登場、退場するとき方向」の問題がある。上記の作品は、作品中のダンサーの出入>りは総じて少なく、出入りがある場合には舞台袖よりも舞台背景の「闇」が利用されており、作品全体としても舞台空間の「幅」よりも「>奥行き」が活用されようとしている、という特徴が共通してみられるのである。一方キリアンの作品には、『シンフォニー・インD』(1976)など、これとは正反対の作品、すなわち、作品中のダンサーの出入りが激しく、舞台袖のみから登退場し、舞台空間の「幅」がフルに活用される作品も見られる。これら二つのタイプの作品を比較することで、キリアンの「舞台空間」(より正確にいえば「舞台外空間」)に対する考え方を読み解いてゆきたい。
これらの考察を踏まえてさらに、『かぐや姫』の空間構成について分析する。『かぐや姫』はキリアンには異色の一晩もの物語バレエである属するが、やはり「非物語劇的バレエ」の様相を帯びている作品である。この作品も、「点・線・面の手法」を使って構成されているが、これによってキリアンが、筋書きを通してよりも空間を通して物語を構成しようとしていることを論証する。また、本発表の本筋からははずれるが、『かぐや姫』という「日本最古の文学作品」に取材するバレエ作品のグローバル化にまつわる問題についても言及したい。
【プロフィール】
譲原 晶子(ゆずりはら・あきこ)
千葉商科大学教授。主要著書にAnne Woolliams: method of classical ballet (Kieser Verlag, 2006),『踊る身体のディスクール』(春秋社, 2007)、最近の主要論文に、'Kylian’s space composition and his narrative abstract ballet', Theatre Research International, Vol.38, No.3 (Cambridge University Press), 2013;メネストリエのバレエ理論からみたノヴェール―『舞踊とバレエについての手紙』(1760)における借用をめぐって,『美学』244号,2014;’Historical and contemporary Schrifttanz: Rudolf Laban and postmodern choreography’, Dance Chronicle, Vol, 37, Issue 3(Routledge) 2014 などがある。

大変遅くなりましたが、12月例会のお知らせをお送りいたします。
年末の大忙しい折とは存じますが、ふるってご参集くださいますよう、お願いします。
連続シンポジウム「スタニスラフスキーは死んだか?」
第3回・総括:ラウンド・テーブル・セッション
日時 12月13日(土)14:00-18:00
場所 成城大学3号館大会議室
司会 日比野啓(成蹊大学准教授)
ディスカッサント 井上優(明治大学准教授)・新沼智之(明治大学非常勤講師)・毛利三彌(成城大学名誉教授)・安田比呂志(日本橋学館大学教授)・山下純照(成城大学教授)[五十音順]
西洋比較演劇研究会では、連続シンポジウム「スタニスラフスキーは死んだか?」を、これまで以下のように二回実施してきました。
2012年12月例会「スタニフラフスキー・システムの歴史的検証」(講師:浦雅春・堀江新二)
告知:西洋比較演劇研究会公式サイト
http://www.comparativetheatre.org/archives/281
概要:『西洋比較演劇研究』第12巻第2号「例会報告」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ctr/12/2/12_297/_pdf
2013年12月例会「日本におけるスタニフラフスキー」(講師:藤崎周平・笹山敬輔)
告知:西洋比較演劇研究会公式サイト
http://www.comparativetheatre.org/archives/317
概要:『西洋比較演劇研究』第13巻第2号「例会報告」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ctr/13/2/13_121/_pdf
最終年度となる今年度は、専門家をお招きしてその研究成果を伺うかわりに、これまで議論されてきた内容をもとに、西洋比較演劇研究会の会員有志によるラウンド・テーブル・セッションを行い、三年間の総括を行います。
※進行次第を以下のように変更いたしました(下記は変更後のみ記載)
直前の変更は望ましいものではないですが、聴衆のみなさまのより広汎な理解が得られ、結果としてフロアからのディスカッションが盛り上がることを期待して、苦渋の決断をいたしました。ご寛恕いただければ幸いです。
進行次第
第一部:スタニスラフスキー・システム基本概念の批判的検討(約60分)
第二部:司会からの『俳優の仕事』の「新しい」読み方の提案(約60分)
(休憩)
第三部:ディスカッサントによる議論:スタニスラフスキー・システムの現在における
有効性(約60分)
第四部:フロアからの議論・まとめ(約60分)
第一部:基本概念の批判的検討(約60分)
多様な解釈を許容する、矛盾をはらんだテクスト=「古典」としての『俳優の仕事』という前提をもとに、ディスカッサントおよび司会が、スタニスラフスキー・システムの基本概念(の一部)を説明し、その内実を批判的に検討します。新訳における訳語の適切さや、スタニスラフスキー自身の用語使用の「揺らぎ」についても言及されることになるでしょう。
[担当概念:担当者(変更の可能性あり)]
1. 魔法の<もしも>・与えられた状況:井上
2. 注意の対象(光の輪)・交感[交流]:安田
3. 断片と課題・ポドテクスト:山下
4. 「我あり」・適応・舞台における内的な自己感覚:日比野
5. 貫通行動[一貫した行動]・超目標[究極課題]:新沼
6. 身体的行動:毛利
第二部:司会からの『俳優の仕事』の「新しい」読み方の提案
21世紀の現在から、ほぼ百年前のテクストである『俳優の仕事』に書き込まれたイデオロギーや「偏向」について検討します。といっても、それは「あと知恵」でスタニスラフスキーを批判するためではなく、今スタニスラフスキーをアクチュアルなものとして読むために必要な「構え」を共有するためです。具体的には、以下の6点についてお話します。
1. リアリズム=「持続する時間」の表象
2. 科学主義
3. 機械論的人間観
4. 主体の統一性という神話
5. 折衷主義
6. 観客の観劇態度を教育するものとしての『俳優の仕事』
第三部:ディスカッサントによる議論:スタニスラフスキー・システムの現在における有効性
第一部・第二部で話し合われたことを受けて、スタニスラフスキー・システムの現在における有効性をディスカッサント間で自由に議論を行います。昨今の上演作品(国内・海外)における成功例・失敗例なども具体的に取り上げられることになるでしょう。
第四部:フロアからの議論・まとめ
第一部から第三部で話し合われたことを受けて、フロアから質問・疑問を受けつけ、必要があればディスカッサント・司会を交えて議論を行います。最後に司会がまとめを行い、今後のスタニスラフスキー・システムの活用の見通しを語ります。
会員のみなさんはふるってご参集ください。また非会員のかたのご見学も歓迎します。
当日お名前と(あれば)所属をお書きいただくだけで、事前のご連絡は不要です。

くださいますようお願い申し上げます。
日時 2014年10月4日(土)14:00-18:00
場所 成城大学3号館3F 大会議室
1 研究発表 田ノ口誠悟 14:00- 15:50
「ルイ・ジューヴェの演劇美学がはらむ政治的モチベーションについて」
近年、フランスの演出家グループ「カルテル」の一人で、20世紀前半の欧米を代表する演劇人、ルイ・ジューヴェ(Louis Jouvet, 1887‾1951)の仕事の見直しが行われている。ジューヴェはこれまで、その師であるジャック・コポーと同じく、戯曲・テクストを重視する演劇の提唱者、実践者と見なされてきた。しかし最近、大戦間期という彼が特に活躍した時代の文化的・社会的ダイナミズムの潮流の中でその仕事を捉え直す気運が高まっているのである。例えば、ジューヴェの未発表の演劇論を検証し、その演劇活動を、諸芸術・技術の超領域的混淆の時代であった大戦間期に特有の、実験的な手法を多用したスペクタクルの構想・実現過程として読み替える提案をしたエーブ・マスカローの研究は記憶に新しい(Louis Jouvet, introduction et choix de textes par Eve Mascarau, Paris, Actes Sud-Papiers, coll. ≪ Mettre en sc?ne ≫, 2013)。
本研究発表もこのような「大戦間期とジューヴェ」という視点に基づくものである。具体的には、芸術・演劇がかつてなく政治化した時代でもあった当時におけるジューヴェのポジションを探ることを目的とする。大戦間期においては、ロシア共産革命や第一次世界大戦といった未曾有の事変が、社会のあり方と向き合う作品を作らねばならないという問題意識を芸術家達にかき立て、演劇の領域においても、問題演劇やプロレタリア演劇、民衆演劇といった傾向的な表現が趨勢を占めた。
このような政治化する演劇シーンの中に組み込まれるものとしてジューヴェの演劇活動も理解されうるのではないか。本発表では、この「政治的演劇人ジューヴェ」という構想の第一段階として、彼の演劇論に読み取られる政治演劇の理念を明らかにする。
発表者プロフィール:たのくち せいご
早稲田大学文学研究科博士後期課程、パリ西大学視覚芸術学研究科演劇コース博士課程在学中。2010?2011年度フランス政府給費留学生ののち、日本学術振興会特別研究員(DC2, 2012?2014年)。2011年パリ西大学演劇学研究科修士課程修了。専門:民主主義体制下のフランスおよび日本における「政治的であること」を標榜した舞台芸術の歴史・理論の研究。
主な研究業績:① ≪ Le théâtre politique sur papier : une étude sur le rapport entre les drames giralduciens publiés et leur public », in Simona JISA et alii (dir.), Jean Giraudoux : écrire/décrire ou le regard créateur, Casa Cărţii de Ştiinţă, actes du colloque international 9-12 mai 2013, Cluj-Napoca, Université Babes-Bolyai, décembre 2013, pp. 47-54. ②「演劇とデモクラシー――政治的言論生産装置としてのジャン・ジロドゥ『ジークフリート』」、『フランス語フランス文学研究』103号、pp. 217-232, 2013年。③「ジャン・ジロドゥの《人民演劇論》」、『西洋比較演劇研究』、Vol. 12 No. 2, pp. 162-173, 2013年。
2 合評会16:00- 18:00
本会紀要『西洋比較演劇研究』第13巻第1号(英語)・第2号(日本語)に掲載された何本かの論文の合評会です。これまでも同様の合評会を何度か行なって参りました。紀要がWeb上公開となってからは、初めてとなります。執筆者の居住状況やスケジュールとの関係で、調整した結果、今回は次の4本のみについての合評会となります。それぞれ内容を要約することなく、ただちに各30分ほどの質疑応答をおこないたいと思います。
ご参会予定の方は、ぜひとも論文を読んでおいでください。
英語論文
“Revolutionary Theatre” or “Syncre-Theatre”: Derek Walcott’s Walker (2002) and the Representations of Temporality.
Yuri SAKUMA (p.39-54)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ctr/13/1/13_3/_pdf
Derek Walcott: A Caribbean ‘National Theatre’ vs. Neo-Colonialist Tourism.
Chihoko MATSUDA (p.69-81)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ctr/13/1/13_5/_pdf
日本語論文
ミュージカルThe Mystery of Edwin Drood における劇中劇構造と歌の劇的意義の分析
藤原 麻優子 (p.94-107)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ctr/13/2/13_2/_pdf
境界を内破する ─キャリル・チャーチル『トップ・ガールズ』における身体
鈴木 美穂 (p.108-119)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ctr/13/2/13_3/_pdf
執筆者紹介(刊行時点)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ctr/13/2/13_120/_article

本会ならではのシンポジウムを開催します。ご来場をお待ちしています。
シンポジウム:「18世紀ヨーロッパにおけるアルレッキーノの変容」
日時:2014年7月19日(土)14:00〜18:00
会場:成城大学3号館3F大会議室
司会:安田比呂志
発表:
奥香織「18世紀パリの縁日芝居におけるアルルカンの表象——ルサージュの作品を中心に」
安田比呂志「18世紀イギリスにおけるハーレクィンの変容——2作のパントマイム『ハーレクィン・ドクター・フォースタス』を中心として」
小林英起子「18世紀ドイツ・ザクセン類型喜劇におけるハルレキーン——クヴィストルプの喜劇における下僕の変容を例として」
趣旨:
ヨーロッパ演劇史の視点からみた場合、18世紀はコンメディア・デッラルテの歴史の中でも非常に興味深い世紀であると言える。18世紀は、コンメディア・デッラルテが上演台本通りの上演を行うことで即興性という本質的な性質を失い、オペラ・コミックとの合併(1762年)によって結果的に演劇史の表舞台から姿を消す世紀である一方で、巡業を通してヨーロッパの各国に根づいていたコンメディア・デッラルテの演劇的特徴が、それぞれの国において独自の展開をみせていた世紀でもあったからである。
ところが、この18世紀のヨーロッパにおけるコンメディア・デッラルテの独自な展開は、たとえばハーレクィン(アルレッキーノ)がその成立過程で重要な役割を果たしたイギリスのパントマイムの場合のように、当時の劇場文化を構成する重要な要素のひとつとなっていたにもかかわらず、その実像が具体的な形で紹介される機会が極めて少ないという現状が、今尚あるように思われる。
そこで今回のシンポジウムでは、コンメディア・デッラルテのヨーロッパにおける独自の展開の様相を明らかにするための第一段階として、コンメディア・デッラルテの様々な登場人物たちの中でも特にアルレッキーノを中心的に取り上げ、18世紀のフランス、ドイツ、イギリスで上演された、アルレッキーノが登場する作品や、そこに登場する役者の演技などを具体的に紹介しながら、それぞれの国にみられたアルレッキーノの変容の性質を検証して行きたい。
奥香織「18世紀パリの縁日芝居におけるアルルカンの表象——ルサージュの作品を中心に」
ルイ14世の時代にパリに定住したイタリア人劇団は1697年に国外追放となるが、イタリア喜劇の「類型」は縁日芝居に取り込まれ、独自に発展を遂げていく。中でもアルルカンは演目のタイトルそのものに頻繁に登場し、さまざまな役で人気を博した。とはいえ、縁日芝居は公権力に認められていなかったために制約も多く、18世紀初頭には対話が禁止されるなどの障害もあった。こうした中で、縁日のアルルカンは、「王の常設劇団」である新イタリア人劇団(1716年に来仏)とは異なるかたちで表象され、発展していく。それは、後のブルヴァール劇のアルルカンへとつながる存在でもある。非公式の場で活躍したアルルカンではあるが、そこには、演劇史における重要性が認められるのである。そこで、本発表では、18世紀初頭のパリの縁日芝居のアルルカンに注目し、その特徴と上演の実態を明らかにする。特に世紀初頭に人気を博したルサージュの作品を中心的に取り上げ、同時代の他のアルルカンとも比較しながら考察を行う。また、制約が多い中でアルルカンがどのように表象されたのか、形式と演技の観点からも検討したい。
プロフィール:
早稲田大学文学研究科博士課程単位取得退学、パリ第4大学博士課程修了。現在、早稲田大学、明治大学ほか非常勤講師。専門はフランスの舞台芸術(特に18世紀フランス演劇とその現代演出)、日仏演劇交流。論文:「マリヴォーとイタリア人劇団——演劇創造の源泉としての演技」(『西洋比較演劇研究』12号、西洋比較演劇研究会、2013)、「マリヴォーにおける「露呈」の演劇性」(『日仏国際シンポジウム 演劇と演劇性』、早稲田大学演劇映像学連携研究拠点、2014)など。
安田比呂志:「18世紀イギリスにおけるハーレクィンの変容——2作のパントマイム『ハーレクィン・ドクター・フォースタス』を中心として」
1723年、ロンドンで2作のパントマイムが上演された。ジョン・サーモンドの『ハーレクィン・ドクター・フォースタス』と、ルイス・ティボルドとジョン・リッチの『ネクロマンサー、あるいはハーレクィン・ドクター・フォースタス』である。ハーレクィンが主人公のフォースタス博士を演じるこれら2作のパントマイムは、18世紀のロンドンでパントマイムの人気を確立したことで良く知られているが、コンメディア・デッラルテの登場人物たちが、とりわけアルレッキーノがイギリスにおいて経験した「変容」の様相を具体的に示す実例という点でも、非常に興味深い作品となっている。
そこで本発表では、これら2作のパントマイムを中心に取り上げ、それらの上演の様子を可能な限り再現することで、21世紀の現在にまで高い人気を維持しているイギリスのパントマイムの伝統的な特徴を明らかにするとともに、フォースタスを演じるハーレクィンの姿をひとつの頂点とする、18世紀のイギリスにおけるアルレッキーノの受容と変容の様相について検証する。
プロフィール:
日本橋学館大学教授。専門はシェイクスピアを中心とするイギリス演劇。共著に『シェイクスピアの架け橋』(東京大学出版会、1998年)、『新訂ベスト・プレイズ』(論創社、2011)、『日本橋学館大学芸術フォーラム叢書3:18世紀ヨーロッパにおける演劇の展開』(2012)など、翻訳にトマス・オトウェイ作『スカパンの悪だくみ』(『西洋比較演劇研究』第11巻、2012)、ウィリアム・ダヴェナント作『劇場貸出し中』(同、第12巻、2013)などがある。
小林英起子:「18世紀ドイツ・ザクセン類型喜劇におけるハルレキーン——クヴィストルプの喜劇における下僕の変容を例として」
18世紀中葉、啓蒙演劇の中心ライプツィヒではゴットシェートの文芸理論が影響を及ぼしていた。それは道化役を良くは理解せず、スカラムーチェやハルレキーンを厳しく批評するものである。彼を囲む文学サロンに属していたのがクヴィストルプである。道化役追放を演劇改良の旗印とした彼らは、市民階級の主人公を誇張された性格と諷刺で描き、良徳と悪徳を示す類型喜劇を得意とした。
本発表では、クヴィストルプの1740年代の喜劇『牡蠣』、『山羊裁判』、『心気症の男』における下僕の役柄と喜劇性を比較し、コンメディア・デッラルテの影響の痕跡を検討する。クヴィストルプがいかに用心深くハルレキーンを変身させていったのか考察する。
18世紀初頭、即興芝居ハウプト・ウント・シュターツアクツィオーンではピッケルヘーリング等が滑稽役であり、フランス経由でハルレキーンが伝わった。ゴットシェートに翻弄されたノイバー座、組みしなかったハルレキーン役者およびウィーンのハンスブルストについても言及する。
プロフィール:
2009年より広島大学文学部教授。レッシング、ノイバー夫人、ザクセン類型喜劇、ゲーテ喜劇等18世紀ドイツ演劇・演劇史を研究。主書 „Lessings Anfaenge – Die fruehen Lustspiele im Kontext der Zeit.“ Bochum: Projekt Verlag 2003. 翻訳 T.J. クヴィストルプ作『心気症の男』(同学社)2009.

日時 2014年5月17日(土) 14:00-18:00
会場 成城大学 7号館、723教室
小田急線、成城学園前駅下車(急行可、快速急行は不可)、
北口徒歩3分(南口横に交番あり)。
内容 1 研究発表 山下純照
2 報告 永田靖
概要
1 研究発表 山下純照
「ドイツ演劇界におけるジョージ・タボーリ受容の変化——衝撃と拒否から肯定へ——」
要旨 演劇学会の最近の会報に寄せた拙稿「研究の視点:バースデイ・パーティ」からも察せられるように、1990年代前半から2007年の死に至るまでの晩年のタボーリは、ドイツ社会のいわば寵児となっていた。個々の演出や新作への手厳しい劇評がなかったわけではない。が、存在としてのタボーリは言わば不可侵の域に達していた。しかし彼は1971年の渡独後、常に好意的な評価を受けてきたわけではなかった。それどころか70年代のドイツ演劇界は全体として、タボーリに対しその先鋭性とドイツの制度になじまない創造スタイルのゆえに拒絶的であった。180度の転換と言えるこのような受容の変化はいかにして引き起こされたのだろうか。今回の発表では、70年代のタボーリを象徴する二つの上演『ピンクヴィレ』(1971年)と『断食芸人』(1977年)、評価転換期の話題作『わが母の肝っ玉』(1978年)と『ベケット・アーベント㈵』(1980年)、80年代後期の成功作『わが闘争』(1987年)とドイツ語圏文学者として最高の栄誉とされるビューヒナー賞の受賞作となった『ゴルトベルク変奏曲』(1991年)に触れながら、上の問いに答えることを試みる。手続きとしては、いくつかのTV映像からのヒントを皮切りに、劇評を最も基礎的な資料として用い、刊行されたテクストに基づく作品紹介をもおこないながら、活動内容の変化と反応の変化を連動させてみたい。仮説の形で、そうした変化とその背景をなす社会文化史との関連を若干展望するところまでを目標とする。
(注 論者はこれまでTaboriの表記を「タボリ」としてきた。しかし、ファーストネームのGeorgeが、ドイツではハンガリー風の「ジェルジ」ではなく、本人のアメリカ帰りを背景とした「ジョージ」であるのに合わせて、ファミリーネームも、同地で呼び慣わされている「タボーリ」に変更することにしたい。)
発表者プロフィール:やました よしてる
専門領域はドイツ語圏を中心とする近現代演劇、および演劇理論。記憶の概念からの現代演劇の再考察を進行中。成城大学教授。日本演劇学理事。
2 報告 永田靖
「文化庁「大学を活用した文化芸術推進事業;劇場・音楽堂・美術館等と連携するアートフェスティバル人材育成事業」について」
平成25年度に大阪大学文学研究科が中心になって獲得した表記補助金事業について、その簡単な概略を報告し、あわせてそこで明らかになった問題点と可能性について、文化庁事業が示す問題性と同時にその文化政策的な転換を、大学がどのように活用し、人材育成につなげて行くのか、またその際の問題点は何かなどについて、大阪大学文学研究科の事例に即して議論したい。
発表者プロフィール:ながた やすし
専門領域はロシア語圏及び日本の近現代演劇史。アジアの演劇研究のネットワーク構築を進めている。日本演劇学会事務局長、IFTR Asian Theatre WG 主宰。

日時 2014年4月12日(土)
会場 3号館3階大会議室
小田急線、成城学園前駅下車(急行可、快速急行は不可)、
北口徒歩3分(南口横に交番あり)。
14:00-15:00 総会
15:00-18:00 討論
「日本での国際舞台芸術祭における諸問題:イプセン演劇祭とフェスティバル/トーキョーを手がかりに」報告 毛利三彌 萩原健
※終了後会場にて懇親会を行う予定です。
【報告要旨】
報告1 〈現代イプセン演劇祭〉からの問題点 毛利三彌
(舞台そのものについて詳しく述べることはしないが、見ていない人も多いだろうから、名取事務所のHPに載せた私の演劇祭総括文−各舞台についての私の個人的感想ーを、あらかじめ読んでおいていただけるとありがたい。〈現代イプセン演劇祭総括〉でネット検索すれば出てくる。)
昨年11月から12月にかけて、東京で開かれた現代イプセン演劇祭(「人形の家」特集)では、6つの舞台が上演された。そのうち4つが海外の舞台であったが、そこから出てきた演劇上演に関する問題、すなわち、演技の問題、近代古典劇上演の問題、字幕の問題について思うところを述べたい。
(i)演技の問題
今回の演劇祭で、ノルウェーの女優ユーニ・ダールの一人芝居「イプセンの女たち」の演技に多くの賛辞が寄せられた。彼女は、自分の演技はスタニスラフスキー・システムを土台としていると言っていたが、昨年度来、スタニスラフスキー・システムの再検討が、研究会のテーマの1つになっていることもあり、彼女の演技が、日本の新劇の演技とどう違っているのか、なぜ違っているのかを考えてみたい。
(ii)近代古典劇上演の問題
4つの海外舞台は、それぞれに演出方針が全く異なっていた。これはイプセンに限らず、近代古典劇現代上演の一般的状況であると思われる。いずれも、私の舞台を含めて、日本の上演とは違った形をとっている。おそらく歴史的事情と社会状況の違いによるものであろう。特に、独裁政権崩壊後のチリの「ノーラ・ヘルメルを追いかけて」の舞台から、それを強く感じた。比べて、日本の演劇状況のたるんでいることも。だがこの論を進めていくと、たるんだ若者を鍛えるために徴兵制度を復活させるべきだ、というような議論になりかねないところもある。
(iii)字幕の問題
海外からの舞台では、一時流行ったイヤホンによる同時通訳方式はほとんど姿を消し、いまは、大半が字幕方式をとっている。だが、多くが十全なものではなく、字幕で舞台の成功不成功が左右されることも少なくない。なかなか解決できない問題だが、実際には、制作上の問題にとどまらず、戯曲翻訳学の重要問題となる可能性がある。外国舞台の映像記録としても考察すべき問題だろう。このような問題提起に対する出席者の討論を期待したい。
《プロフィール》
毛利三彌(もうりみつや)、成城大学名誉教授、元日本演劇学会会長
主な著書編書:『北欧演劇論』、『イプセンのリアリズム』(日本演劇学会河竹賞)、『イプセンの世紀末』、『演劇の詩学』、『演劇論の変貌』(編著)。主な訳書:『北欧文学史』(共訳)、『講談社世界文学全集 イプセン、ストリンドベリ集』、『イプセン戯曲選集−現代劇全作品』(湯浅芳子賞)主な演出:イプセン現代劇連続上演(名取事務所1999〜2012)
報告2 フェスティバル/トーキョーとリミニ・プロトコル 萩原健
2009年春に始まった国際舞台芸術祭、フェスティバル/トーキョー(F/T)は昨秋で6回目を数えた。本報告では、F/Tの概況報告に続けて、繰り返し招かれている国内外の作り手のなかからリミニ・プロトコル(2000年結成)を取り上げ、彼らがF/Tで発表し、報告者がその制作に関わった3作品——『カール・マルクス:資本論、第一巻 東京ヴァージョン』(09年春)、『Cargo Tokyo-Yokohama』(09年秋)、『100% トーキョー』(13年秋)——を中心に、そのクリエーションにおける、演技、近代古典劇の現代化、字幕の各点について検討する。またここから導かれる、F/Tの特徴と課題について考えたい。
《プロフィール》
萩原健(はぎわらけん)
明治大学国際日本学部准教授。
現代ドイツ演劇および関連する日本の演劇。共訳に『パフォーマンスの美学』(2009)、共著に『演劇インタラクティヴ 日本×ドイツ』(2010)、『村山知義 劇的尖端』(2012)ほか。戯曲翻訳、稽古場通訳、字幕翻訳・制作・操作も手掛ける(萩原ヴァレントヴィッツ健)。